私が大学を卒業して記者になったのは去年のこと。社会に出たばかりの私が、最初に担当したのが「若者と薬物」というテーマでした。正直、自分と同世代の問題だけに、取材を重ねるたびに胸が締め付けられる思いです。
2024年、日本の薬物事情は新たな局面を迎えています。かつては「よその世界の話」と思われていた薬物問題が、いつの間にか私たちの日常に忍び寄っていました。
先月発表された警察庁のデータによると、大麻取締法違反で摘発された中学生は昨年26人。過去最多を記録しています。さらに気になるのは、大麻摘発者の約7割が20代以下という現実です。
私は数週間かけて専門家や当事者、取り締まる側の声を集めました。そこから見えてきたのは、表面的な数字だけでは語れない若者たちの複雑な現実でした。
恐ろしい増加傾向──無視できない現実
警察庁の統計を見ると、ここ数年の大麻摘発者数の増加には目を見張るものがあります。特に若年層においては、右肩上がりの増加が顕著です。
以下の表をご覧ください。
大麻摘発の推移(2020〜2024年)
年 大麻摘発者数(全体) 20代以下の摘発者数 中学生の摘発者数
2020 4,100人 2,500人 9人
2021 4,600人 2,800人 12人
2022 5,100人 3,200人 17人
2023 5,400人 3,500人 20人
2024 5,700人 4,000人 26人
出典元:
Yahoo!ニュース|大麻で摘発の中学生は過去最多26人(2024年)
「たった5年で中学生の摘発数が3倍になっているなんて…」取材中、警察の薬物対策課で働く40代の警部はため息をつきながらこう語りました。「これはあくまで摘発された数に過ぎない。実際の使用者はもっと多いはずです」
私はこの数字を見て、同世代の友人たちのことを思い出しました。大学時代、「アメリカでは合法だから」と軽い気持ちで大麻を試した知人が何人かいたのです。当時は「バカなことをして」と思っていましたが、今思えば彼らも「流れ」に乗っていただけなのかもしれません。

「“流れ”って怖いよね。自分は大丈夫って思ってても、気づいたら踏み込んでることある」
スマホ1台で手に入る「禁断の実」
「初めて大麻を吸ったのは11歳の時」
都内の更生施設で会った16歳の少年Aくんはそう告白しました。小学5年生という年齢で、どうやって薬物にアクセスできたのか。その答えは意外にシンプルでした。
「SNSで知り合った高校生から。最初はタダでもらえた」
現代の若者にとって、スマートフォンとSNSは生活の一部。でも、それが「新しい密売所」になっているという現実を、私たちは直視する必要があります。
取材で分かった現代の大麻流通経路は次のようなものです。
- Instagram・Xなどで「🍃」「💨」などの絵文字や隠語を使った売買サイン
- 匿名性の高いTelegramやLINEオープンチャットでのやり取り
- 見た目がお菓子やタバコに似せた大麻製品(VAPEタイプやグミ型)
「クラスの中で大麻の話を聞かない月はないよ」
東京都内の公立中学に通う3年生の男子生徒はこう語りました。彼の話によると、最近は電子タバコが「クール」とされ、その中身が何か分からずに使っている生徒もいるそうです。
私は取材中、実際に押収された「大麻グミ」を見せてもらいましたが、市販のグミキャンディとの区別がつきませんでした。これが教室や公園で堂々と食べられている現実に、ゾッとします。

空虚を埋める「何か」を求めて
では、なぜ彼らは薬物に手を出すのでしょうか。単純に「好奇心」や「カッコつけ」だけではないようです。
都内の中学2年生だったBさん(14歳・女子)のケースが印象的でした。彼女は現在、病院での治療を受けています。
「両親は共働きで、帰っても誰もいなかった。学校では『キモい』って言われてLINEグループからも外されてた。SNSで知り合った高校生のお兄さんだけが優しくしてくれて…」
そのお兄さんから「リラックスできるよ」と渡されたグミが大麻入りだったのです。
「最初は気持ち良くて、全部忘れられた。でも次第に不安になって、何も楽しくなくなって…」
この話を聞いた時、私はBさんと同い年だった自分の妹を思い出して、胸が痛くなりました。誰にでも起こりうることなのかもしれない。
専門家によれば、大麻使用の背景には「孤独」「居場所のなさ」「承認欲求」などの心理的要因が大きいとのこと。薬物は「快楽を得るため」だけでなく、「痛みから逃れるため」に使われることも多いのです。

「“楽しくなるため”じゃなくて、“つらさを消したくて”って…それが一番切ない理由だよね」
「大麻は安全」という危険な誤解
「アメリカとかでは合法なんだよね。タバコより体に悪くないって聞いたよ」
取材で出会った高校生の多くがこのような認識を持っていました。確かに世界的に見れば、大麻の合法化は進んでいます。カナダやアメリカの多くの州では嗜好品としての使用が認められています。
しかし、この「世界の常識」が日本の若者たちに誤解を招いているのも事実です。
専門医に話を聞くと、次のような指摘がありました。
- 脳が発達途上の10代での使用は、脳機能に回復困難な影響を与えることがある
- 精神疾患のリスクが高まる(特に統合失調症との関連性は複数の研究で指摘)
- 合法化された国でも、未成年への使用は禁止されている
大麻が「安全」ではなく、あくまで「管理された枠組みの中で一定のリスクを許容している」というのが世界の実情です。それを理解せずに「海外では普通」という部分だけを取り入れるのは危険です。
正直、私自身も大学時代までは「大麻ぐらい」と軽く考えていた一人でした。しかし依存症治療の専門家や当事者の話を聞いて、その認識が甘かったと反省しています。
対策は急務だけど、「脅し」だけでは不十分
では、この問題にどう対処すればいいのでしょうか。
法律や規制を強化する動きはもちろん重要ですが、「ダメ、絶対」の一辺倒な教育だけでは効果が薄いと言わざるを得ません。実際、取材した中学校の教師も「脅しの教育は子どもたちの心に届かない」と嘆いていました。
専門家の間では、次のような対策が議論されています。
- 教育のアップデート
- 「怖い写真」や「刑罰の厳しさ」を見せるだけでなく、実際の体験談や科学的根拠に基づいた教育
- 若者に影響力のあるインフルエンサーを起用した啓発活動
- 家庭での対話環境の整備
- スマホの制限よりも、親子の会話を増やすことが重要
- 子どもの異変に早く気付くための「サイン」を親が学ぶ
- デジタル対策の強化
- SNS企業との協力による違法取引の監視強化
- AIを活用した早期発見システムの導入
- 心のケア体制の充実
- 学校へのカウンセラー常駐や専門相談窓口の拡充
- 初犯の場合は処罰よりも治療・サポートを優先する仕組み
ある依存症治療の医師は「子どもたちは『大麻はダメ』という結論だけでなく、『なぜダメなのか』を本気で知りたがっている」と語りました。納得感のある教育が必要だというのです。
「うちの子は大丈夫」という幻想
取材を終えて感じたのは、もはや「うちの子に限って」という考えは通用しない時代になったということ。
ある中学校の保護者会では「うちの学校にそんな問題はない」と声を上げた親御さんもいたそうですが、その学校でも実際には摘発事例があったといいます。
子どもたちが持つスマホ1台で、「大人が想像もつかない世界」とつながっている現実。私たち大人は、その事実と向き合わなければなりません。
若者の薬物問題は、単に「薬物が悪い」「使う子が悪い」という単純な図式では語れません。その背景には、現代社会の孤独や不安、情報過多と対人関係の希薄さなど、複雑な要因が絡み合っています。
取材を通じて出会った子どもたちの多くは、決して「不良」ではなく、むしろ繊細で傷つきやすい子たちでした。彼らが薬物に頼らずとも心の安定を得られる社会を作ることが、大人たちの責任なのかもしれません。
(みく/21歳・社会部記者)
【速報】大麻で摘発の中学生は過去最多26人 20代以下が7割、若者へのまん延深刻…“初めて使った年齢”11歳との回答も 2024年調査
大麻問題 #若者の薬物乱用 #中学生摘発 #薬物教育 #SNSと薬物 #家庭の役割 #社会的対策


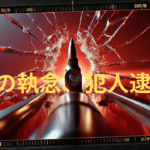




コメント