退職金への課税強化が「サラリーマン増税」ではないかと騒がれている。もともと退職金には長年勤めた人ほど税負担が軽くなる優遇措置があった。だが、雇用の流動化が進む現代において、この仕組みが「時代遅れ」だと指摘されるようになってきた。
政府は見直しを進める構えだが、国民の間では「老後資金にまで手をつけるのか?」と不安が広がっている。果たして、退職金への課税強化は本当に必要なのか。それとも、ただの増税なのか。
退職金課税の現状と時代遅れの仕組み
まず、現在の退職金課税の仕組みを見てみよう。
退職金の控除額(2024年現在)
| 勤続年数 | 控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 1年あたり40万円 |
| 20年以上 | 20年を超えた分は1年あたり70万円 |
この制度では、勤続年数が長いほど控除額が増える。つまり、長く同じ会社で働いた人ほど退職金にかかる税金が少なくなるわけだ。これは、終身雇用が当たり前だった時代には理にかなった制度だった。
しかし、今は転職が当たり前の時代。新卒から定年まで同じ会社に勤める人はどんどん減っている。転職組にとっては「なんで長く勤めた人だけが優遇されるの?」という疑問が出てくるのも当然だろう。
見直しの背景と政府の本音
石破首相は「慎重な上に適切な見直しをすべき」と発言している。つまり、「見直すことは決まっているが、あまり強く反発されないように慎重に進める」という意味だろう。
では、政府はなぜこの見直しを進めようとしているのか?主な理由は以下の3つだ。
1. 雇用の流動化と「不公平感」
- 転職する人が増え、「長く勤めた人だけが得をするのはおかしい」という声が出てきた。
- 労働市場の流動性を高めるためには、退職金制度も時代に合わせるべきだという意見がある。
2. 経済環境の変化
- 企業にとっては、長く勤めてもらうより、必要なスキルを持った人材を採用・活用する方が重要になってきている。
- 退職金制度を「企業に長く縛りつけるための仕組み」として残すことに、経済界からも疑問の声が上がっている。
3. 財源確保の必要性
- 社会保障費は増える一方で、税収をどこかから確保しなければならない。
- 退職金の税制を見直せば、新たな税収源になる。
政府の本音としては、やはり「税収が欲しい」という部分が大きいのではないか。
国民の不安と「サラリーマン増税」への反発
当然ながら、こうした動きに対して国民の反応は冷ややかだ。特にサラリーマン層からは「退職金にまで課税を強化するのは実質的な増税ではないか」という声が上がっている。
主な意見
| 意見 | 内容 |
|---|---|
| 退職金課税への反発 | 「何十年も働いてやっともらえる退職金にまで税金をかけるなんて、やりすぎだ」 |
| 転職者の不安 | 「転職が当たり前の時代なのに、税制がそれについていっていない」 |
特に「老後資金としての退職金」という意識が強い日本では、ここへの課税強化はかなりセンシティブな問題だ。政府としては「転職者のため」と言いたいのかもしれないが、実際には「税収のため」と受け取られてしまうのも仕方がない。
今後の議論のポイント
では、退職金課税の見直しはどのように進められるべきなのか。ここで重要なのは、単に「課税強化=増税」という図式ではなく、「より公平な制度をつくる」という視点を持つことだろう。
今後、議論されるべきポイントは次のようなものだ。
- 転職者と長期勤続者の税負担をどうバランスさせるか
- 退職金を老後資金として確保するための負担軽減策はあるのか
- 雇用の流動性を妨げず、かつ退職金を安心して受け取れる制度設計
政府が「慎重な上に適切な見直し」をすると言うなら、本当に働く人のことを考えた税制にしてもらいたい。単なる増税ではなく、働き方の変化に合わせた制度改革になるのか。今後の議論の行方に注目が集まる。
#退職金 #増税 #石破首相 #雇用流動化 #税制改革 #サラリーマン増税 #転職 #老後資金
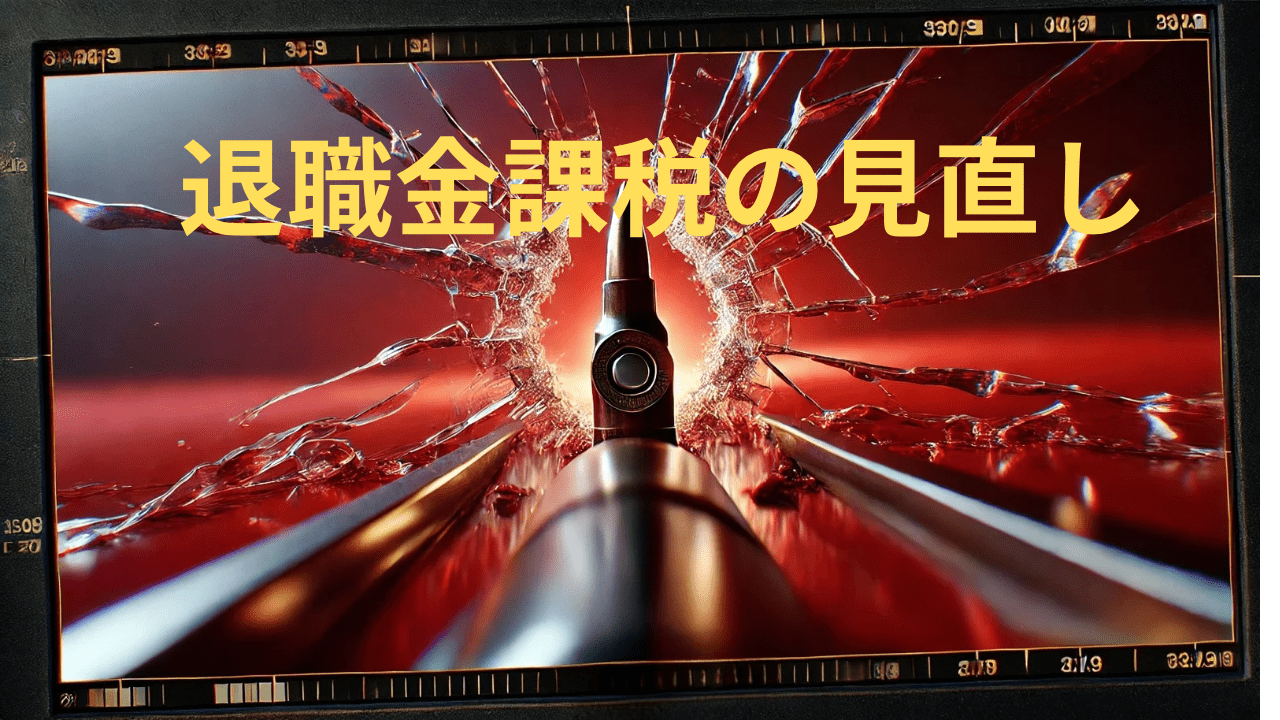



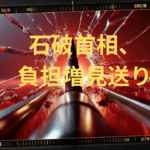
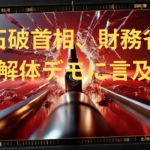
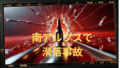

コメント