文・かずみ(ルポライター)
【注目ポイント】
- 担任教師が児童の成績表を誤送信
- クラス全保護者に一斉配信という個人情報流出
- 学校は緊急で保護者説明会を開催
- 教育現場の情報リテラシーの課題が浮き彫りに
教育現場に起きた”誤送信”の衝撃
「え、これって…全員の成績?」
北海道・稚内市にある市立小学校で、2025年春、新学期の準備に追われていたある担任教師が信じられないミスを犯した。「時間割表」として保護者に送信したメールに、誤って児童全員の成績一覧を添付。クラス全保護者に届いてしまったことで、深刻な個人情報漏洩事故が発生した。
私は現地に赴き、保護者や学校関係者に話を聞いた。一人の母親はスマホを見せながら、「これが送られてきたんです」と教えてくれた。そこには確かに、クラス全員の成績が一目で分かる表が広がっていた。

成績一覧を一斉送信とか…想像だけで胃が痛い
添付された情報の中身(例)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 児童名 | フルネーム記載 |
| 教科別評価 | 国・算・理・社など5段階評価 |
| 個別コメント | 教師からの具体的な所見 |
| 学年・クラス | 明記されていた |
| 総合評価 | 総合的な学習成績の傾向 |
「時間割のつもりが成績表を添付してしまった」という担任教師の釈明。しかし、この”単純ミス“が引き起こした波紋は想像以上に大きい。
「冗談じゃない」—保護者たちの怒りと不安
説明会は学校の体育館で行われた。集まった保護者の表情は硬く、空気は重かった。
「うちの息子、算数が『2』だったって、みんなに知られたんですよ。これからクラスの子たちにどう接していけばいいんですか」
30代の男性保護者は声を震わせていた。別の母親は「子どもの成績は家庭内でさえ慎重に扱うのに、こんな形で公開されるなんて」と涙ぐんだ。
私が数日かけて取材した限り、保護者からは以下のような声が多く聞かれた:
- 「子どもの評価が他人に知られる恥ずかしさ、分かりますか?」
- 「これじゃあSNSで拡散されても文句言えないじゃない」
- 「うちの子、前からクラスで成績のことでからかわれてて…これで余計に…」
これらの声を聞きながら感じたのは、成績という「数字」が子どもたちのアイデンティティや自己肯定感と深く結びついているという現実だ。それが一瞬で他者に晒される恐怖は、単なるプライバシー侵害を超えたものがある。

成績って、“ただの数字”じゃなくて、心まで傷つけるんだよね…
「時間に追われていて…」—教員の過酷な現場
「申し訳ありません…本当に申し訳ありません」
説明会で頭を下げ続けた40代の女性教師。彼女は市内でも評判の良い先生だったという。なぜ、こんなミスが起きたのか。学校外で彼女の同僚に話を聞くことができた。
「正直、彼女だけのせいじゃないんです。残業は当たり前、休日出勤も。そんな中での新学期準備で、誰でもミスはあり得ます」
確かに、教育現場の労働環境は過酷だ。文部科学省の調査によれば、小学校教員の平均残業時間は月約80時間。過労死ラインとされる80時間に到達している。
その一方で、ITスキルや情報管理に関する体系的な研修はほぼ皆無に等しい。この事が問題だと私は思う。
学校現場の構造的な問題点
私が取材を進めるうちに見えてきたのは、単なる個人のミスではなく、教育現場全体の抱える構造的な問題だった。
市教育委員会の担当者は「各学校での情報管理については、基本的に学校裁量に任せている部分が大きい」と話す。つまり、統一したルールやシステムが存在しないのだ。
教育現場の情報管理体制:現状と問題点
| 項目 | 現状 | 問題点 |
|---|---|---|
| 添付ファイル確認 | 担任教師の判断任せ | ダブルチェック体制が不在 |
| 一斉送信メール | 簡易的に実施されている | 誤送信時のリスクが大 |
| 情報管理マニュアル | 存在しない、または形骸化 | 運用されていない |
| IT研修 | 年に1回あるかどうか | 実効性に欠ける |
| 管理システム | 学校によってバラバラ | 導入に地域差が大きい |
ある校長は匿名を条件に本音を漏らした。「予算も人手も足りない。デジタル化を進めろと言われても、現場は追いつかない。それでいて保護者とのコミュニケーションは増やせと…矛盾だらけです」この事は保護者側にも理解が必要で、学校側ばかりに解決の糸口を押しつけても解決はしない。
ヒューマンエラーを防ぐには
「そもそも、なぜファイル名に『成績_3年1組.xlsx』と『時間割_3年1組.xlsx』のような似た名前をつけるんですか?」
私がある教育関係者に尋ねると、「それが普通なんです」という返事が返ってきた。教員たちの多くは、ITに特化した訓練を受けていない。だから、ファイル管理の基本的なルールすら知らない場合が多いという。
教育工学を専門とする大学教授は、「現場の教員には、情報管理よりも授業や生徒指導を優先せざるを得ない現実がある」と指摘する。確かに、彼らの本業は「教育」であって「情報管理」ではない。
しかし、デジタル社会において、その線引きはもはや不可能なのではないだろうか。

“教育が本業”でも、情報管理はもう避けられない時代だよね
現場から考える具体的な対策
「二度とこんなことを起こさないためには?」
この問いに対して、専門家や現場の教員たちから出た案をまとめると:
推奨される改善策
| 改善項目 | 対応例 |
|---|---|
| 添付ファイル確認 | 上司・副担任による事前チェックの義務化 |
| 情報共有手段の見直し | メールから教育向けアプリ(Classi、Google Classroom等)へ移行 |
| IT研修の強化 | 年2回以上、全教員必須の情報管理講習を実施 |
| 送信ログの保存 | 送信履歴を学校サーバーに自動保存し、監査可能に |
| 個人情報マニュアル | 校内での作成・配布と年1回の確認テスト |
実際に取材した学校では、この事件を受けて「メール送信前に必ず教頭または副担任に内容確認をする」というルールを急遽導入したという。
しかし私が感じたのは、こうした対策が本当に現場に定着するのか、という懸念だ。教員の長時間労働が改善されない限り、どんな素晴らしいルールも「やらなければならないこと」が一つ増えるだけになりかねない。
こんなことで解決するくらいなら、この事件はそもそも起きていない。原因はもっと根深く、奥深い所に存在すると思った。上にまとめた表を見て、誰が「これで大丈夫だ!」と言えるのか?
子どもたちへの影響
この問題で最も気がかりなのは、当事者である子どもたちへの影響だ。
「成績が低い子が、からかわれていないか心配です」と、ある保護者は話す。子どもの世界は時に残酷だ。大人が想像する以上に、こうした情報が子どもたちの関係性に影響を与える可能性は高い。
学校は臨時のカウンセラーを配置し、子どもたちのケアに努めているという。しかし、傷ついた信頼を回復するのは容易ではない。
また、意外な視点を提供してくれたのは、あるIT企業に勤める保護者だった。
「子どもたちにとって、これは情報リテラシーを学ぶ機会になるかもしれない。『情報が漏れるとどうなるか』を実体験として知ることで、将来、彼ら自身が情報を扱う際の教訓になるのでは」
確かに、失敗から学ぶことも多い。しかし、その代償があまりにも大きいとは思えないだろうか。

教訓になるかもしれない。
でも、子どもたちの心が傷ついたら意味ないよね…
私たちはどう向き合うべきか
正直に言おう。こうした問題は、教育現場だけでなく、私たち一人ひとりの日常にも存在している。
仕事のメールで添付ファイルを間違えたことはないだろうか?グループLINEで送るつもりだった写真を、別のグループに誤送信したことは?
デジタル社会において、情報の流出は一瞬で起こり得る。そして、一度流出した情報は完全に回収することはできない。
今回の事件は、学校という密閉された環境で起きた。しかし、これがインターネット上で起きていたら、その影響はさらに計り知れないものになっていただろう。
我々は「情報を扱う責任」について、もっと真剣に考えるべき時が来ているのではないか。

情報って便利だけど、扱い方ひとつで誰かを傷つける…怖いよね
終わりに
この原稿を書き終える頃、稚内の学校からある連絡が入った。
「メールでの配信をやめて、専用アプリに切り替えることになりました」
小さな一歩かもしれないが、変化は始まっている。問題は、この変化が一時的なものに終わるか、教育現場全体の意識改革につながるかだ。
数字や評価に一喜一憂する現代社会で、子どもたちの成長を守るためにできることは何か。引き続き、この問題を追っていきたい。
(かずみ)
児童の成績がクラスの保護者全員に…「時間割と間違え」担任が誤送信 学校が緊急の保護者説明会 稚内市
情報漏洩 #学校トラブル #教育現場 #個人情報 #メール誤送信 #成績表 #稚内市 #教師ミス #保護者説明会
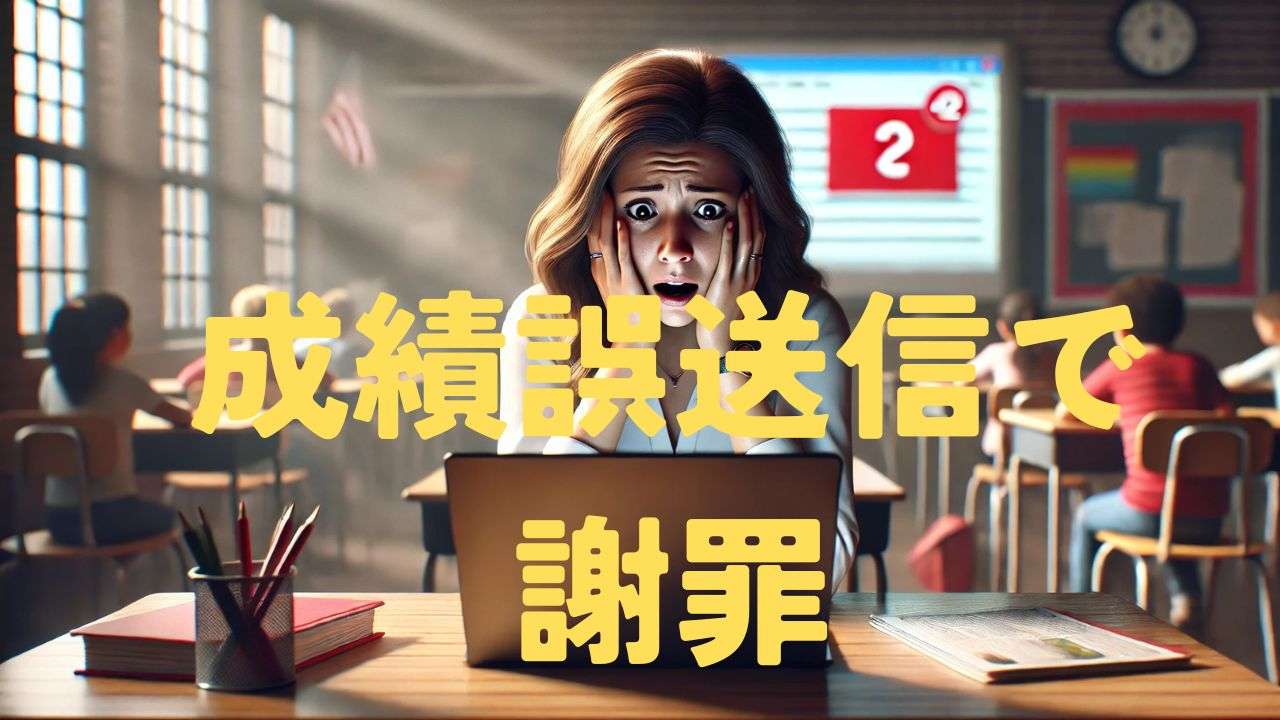






コメント