取材・文 みゆき(21歳ルポライター)
「あれ、何か貼ってある」
大阪・住之江区の商業施設ATCに足を踏み入れ、まず目に飛び込んできたのは、ストリートピアノ脇の小さな立て札だった。
「手前よがりな演奏は”苦音”です」
「練習は家でお願いします」
正直、最初は意味がよく分からなかった。「苦音」って何?「下手な人は弾くな」ってこと?そんな疑問を抱きながら、私は取材を始めた。
現場はノリノリの若者たち
平日昼間だというのに、ピアノ周辺には10人ほどの若者が集まっていた。彼らの多くはスマホを手に持ち、カメラの角度を調整している。
「初めて来たんですか?」と声をかけると、黒髪の男子高校生が笑顔で答えてくれた。
「うん、今日3回目。TikTokに上げたくて」
彼の名は佐藤君(仮名・18歳)。学校をサボって来たという彼は悪びれる様子もなく、「これでバズったら学校なんて行かなくていいし」と笑う。その自由な態度に、少し驚いた。
ちょうどそこへ、別の男性がピアノに向かい、鍵盤を叩き始めた。少し固い表情で、何度も同じフレーズを繰り返している。どうやら『残酷な天使のテーゼ』らしいが、音がところどころ外れていて、聴いていて少し疲れる。それでも彼は30分、40分と弾き続けていた。
これが、問題の「苦音」なのだろうか?

“バズりたい”って気持ちは分かるけど…耳にはちょっとキツいかも
SNSで吹き荒れる二極化した議論
この「苦音」投稿がネット上で拡散され、賛否両論の嵐が吹き荒れている。ぶっちゃけ、議論は不毛なレベルまでエスカレートしていると感じた。
ある投稿では「音楽をやったことない人間が上から目線で批判するな」と激しく怒り、また別の投稿では「公共の場のルールも守れないガキは家でやってろ」と罵り合いに発展していた。
表面的には「音楽の自由」VS「公共マナー」という対立軸だけど、本当はもっと複雑な問題がここにある気がする。
喫茶店のおばちゃんが教えてくれたこと
「あんたも記者さん?」
ATCの小さな喫茶店で休憩していると、店主のおばちゃんが話しかけてきた。この騒動以来、何人もの記者が来ているらしい。
「正直言うとね、うるさい時もあるよ。特に下手くそな子が何時間も同じとこ弾いてると、お客さんから『あのピアノどうにかならんの?』って言われることもある」
でも彼女は続けた。
「でもね、昔ピアノ習ってたけど挫折した人とか、家にピアノがない子とかが、楽しそうに弾いてるの見ると、それはそれでええなって思うんよ」
その言葉に、問題の複雑さを感じた。技術の上手い下手より、「その場にいる人たちとどう共存するか」が大事なんだと。

うるさいけど、楽しそうに弾いてる姿見ると許せちゃう…って、わかる気がする
表を作ってみた!SNSでの反応まとめ
| 立場 | 主張内容 | よく見られるコメント |
|---|---|---|
| 賛成派 | • ストリートピアノの本質は「自由に弾ける」こと • 演奏の上手下手を評価するのはエリート主義 • 運営側の言葉が演奏者を傷つける | 「誰でも弾けるからこそ意味がある」 「音楽の多様性を認めない発想」 |
| 反対派 | • 公共の場での「練習」は迷惑行為 • 「自由」には「責任」が伴う • 他の利用者の権利も尊重すべき | 「自己満足で周囲を不快にする権利はない」 「マナーの問題であって、技術の問題ではない」 |
でも、ネットの意見って極端に振れがちだよね。実際には、もっとグラデーションがあるはず。
個人的には、「あいつウザいし帰れ」って思いながらも「でも言いづらいよね…」って思うような、そんな複雑な気持ちの人が多いんじゃないかと思う。
そもそもストリートピアノって何?
そういえば、ストリートピアノの歴史について調べてみると、2008年にイギリスのアーティスト、ルーク・ジェラムさんが始めたプロジェクト「Play Me, I’m Yours」が発端だって知った。
彼の意図は「都市の公共空間に人々が集まり、交流する場所を作ること」だった。日本では2010年代から広がり始めたけど、最近はSNSと絡んで「ちょっとしたステージ」みたいな感じになってるよね。
あ、そうそう、先月ロンドンに研修旅行で行った時、駅でストリートピアノを見かけたんだけど、日本と雰囲気が全然違った。みんな5分くらいで交代して、下手でも拍手が起きるし、なんか自然な感じ。日本だとずっと一人で弾き続ける人も多いし、トラブルも起きやすいのかも。文化の違いかな?
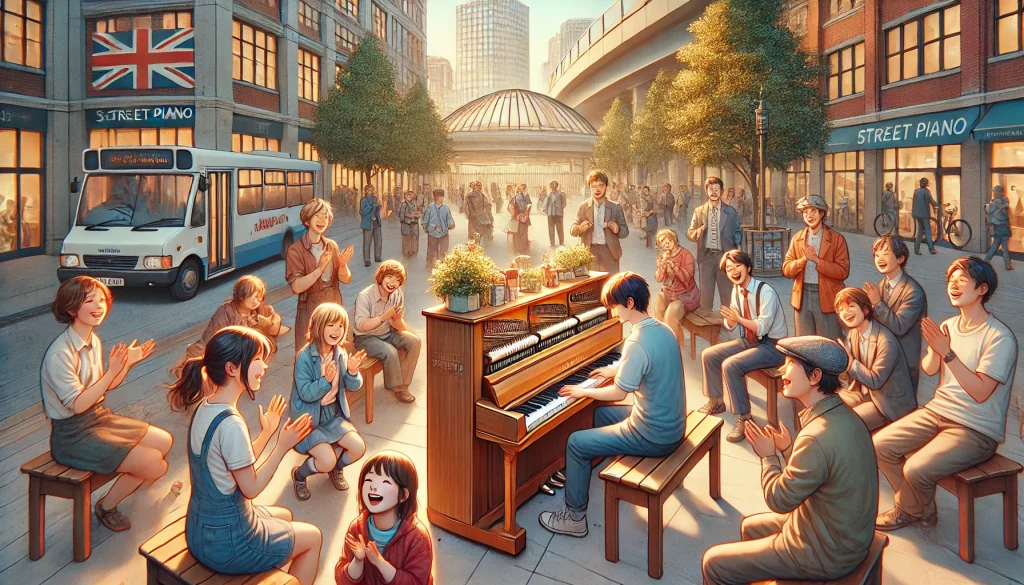
運営スタッフの本音
取材2日目、運営側のスタッフに話を聞くことができた。
「あの、『苦音』の件なんですが…」と切り出すと、30代くらいの男性スタッフは少し疲れた顔で答えてくれた。
「正直、あの表現は良くなかったと反省してます。でも、困ってたんですよ。特に週末なんか、同じ人が何時間も独占して、他の人が弾けなかったり。周りのお店からもクレームが来てて…」
彼によれば、施設側としては「技術の良し悪し」ではなく「共有スペースとしてのマナー」を訴えたかったそうだ。でも「苦音」という言葉が独り歩きしてしまった。
「表現を変えようと考えてます」と彼は言っていた。

“苦音”じゃなくて、“思いやりの音”とかに変えたらいいのにね
マサくんの話ーどんな音楽が「苦音」なのか
取材3日目、ピアノを弾いていた20歳くらいの男性、マサくん(仮名)に、彼なりの「苦音」の定義を聞いてみた。
「それはやっぱり、自分にしか届いてない音楽じゃないスか?僕は上手くないけど、誰かに聴いてもらいたいから弾くんです。でも、明らかに練習してるだけの人もいて、それはちょっと…」
彼は学生時代に軽音楽部でドラムをやっていたそうだ。「バンドだと自然と『聴き手』を意識するけど、ピアノだとそれが薄れがちかも」と言う彼の分析は、鋭いなと思った。
どうすれば解決するの?
単純に考えると、「時間制限を設ける」のが一番手っ取り早いかもしれない。例えば「混雑時は15分まで」とか。でもそれって本当に「自由なピアノ」なのかな?
もっと理想を言えば、演奏者と聴き手の間に自然な「対話」が生まれることが望ましい。でも日本人って、面と向かって「ちょっとうるさいかな」とか言いにくいんだよね。
お、そうだ!こんなアイデアはどうだろう?ピアノの横に「今日の感想ボード」みたいなのを置いて、聴いた人が簡単なコメントを書けるようにする。そうすれば「誰かに聴いてもらってる」という意識も生まれるし、「練習モード」になりすぎることも防げるかも。
そもそも「苦音」じゃなくて「共音」を目指すべきなんじゃないかな。一人で奏でるんじゃなくて、そこにいる全員で作り上げる音楽。

“苦音”じゃなくて“共音”って…めっちゃ素敵な発想じゃん!
どうしても言いたいこと
この問題、正直どっちが「正しい」とか言い切れないと思う。でも、2日間現地にいて感じたのは、要は「コミュニケーション不足」なんだよね。
演奏者は「自分の世界」に入りすぎず、周りの反応を見てほしい。
聴き手は「下手だから」で判断せず、その「想い」を感じ取ってほしい。
運営側は一方的なルールを押し付けず、利用者との対話を大事にしてほしい。
「自由」って、実は一人じゃ成り立たないんだよね。誰かの「自由」が他の誰かの「不自由」になることもある。でも逆に、お互いを尊重すれば、もっと大きな「自由」が生まれるかもしれない。
ストリートピアノから見える社会の縮図。そんなことを考えながら、私も最後に勇気を出して『海の見える街』を弾いてみた。めちゃくちゃ下手だったけど、誰かが小さく拍手してくれて、なんだか嬉しかった。

【追記】
実はこの記事を書いた後、ATCにもう一度行ってみたら、例の「苦音」という言葉が「迷惑」に変わっていた。小さな一歩だけど、対話は始まっているのかもしれない。あと、夕方に行ったせいか、ちょうど仕事帰りのおじさんが『千の風になって』を弾いていて、それがめちゃくちゃ上手かった。周りに自然と人が集まって、拍手が起きたりしてて。「こういうのが理想なんだろうなぁ」って思った。
でもやっぱりあの日の昼間、3時間同じフレーズを繰り返してた男の子の姿も忘れられない。彼にとってあのピアノは、きっと大切な「練習場所」だったんだろうな。どっちが正しいとか、そういう単純な話じゃない気がする。
(取材・文 みゆき)
※※関連記事※※
ストリートピアノ文化が長続きするために|角野 隼斗 – かてぃん – note
ストリートピアノのルールを細かく設定するべきか? – Surfvote
ストリートピアノ #演奏マナー #公共スペース #音楽文化 #社会問題
広告
熱狂!夢だった「ピアノのある暮らし」が今、手に届く理由
こんにちは、21歳ルポライターのかずみです。先日、とある楽器店で出会った電子ピアノ「Carina(カリーナ)」に、私、完全に心を奪われてしまいました。
私自身、子どもの頃からピアノに憧れていたのに、「狭い部屋に置けない」「高すぎる」と諦めていた一人。でも、この「LF0088セット」を見て、その常識が覆されました。正直、最初は「またどうせ安っぽい電子ピアノでしょ」と思ったんです。でも触れてみて…これは違った。
弾いた瞬間に驚愕した音の豊かさ
店員さんの勧めで座ってみると、まず木製の質感に驚き。フランス製「DREAM音源」とかいう謎の技術が使われているらしいのですが、私みたいな素人が弾いても、なぜか豊かな音が広がるんです。クラシックを習っていた友人に電話で弾いてみせたら「それ、本当に電子ピアノ?」と疑われるレベル。
特に低音の響きが深くて、ショパンのノクターンを弾いた時(下手くそですが)、私の狭いワンルームがコンサートホールに変わった気分になりました。最大同時発音数128音という数字も意味がわからなかったけど、要は「めっちゃ音が重なっても大丈夫」ということらしい。
「電子ピアノに見えない」がすごい
正直に言います。これまでの電子ピアノって、どれも「私、電子ピアノです!」って主張しすぎじゃないですか?でもこのCarinaは違う。
ウォールナット調の木製ボディを選んだけど、まるで北欧家具のよう。私の安物しか置いてないワンルームが、一気におしゃれカフェに変身!友達が来た時も「これ、インテリアとして買ったの?」と言われました。ブラック、ホワイトなど他の色もあるらしいけど、私はこの落ち着いた木目調が気に入っています。
実は超多機能なのにシンプルで使いやすい
これ、380種類もの音色が入っているらしい。試しにバイオリンやオルガンの音で遊んでみたら、夜中まで止まらなくなりました。しかも、スマホと連携できるBluetooth機能付き!
私はiPhoneのGarageBandと連携させて、勝手に作曲までしちゃいました(センスはないけど)。会社の先輩で「音楽やってる」という人に聞いたら、「それ、10万円以上するヤツじゃない?」と驚かれました。違うんです、もっとリーズナブルなんです。
30代の先輩が羨ましがる理由がわかった
取材で知り合った30代の編集者さんの家にあったのも、実はこのシリーズだったと後で気づきました。彼女曰く「仕事のストレスを解消するために始めた」とのこと。子どもがいる先輩は「子どもと一緒に弾くのが日課になった」と教えてくれました。
私自身、記事締め切り後のリラックスタイムにちょっと弾くだけで、不思議と心が落ち着きます。本当に”音楽という魔法”を日常に取り入れる感覚です。
他の電子ピアノと何が違うのか
正直、素人の私には専門的な違いはわかりません。ただ、明らかに違うのは「全部セット」で届くこと。スタンド、椅子、譜面台、ペダルまで全部揃っているから、届いたその日から弾けます。
しかも重さが10.75kgと軽いので、女性の私でも移動できました(ちょっと大変だけど)。引っ越しが多い私たちの世代には、これは大きなポイントだと思います。
思い切って買って良かった
今、私の小さな部屋の片隅には、このCarina電子ピアノがあります。毎朝、出勤前に5分だけ弾く習慣ができて、なんだか人生が豊かになった気がします。
子どもの頃からの「ピアノのある暮らし」という夢が、こんな形で叶うとは思いませんでした。同じように音楽のある生活に憧れている人に、自信を持っておすすめできます。現在キャンペーンもやっているようなので、気になる方はチェックしてみては?
(個人的には、レビュー特典も狙っちゃいました。だって学生の私には大きい出費だったんですもの!)
|
|









コメント