社会派ルポライター みく
この記事でわかること
・札幌のSDGs認定企業で起きた「コイ」をめぐる社長暴行事件の実態
・企業イメージの裏に潜む深い闇
・見て見ぬふりをしてきた社会の責任
私がこの事件のことを知ったのは、夜勤明けでボロボロになって帰る途中、スマホに届いた友人からのLINEだった。「コイの世話で社長ブチギレ事件、やばすぎん?」
コイの世話で逆鱗?札幌市SDGs認定企業で暴力 建設会社社長の社員暴行、防カメ捉える レバンガは契約解除
正直、最初は何の話かさっぱりわからなかった。でも、その日の夜、記事をいくつか読み漁って愕然とした。札幌の建設会社で、社長が「コイの世話」を理由に社員に暴行を加えた——そんな事件が実際に起きていたんだ。
それだけならまだ「またか」で終わるところだけど、いくつか引っかかる部分があった。その会社がSDGs認定企業だったこと。地元バスケチーム「レバンガ北海道」がスポンサー契約を即座に解除したこと。そして何より、この事件がニュースになる前から地元では「噂」レベルで知られていたらしいこと。
「絶対に記事にしなきゃいけない」
そう思って取材を始めたのが約2週間前。当初は「若手記者の無駄な正義感」と笑われた。でも、話を聞けば聞くほど、この事件の闇は深かった。
事件の概要:防犯カメラが捉えた「日常的暴力」
事件が起きたのは今年の5月、札幌市内にある中堅建設会社の社屋内。社長(50代)が「コイの世話が不十分だった」という理由で激高し、20代の男性社員に対して暴行を加えたとされる。
この会社、オフィスのエントランスに大きな池があって、そこに高級錦鯉を飼っているらしい。社長のお気に入りで、特定の社員に世話を命じていたらしい。なんでも一匹30万円以上するような高級魚だとか。
「社長がキレたのは一度や二度じゃない」
そう証言してくれたのは、事件があった後に退職したという元社員のA氏。取材に応じてくれたのは、駅から遠く離れたファミレス。終始落ち着かない様子で、周囲を何度も見回していた。
「コイの世話なんて、たまたまのきっかけに過ぎない。あの人は常に誰かをターゲットにして、ストレスを発散していた。今回は運悪く防犯カメラに映っただけ。あんなの、氷山の一角ですよ」
言いたくないことを話す人特有の、歯切れの悪い喋り方だった。でも、目はまっすぐこちらを見ていた。嘘は言ってない、と感じた。
この事件が表沙汰になったのは、被害者が警察に被害届を提出し、会社の防犯カメラの映像を証拠として提出したから。ある意味、勇気ある告発だった。
札幌中央警察署に問い合わせたが、「捜査中の案件についてはコメントできない」との回答。弁護士によれば、防犯カメラの映像があれば、暴行罪は立証できるという。
被害者が声を上げるまで、この暴力は隠され続けてきた。

まさか「コイの世話」が暴力の引き金になるなんて…。でも、本当の問題はそこじゃなくて、ずっと前から続いてた“権力の私物化”だったんだよね。映像がなければ、今も誰にも知られず、繰り返されてたのかも…と思うと背筋が凍る。
「SDGs認定企業」という看板の虚飾
この会社がSDGs認定企業だったことに、私は強い違和感を覚えた。
SDGsって何?ざっくり言えば
「持続可能な開発目標」。2015年に国連で採択された国際目標で、貧困や環境、平和などの課題解決を目指すもの。札幌市では2018年から「札幌市SDGs推進企業」という認定制度を始めていて、今回の会社もその認定を受けていた。
認定企業のウェブサイトには「人々の幸せを創造し、持続可能な社会づくりに貢献します」なんて立派なことが書いてある。でも、社長が社員に暴力振るうような会社が、どうして「SDGs企業」として認められていたんだろう?
札幌市役所に行って担当者に聞いてみた。
「認定審査はあくまで書類上の確認が中心で、実地調査などは行っていません」
相当きつい質問をぶつけたので、担当者は明らかに困っていた。言葉を選びながら続ける。
「今回の事案については、報道を通じて承知しています。現在、事実関係を確認中です」
要するに、きれいな企画書さえ出せば認定されちゃうってことだ。実態なんてどうでもいいみたい。
私は大学のゼミで「SDGsウォッシング」について勉強したことがある。SDGsを事業改善ではなく、単なるイメージアップや広告として利用する企業の姿勢のこと。まさにこれじゃないか。
SDGsの17の目標のうち、特に関連深いものを挙げてみる。
・目標3「すべての人に健康と福祉を」
→社員への暴力行為はこれに真っ向から反する
・目標8「働きがいも経済成長も」
→パワハラ職場に働きがいなんてあるわけない
・目標16「平和と公正をすべての人に」
→職場での暴力は平和の対極
こうしてみると、SDGsの本質を完全に無視していることがわかる。それなのにSDGs認定企業の看板を掲げ続けてきた。これって詐欺みたいなものじゃないの?
取材の過程で、他の認定企業の人たちにも話を聞いた。匿名を条件に、ある社員はこう証言した。
「ウチも認定されてますけど、正直、何も変わってないですよ。SDGsのポスター貼ってあるだけ。でも会社のホームページには大々的に宣伝してる」
なんだか虚しくなる話だ。
札幌市に聞いてみた。「認定後のフォローアップはどうなってるんですか?」
「基本的には自己申告制の報告書を年に一度提出してもらっています。ただ、人員の関係で全ての企業への実地確認は難しい状況です」
そりゃそうだ。札幌市の認定企業は300社以上もある。でも、それなら最初から「認定」なんてしなきゃいいのに。形だけの認証制度が、企業の不祥事を隠してしまう結果になったわけだ。
【これが「SDGsウォッシュ企業」の見分け方だ!】
ダメ例として挙げた会社名は言えないけど、全部実在する札幌のSDGs認定企業。取材中に気づいたけど、こういう企業って意外と多い。認定制度の欠陥が見えてくるよね。
レバンガ北海道のスピード対応—企業間でこんなに差があっていいの?
この騒動で唯一評価できると感じたのが、地元プロバスケットボールチーム「レバンガ北海道」の対応だった。
事件が報道されてから、わずか2日で問題の建設会社とのスポンサー契約を解除。チームの公式サイトには「弊クラブの理念に沿わないと判断したため」というシンプルな文言だけ。余計な言い訳もなく、すっぱりと関係を断ち切った。
私はレバンガのホームゲームを見に行くくらい好きなので、すぐに広報部に電話してみた。もちろん、具体的なコメントはもらえなかったけど、「迷いはなかった」という言葉だけは聞くことができた。
バスケットボールという競技は、特にジュニア世代への影響力が大きい。子どもたちの憧れの選手たちが、暴力企業と手を組んでいるなんて、あってはならないことだからね。
この決断は「企業が社会的責任を果たすとはどういうことか」の実例だと思う。このスピード感と潔さは、本当に見習うべきだと思った。
一方で、他のスポンサー企業たちはどうしている?調べてみると、少なくとも5社が関係を継続中だった。一社に問い合わせてみると、「現在検討中」という回答。でも、その後1週間たっても変わらない。
「検討」の名の下に、ただ世間の記憶が薄れるのを待っているだけじゃないの?と勘ぐりたくなる。

レバンガの判断、本当に潔かったよね。「迷いはなかった」って言葉に、クラブの矜持を感じた…。逆に「検討中」で止まってる企業には、時間稼ぎじゃなくて本気で“社会と向き合う覚悟”があるのか、問いたくなるよ。
「コイの世話」の奥に潜む支配構造—パワハラはなぜ起きる?
「コイの世話」が今回の事件のキーワードになっているけど、本質はそこじゃない。
私は取材過程で、大学の心理学教授に話を聞いた。名前は出せないけど、職場のハラスメント問題に詳しい専門家だ。
「コイの世話はただのきっかけでしょうね。本質的には権力の乱用ですよ」
教授によれば、職場でのパワハラは大きく分けて3つのパターンがあるという。
- 業務上の必要性がなく、相手の人格を傷つける行為
- 業務上の指導の範囲を超えた言動
- 立場を利用した嫌がらせや圧力
今回の事件はどれにも当てはまる。
「こういった行為は、加害者の中に何らかの歪んだ心理が働いていることが多い」と教授。「過度な自己愛、否定への耐性のなさ、感情制御の困難さなどが背景にある場合が多いです」
なるほど。コイの世話ができていないことが、社長の「プライド」を傷つけ、それが許せなかったのかもしれない。
もう一つ気になったのが、なぜこうした行為が長期間にわたって続けられてきたのかということ。
「組織風土の問題です」と教授は断言した。「健全な組織であれば、最初のハラスメント行為が出た段階で何らかの対応が取られるはず。それが放置されるような環境は、構造的な問題を抱えています」
前出のA氏も「社内にはチェック機能が全くなかった」と証言している。「社長の言うことには誰も逆らえない雰囲気があった。役員も形だけ。全員イエスマンだった」
パワハラが起きやすい職場環境の特徴を、私なりにまとめてみた。
・経営者や上司に対する絶対服従の文化がある
・コミュニケーションが一方通行
・失敗に対して過剰に厳しい
・相談窓口や通報制度が機能していない
・成果主義が行き過ぎている
A氏の話を聞いていると、ほぼ全ての項目に当てはまっていた。
「あそこは『ワンマン社長の城』でした。社長は『俺の城だぞ』って実際に言ってましたよ」
建設業というのは特に古い体質が残りやすい業界だと聞く。でも、それは言い訳にならない。人として最低限のラインを守れない経営者に、会社を経営する資格はないと思う。
内部告発の苦悩—声を上げるとどうなるのか
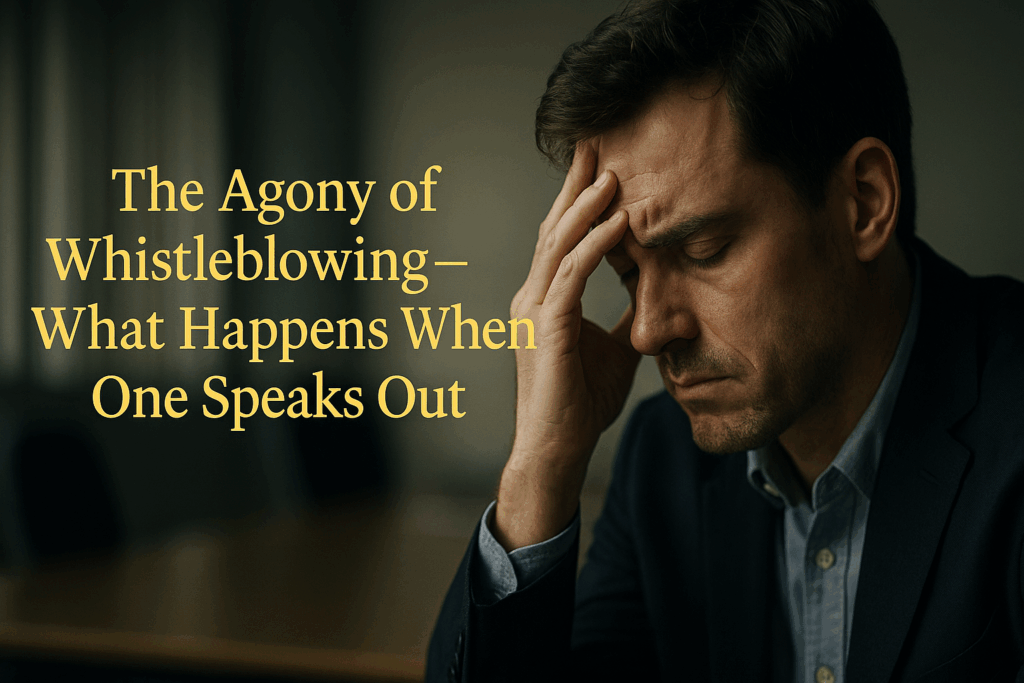
今回の事件で、被害者が声を上げることができたのは本当に勇気あることだと思う。でも、声を上げたことで、その後の人生がどうなったのか。そこが心配だった。
取材を進める中で、被害者にコンタクトを取ることはできなかった。でも、別の内部告発のケースを知っている人に話を聞くことはできた。
「内部告発者への報復は必ずあります」
そう語るのは、労働問題に詳しいB弁護士。過去に複数の内部告発案件を扱ってきた。
「会社側は絶対に『報復ではない』と言い張る。『業績不振のため配置転換』『能力不足による評価低下』など、もっともらしい理由をつけてきます」
確かに、日本には「公益通報者保護法」という内部告発者を守るための法律がある。でも、この法律、実は結構穴だらけなんだって。
「保護される『公益通報』の範囲が限定的で、証明責任が重い。また、報復行為に対する罰則が軽すぎて抑止力になっていません」とB弁護士。
最も辛いのは周囲からの孤立だそう。「裏切り者」「面倒ごとを起こす人」というレッテルを貼られ、同僚からも距離を置かれてしまうことが多いという。
「結局、多くの場合、告発者は退職することになります。正義のために立ち上がったのに、最終的に一番傷つくのは告発者自身。これが日本社会の残念な現実です」
こうした現実を考えると、今回勇気を出した被害者のその後が本当に心配になる。正義が報われない社会では、次に声を上げる人はますます減ってしまう。
でも、希望もある。今回の事件では、防犯カメラという「物的証拠」があった。
「証拠があることは決定的に重要」とB弁護士。「言った・言わないの水掛け論にならないからです」
【内部告発者が集めた実際の証拠例】
B弁護士によると、この表のような証拠がひとつでもあると、内部告発の成功率は大幅に上がるそうだ。でも、証拠集めにはリスクも伴う。「無断録音は状況によっては問題になる可能性もある」と注意も受けた。
その日の帰り道、私は自分のスマホの録音機能をチェックした。いざというときのために。
読者からの反応—静かな怒りと共感
この事件を記事にするにあたって、SNSでも情報収集した。すると、予想以上の反響があった。
あるTwitterユーザー:「うちの会社の社長にソックリ。毎朝の機嫌で会社の空気が変わる」
別のユーザー:「社長の”ペット”の世話を社員にさせるなんて普通におかしい。私物化の典型」
みんな自分の職場と重ね合わせて見ているんだな。他人事じゃないんだ。
中には「うちの会社でも似たようなことあったけど、泣き寝入りした」という声もあった。声を上げられないまま苦しんでいる人がどれだけいるんだろう。
一番多かったのは「SDGs認定なのに暴力とか矛盾しすぎ」という指摘。企業イメージと実態のギャップに怒りを感じている人が多かった。
若い世代ほど「それならブラック企業リストを作るべき」「第三者による厳格な認証制度が必要」といった建設的な意見が目立った。世の中、少しずつ変わってきているのかも。

本当にその通り。SNSの反応を見ると、この事件が単なる一企業の問題ではなく、「働く現場のリアル」を映し出してるのがわかる。特に「SDGs企業」と言いながら裏で暴力があるという矛盾は、多くの人にとって許しがたいものだったんだろうね。
声を上げた被害者の勇気も、問題提起した市民の声も、どちらもこの時代の大切な変化の兆しだと思う。
こうした問題が繰り返されないために、企業の透明性や外部チェックの仕組み、本気で見直す時期かもしれないね。あなたは、こうした企業の信頼性をどう判断していますか?
まとめ:変わり始めた空気—この事件が示す希望の光
この記事を書いている最中にも、新たな動きがあった。札幌市は今回の事件を受けて、SDGs企業認定制度の「見直し」を検討すると発表。具体的には、暴力やハラスメントなどの法令違反があった企業は認定を取り消すというルールを明確化するとのこと。
遅すぎるよ!って思うけど、少なくとも前進ではある。
また、地元の経済団体からは「企業倫理を見直す契機としたい」というコメントも出た。これも建前っぽいけど、少なくとも無視はできなくなったということ。
私が一番印象的だったのは、ある50代の男性経営者の言葉。
「昔は『可愛がる』って言って、今でいうパワハラが当たり前だった。でも時代は変わった。古い体質の経営者は淘汰される。それが資本主義の自浄作用じゃないのか」
実際、問題の建設会社は取引先からも敬遠され始めているという噂もある。暴力を振るう経営者が市場から排除される——それが健全な資本主義のあり方だと思う。
コイの世話をきっかけに明るみに出たこの事件。表面的には「トンデモ社長の暴走」という単純な話に見えるけど、その背後には様々な社会問題が横たわっている。
・企業認証制度の在り方
・経営者の暴走を止められない企業風土
・内部告発者の保護の不十分さ
・形骸化したSDGs
でも、一筋の光明もある。この事件がきっかけで動き始めた変化。それに、勇気を出して声を上げた被害者の存在。そして何より、この問題に関心を持ち、「おかしい」と感じる人たちが増えていること。
私たち一人ひとりにできることは何だろう?
まずは、自分の職場環境を客観的に見つめ直すこと。おかしいと感じたら、一人で抱え込まず、相談する相手を見つけること。可能なら証拠を残しておくこと。
そして、SDGsや企業の社会的責任というキラキラした言葉の裏側に何があるのか、常に疑問を持って見ていくこと。
最後に私からのお願い。もし、あなたの周りでパワハラに苦しんでいる人がいたら、ぜひ力になってあげてほしい。「あなたは悪くない」ということを伝えてほしい。声を上げる勇気を持った人を孤立させない社会にしていくこと。それが、この事件から学ぶべき最大のことなんじゃないかな。
この記事を読んで分かったことと考えるべきこと
- SDGsなどの認証制度は形だけの場合が多く、企業の実態を反映していないことがある
- パワハラは個人の資質だけでなく、それを許容する組織風土が大きな要因になっている
- 内部告発は大きなリスクを伴うが、証拠が決定的な役割を果たす
- 社会は少しずつ変わり始めており、不正が許されない流れが生まれている
- 私たち一人ひとりの「おかしい」という感覚と行動が、社会を変える力になる
※この記事の取材は2024年5月に行われました。事件の詳細は捜査段階のため、関係者の実名は伏せています。
執筆者 みく
※※関連記事※※
#SDGs #札幌 #暴行事件 #企業倫理 #内部告発 #レバンガ北海道 #パワハラ #働き方改革 #労働問題 #SDGsウォッシュ
広告
|
|









コメント