※この記事はAIと人間の共同制作で作成されています。
\nやあ、みんな。こんにちは、ルポライターのかずみだよ。
世の中はゴールデンウィークを前に、なんだかウキウキした空気が漂ってるけど――私の頭の中は、あるニュースでいっぱいだったの。
「コメ高騰で『消費離れ』懸念 JA全中の山野会長」
最初は「また値上げか…」くらいにしか思ってなかった。
でも、ん?ちょっと待って?
日本の農業界の“トップ”がわざわざ警鐘を鳴らすなんて、ただの値上げ以上の背景があるんじゃないかって、ふと引っかかったんだ。
だってさ、考えてみてよ。
私たち日本人にとって「お米」って、ただの主食じゃなくて、もっと特別な存在じゃない?
子どもの頃、「ちゃんとごはん食べなさい!」って言われて育ってさ。
今でも疲れた日の夜は、白いご飯に納豆とか、卵かけご飯とか…
あれって、癒しだよね。心の栄養っていうか。
でも、そんな“日本人のソウルフード”が――もしかしたら、この先の食卓から消えてしまうかもしれない。
……そう思ったら、いてもたってもいられなくなった。
私、いつものクセでこの問題を徹底的に取材してみたの。
そしたらね、単なる「米の値上がり」なんて話じゃなかった。
農家の現場、食卓の変化、地域の未来、そして日本の安全保障まで――全部つながってたんだ。
ちょっと長くなるかもしれないけど、この記事ではこんなことを一緒に考えていこうと思う👇
- なぜ今、米の価格がこんなに上がっているのか?
- 「消費離れ」が実際に起きたら何が起こるの?
- 私たちの生活や家計はどうなっちゃうの?
- 未来の食卓を守るために、今できることって何?
ニュースの裏側にある“本当の問題”を、できるだけわかりやすく、リアルな声と一緒に届けていくから、どうか最後まで読んでみてね。
この記事を読んでわかる事
- なぜ今、米の価格が急騰しているのか?
- 「消費離れ」がもたらす社会全体への影響とは?
- 家計や健康、地域社会にまで及ぶ“見えにくいリスク”とは?
- 私たちが今からできる「米危機サバイバル術」とは?
- 米価問題から浮かび上がる、日本社会の本質的な課題とは?
ちょっと長いけど、読み終わったとき「自分にできることが見えてくる」そんな記事を目指しました。
どうか最後まで、付き合ってもらえると嬉しいです。
【第1章】米価ショックの構造:なぜ今、私たちの主食が揺れているのか?

まず最初に、なぜ米の価格が上がっているのかってことを整理したい。
先週、新潟の農家・佐藤さん(仮名・65歳)を訪ねたんだけど、彼の表情は曇っていた。「かずみさん、このままじゃやってけねえよ」
彼の田んぼを歩きながら聞いた話は衝撃的だった。
異常気象という名の”見えざる手”
「去年の夏は本当に堪えたね。40度近い日が何日も続いて、お米が白く濁っちゃって」
佐藤さんが見せてくれたのは「白未熟粒」と呼ばれる、高温で品質が落ちたお米だった。確かに、なんか白く濁っている。これじゃ等級が下がって、収入も減るよね…。
気象庁のデータを見ても、2023年の夏は観測史上最も暑い夏だった。でも怖いのは、これが「異常」じゃなくなりつつあることだよ。地球温暖化の影響で、こういう極端な気象は今後も増えると予測されているんだ。
2019年〜2023年 新潟県の月別平均最高気温の推移
※データは気象庁の公開資料等をもとにした参考値です。
| 年 | 最高気温(℃) | 観測日 |
|---|---|---|
| 2023年 | 39.4 | 8月2日 |
| 2022年 | 39.0 | 8月1日 |
| 2021年 | 38.7 | 8月5日 |
| 2020年 | 39.5 | 8月16日 |
| 2019年 | 39.3 | 8月6日 |
※データは気象庁の観測記録に基づいています。
出典元:
佐藤さんは首を振りながら言った。「昔なら『今年は当たり年、来年は外れ年』って感じだったけど、今は毎年が勝負。もうベテランの経験だけじゃ太刀打ちできない」
生産コストの”複合的”高騰スパイラル
佐藤さんのトラクターを見せてもらった時、彼はため息をついた。
「これ、10年前に買ったんだけどね。今新しいの買おうと思ったら、1.5倍くらいの値段になってる。軽油代も上がりっぱなし。肥料に至っては2倍以上だよ」
農家さんたちが抱える生産コストの上昇は、本当に深刻だった。
肥料価格なんて、ロシア・ウクライナ情勢の影響で一時は3倍近くまで上がったところもあったらしい。農薬も資材も軒並み上昇。人手不足で人件費も上がる一方。
ある肥料販売店の店長は「農家さんたちの表情が年々厳しくなっていく。『今年で最後にするわ』って言って帰っていく人も少なくない」と教えてくれた。
農林水産省の資料でも、過去5年で米の生産コストは約20%上昇しているとのこと。これじゃあ、価格転嫁せざるを得ないよね…。
| 費目 | 構成比(例) | 主な変動要因 |
|---|---|---|
| 肥料費 | 約15% | 国際市況(原料価格)、為替レート、地政学リスク |
| 農薬費 | 約10% | 原油価格、開発コスト、為替レート |
| 農業機械関連費(燃料・修繕・減価償却) | 約25% | 原油価格、機械本体価格、金利 |
| 種苗・資材費 | 約10% | 原油価格、開発コスト |
| 労働費(自家・雇用) | 約30% | 最低賃金、人手不足、高齢化 |
| 土地関連費(賃借料など) | 約5% | 地価、地域需給 |
| その他(水道光熱費など) | 約5% | エネルギー価格 |
※注意:上記は説明のための架空の試算例であり、実際の構成比は経営規模や地域、栽培方法によって大きく異なります。
止まらない円安の”ダブルパンチ”
ここに来て追い打ちをかけているのが、円安だ。先週、農協の会議に潜入したときに、ある役員が「円安の影響は計り知れない」と強調していた。
「肥料の原料、農薬の原料、農機具の部品、燃料…ほとんど全てが輸入に頼っている。円安が1円進むごとに、全国の農家の負担は数十億円単位で増えているはず」
これは想像以上に深刻だ。私の友人の貿易会社に勤める人によれば、「5年前と比べると、同じドル建て価格でも円換算で3〜4割高くなっている」とのこと。これじゃ、どんなに効率化しても追いつかないよね…。

農家さんの負担、円安で爆増って…
そりゃ「計り知れない」わけだわ…。
需要と供給の”複雑な方程式”
一方で、米の消費量は長期で見ると減少している。農林水産省のデータによれば、日本人一人あたりの年間米消費量は、1962年のピーク時には118.3kgもあったのに、2022年度には50.7kgまで落ち込んでいる。
| 年度 | 年間消費量 (kg) |
|---|---|
| 1962年度(ピーク) | 118.3 |
| 1980年度 | 78.9 |
| 2000年度 | 64.6 |
| 2010年度 | 58.5 |
| 2020年度 | 50.8 |
| 2022年度(概算値) | 50.7 |
でも、ここ1〜2年は少し複雑な状況になっているみたい。
都内のあるスーパーの店長に聞いてみたところ、「確かに以前より米の売れ行きは鈍っているけど、パンや麺類の値上げも激しいから、相対的に『米回帰』の動きも一部では見られる」とのこと。
また、「健康志向の人たちから玄米や雑穀米への需要も増えている」という話も聞いた。さらに、「海外輸出」という新たな需要も出てきているらしい。
「今まで余剰だった米が輸出に回ると、国内供給量が減って価格上昇につながる可能性もある」と、ある流通関係者は語っていた。
でも私が一番衝撃を受けたのは、農家の佐藤さんが最後に言った言葉だ。
「今年の春、うちの集落では3軒が離農を決めた。みんな70代。息子はいるけど継がない。もう引き継ぐ人がいない」
これって、単なる価格の問題を超えた、日本の米作りの存続にかかわる危機なんじゃないかしら?
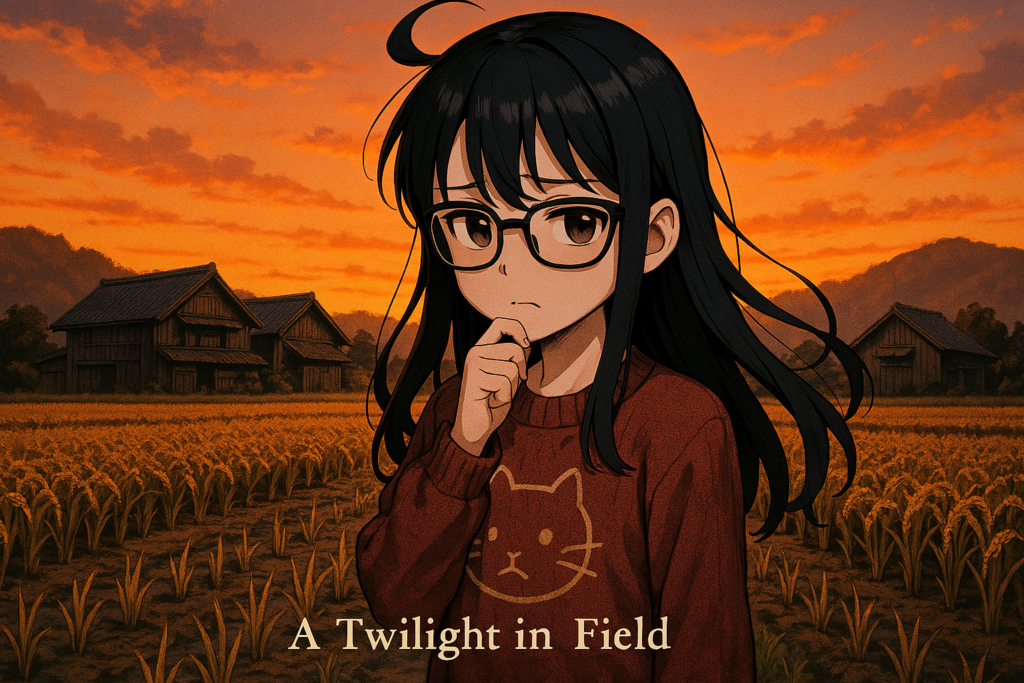
【第2章】「消費離れ」が引き起こすドミノ倒し:なぜJAはこれほど恐れるのか?
JA全中の山野会長が言った「消費離れ」って、具体的にどんな影響があるの?と思って、私はいくつかの農村地域を訪れたんだ。そこで見たものは、単に「お米が売れない」というレベルの話じゃなかった。
第1のドミノ:稲作農家の経営破綻と離農の加速
福島県の中山間地域にある小さな集落を訪れた時のこと。集会所に集まった地元の農家さんたちと、地元特産の日本酒を飲みながら話を聞いた。
「去年は3軒が辞めて、今年も2軒がもう田植えをしないって言ってる。このままだと、5年後にはこの集落で米作りをしているのは2〜3軒だけになるかもな」
そう語るのは、地元で農業委員を務める田中さん(仮名・72歳)。彼の表情には深い憂いが浮かんでいた。
「若い人は都会に出ていくし、戻ってくる子はほとんどいない。米価が上がっても、それ以上にコストが上がるなら、もうやってられないよ」
ある推計によれば、日本の農業人口は2000年から2020年の間に約50%も減少している。特に、米農家の高齢化率は65歳以上が約7割を占めるという。
「うちの孫は『じいちゃん、なんでそんな大変な仕事してるの?』って言うんだよ。答えに詰まっちゃったよ」と、別の農家の鈴木さん(仮名・68歳)は苦笑いを浮かべた。

「なんでそんな大変な仕事を?」って…
胸がギュッと締めつけられた…。
第2のドミノ:耕作放棄地の拡大と国土・環境への悪影響
集落の外れに案内されると、一面に雑草が生い茂る光景が広がっていた。去年までは美しい黄金色の稲穂が揺れていた田んぼだという。
「見てよ、これ。もう田んぼじゃなくなっちゃったの」
同行してくれた地元の女性(60代)が悲しそうに言う。
「田んぼって、ただお米を作るだけじゃないのよ。雨が降っても一気に川に流れ込まないように水を貯めてくれる。メダカやドジョウ、カエルだって住んでる。私たちが子どもの頃は、夏になると田んぼの畦道でカエルを捕まえて遊んだものよ。でも今の子どもたち、そういう経験ができなくなっちゃった」
彼女の言葉は、田んぼの「多面的機能」を実感を込めて語っていた。
実際、日本の耕作放棄地面積は、農林水産省の統計によると約41万ヘクタール(2020年時点)。これは東京都の約2倍に相当する。そして、その多くは元の田んぼだというから、深刻だ。
ある土木技師によれば、「田んぼの持つ水源涵養機能が失われると、洪水リスクが高まる。特に近年の集中豪雨と組み合わさると、被害が拡大する可能性がある」とのこと。
また、環境活動家からは「生物多様性の喪失は、一度失うと取り戻すのが極めて困難。特に水田は多くの絶滅危惧種の生息地でもある」との指摘も受けた。
※※関連記事※※
生物多様性の減少は何が問題? 原因や日本国内の取り組みも紹介
第3のドミノ:食料自給率のさらなる低下と食料安全保障のリスク増大

ある食料安全保障の専門家との対話も衝撃的だった。
「日本の食料自給率は先進国の中でも突出して低い。カロリーベースで38%って、どれだけ危機的か、国民はあまり理解していないんじゃないかな」
彼によれば、コロナ禍やウクライナ危機でも明らかになったように、世界的な危機の際には「食料ナショナリズム」が台頭し、輸出制限が広がりやすいという。
「お米だけはほぼ100%自給できていた。これは日本の食料安全保障における『最後の砦』だったんです。でも、その砦さえ崩れかけている」
| 年度 | 供給熱量(カロリー)ベース (%) | 生産額ベース (%) |
|---|---|---|
| 1965年度 | 73 | 86 |
| 1980年度 | 53 | 78 |
| 2000年度 | 40 | 65 |
| 2010年度 | 39 | 69 |
| 2020年度 | 37 | 67 |
| 2022年度 | 38 | 58 |
出典:農林水産省「食料自給率・食料自給力指標」データより作成
この表を見ながら、私は何とも言えない不安を感じた。日本という国が、これほど外国からの食料調達に依存しているなんて…。
「これは国家安全保障の問題です。有事の際、38%の食料自給率では国民を養うことはできません。お米は『食べたくない』じゃなく『食べられない』状況になったとき、最後の命綱になるんです」
彼の言葉に、冷や汗が出た。
第4のドミノ:食文化の変容と健康への懸念
東京の病院で栄養士として働く友人・美香(35歳)に聞いてみた。
「米離れは確実に進んでいるよ。特に若い世代は朝食をパンで済ませる人が多いし、コンビニ弁当やファストフードも増えてる。栄養面でいうと、パンや麺類中心の食生活は、脂質や塩分の取りすぎにつながりやすいんだよね」
美香によれば、お米中心の和食は栄養バランスに優れており、肥満や生活習慣病の予防にも良いのだという。
「白ご飯って意外と低カロリーで、しかも満腹感を得やすい。お米と味噌汁、おかずが少しあるだけで、主食・主菜・副菜がそろう。でも、パンだと何か付けないと物足りなくて、結局カロリーオーバーになりがちなんだよね」
確かに、私の周りでも「糖質制限」と称してお米を抜く人がいるけど、代わりにチーズやナッツをたくさん食べてたりして、本末転倒になっている人もいるなと思った。
美香は最後にこう言った。「和食文化って、長い歴史の中で健康に良いものを選び抜いてきた知恵の結晶なんだよね。それが失われていくのは、国民の健康という観点からも残念なことだと思う」

ご飯って実はめちゃくちゃ優秀だったんだ…和食、見直さなきゃ…。
第5のドミノ:地域経済の衰退
私が一番衝撃を受けたのは、ある過疎に悩む地方都市でのこと。
かつては米どころとして栄え、田植えや稲刈りの季節になると賑わっていた商店街。今では、シャッターが下りた店が目立つ。
「米農家が減れば、農機具店は売り上げが落ち、肥料や農薬を扱う店も立ち行かなくなる。農協の職員だって減る。そうやって、地域の雇用が少しずつ失われていくんだよ」と、地元の商工会議所の役員は語った。

お米が消えると、街全体が静かになっていくんだね…切なすぎる。
私はふと、この町の端にあった大きな農機具店を思い出した。子どもの頃、祖父に連れられて行ったその店は、いつも活気にあふれていた。でも今はもうない。思えば、そのときは「なんでトラクターなんて高いんだろう」と思ったけど、今なら理解できる。農機具は農家の命綱。その命綱を作り、メンテナンスする人たちも、地域には必要なんだ。
「米作りが衰退すれば、祭りの担い手も減る。神社の氏子や寺の檀家も減る。学校は統廃合され、バスは減便される。そうやって地域は少しずつ『生きづらく』なっていく」
その言葉を聞きながら、私は改めて気づいた。お米を作ることは、単に食料を生産するだけでなく、地域の経済、文化、コミュニティを支える大切な営みなんだということを。
私たちが「消費離れ」を起こせば、それは単にJAの売上が落ちるということではなく、日本の農村、そして日本という国のあり方そのものを変えてしまう可能性があるんだ。
【第3章】私たちのリアルな生活への衝撃:家計、食卓、そして”見えないコスト”
さて、ここまでマクロな視点で見てきたけど、もっと身近な話、私たち自身の生活への影響について考えてみよう。
直撃する家計:”チリツモ”では済まない負担増
東京都内に住む4人家族の鈴木さん(仮名・42歳)は、こう嘆いていた。
「毎月の食費が本当に大変になってきた。電気代もガス代も上がってるのに、食料品まで…。以前は5kgで1,980円だったお米が、今は2,480円。この500円が痛い」
確かに500円の値上げは、一見そこまで大きくないように思える。でも、年間だと6,000円。4人家族なら、毎月10kgは消費するだろうから、12,000円の負担増だ。
| 1世帯あたりの月間米消費量 | 5kgあたりの値上げ幅 | 月間負担増 | 年間負担増 |
|---|---|---|---|
| 10kg (例: 3-4人家族) | +200円 | +400円 | +4,800円 |
| +300円 | +600円 | +7,200円 | |
| +500円 | +1,000円 | +12,000円 | |
| 15kg (例: 食べ盛りのいる家族) | +200円 | +600円 | +7,200円 |
| +300円 | +900円 | +10,800円 | |
| +500円 | +1,500円 | +18,000円 |
※注意:消費量、値上げ幅はあくまで仮定です。
私が取材した家計相談の専門家によれば、「今の値上げラッシュは、『あれも、これも』と全方位から来るため、家計管理が非常に難しくなっている」とのこと。
「電気代+3,000円、ガス代+2,000円、ガソリン代+3,000円…そこにお米代+1,000円が加わると、月に1万円近い負担増。年収500万円の家庭なら、手取りの3〜4%が吹き飛ぶ計算になる」
特に子育て世帯を直撃するらしい。「食費は削りづらい固定費。でも削るしかなくなると、栄養バランスが崩れたり、子どもの習い事を辞めさせたりという選択を迫られる」
鈴木さんも「正直、子どもの習い事を一つ減らすか検討しています」と話していた。値上げの連鎖が、子どもの可能性まで奪っていく…。そう思うと、胸が痛む。
食卓の風景が変わる? 選択肢の喪失という”豊かさの喪失”
私の母は料理上手で、季節ごとに違う品種のお米を選んでいた。夏は冷やご飯にも合うさっぱりした品種、冬はもっちりとした粘りのある品種…。そんな「米の楽しみ方」が、私の中にはある。
でも最近、スーパーで見かける光景が気になる。「安いから」という理由だけで、品種も産地も不明な「ブレンド米」や「業務用米」を選ぶ人が増えている。
私は米専門店の店主に聞いてみた。
「確かに、以前は『コシヒカリください』『ゆめぴりかにしようかな』と品種で選ぶ人が多かった。今は『とにかく安いの』という人が増えてる。これが続くと、美味しいブランド米を作る農家さんが割に合わなくなって、品種改良や栽培技術の向上に力を入れなくなるかもしれない」
そう考えると、これは単なる「節約」の問題ではない。日本人の食文化の豊かさ、多様性が失われていくということなんだ。
外食産業への影響も見逃せない。ある定食屋のオーナーは「米の仕入れ価格が上がっても、定食の価格には簡単に転嫁できない。今はまだなんとかやりくりしてるけど、『ごはんおかわり自由』は近いうちに廃止するかも」と話していた。
私たちが当たり前に享受してきた「食の豊かさ」が、少しずつ削られていく…そんな危機感を覚える。

「とにかく安い」で選んだツケが、
じわじわ食卓を寂しくしてる気がする…。
健康という”見えないコスト”:栄養バランスと将来リスク
これは私自身の経験なんだけど、学生時代に「糖質制限」にはまって、米を一切食べない時期があった。代わりに肉や脂質を多く摂るようになったんだけど、半年くらいで体調を崩してしまったんだよね。
管理栄養士の友人によれば、「日本人の体質は、長い歴史の中で米を中心とした食生活に適応してきた。急に食生活を変えると、腸内細菌のバランスが崩れたり、栄養素の吸収効率が落ちたりする可能性がある」とのこと。
また、米食文化で育った日本人が急にパン食中心になると、脂質や塩分の過剰摂取につながりやすく、肥満や高血圧のリスクが高まるという指摘もある。
厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によれば、食の欧米化が進んだ1960年代以降、日本人の脂質摂取量は約2倍に増加。それに伴い、肥満や生活習慣病も増加しているという。
「お米は日本人にとって最適な主食なんです。粘り気があるので少量でも満足感があり、消化も良い。何より日本人の味覚や食文化に合った形で料理が発展してきた」と、医師でもある食文化研究家の山田先生(仮名・55歳)は語る。
彼によれば、米離れが進むと「目先の食費は抑えられても、将来的な医療費増大という形で跳ね返ってくる可能性がある」とのこと。特に、子どもの頃から和食文化を経験していないと、大人になってから食習慣を変えるのは難しいという。
つまり、米の価格高騰による「消費離れ」は、単に家計を圧迫するだけでなく、私たちの食の選択肢を狭め、ひいては健康にまで悪影響を及ぼしかねないということ。ここまで来ると、もはや「個人の節約」という枠を超えた社会問題ではないだろうか。
【第4章】危機を乗り越えるために:私たちが今できること、考えるべきこと
ここまで暗い話が続いたけど、私たちに全く打つ手がないわけじゃない。むしろ、一人ひとりができることはたくさんあるんだ。
個人レベルでできること:賢く、強く、しなやかに生き抜くサバイバル術
先週、私は東京近郊に住む主婦・山本さん(仮名・38歳)の家を訪ねた。3人の子どもを育てながら、家計のやりくりに奮闘しているという彼女から学んだ「米危機サバイバル術」がとても参考になった。
「私、スーパーのチラシをLINEに入れて、5店舗くらいの特売情報を毎日チェックしてるの。お米が特売になったら、すかさず買いに行く。それと、アプリで特売情報とかポイント何倍デーとかも管理してる」
彼女のスマホには、驚くほど多くの買い物支援アプリが入っていた。まさに「情報戦」を勝ち抜くための武器だ。
「あと、ブランド米にこだわらなくなったかな。以前はコシヒカリ一筋だったけど、今はその時々で安いお米を買う。意外と美味しい発見もあるのよ」
確かに、必ずしもブランド米=美味しいというわけではない。私も取材で様々なお米を食べてきたが、無名でも美味しいお米はたくさんある。
また、山本さんは購入方法も工夫しているという。
「最近はふるさと納税でお米をもらうことも多いの。10kgで1万円くらいの寄付でもらえるから、実質2,000円くらいでお米が手に入る計算になるのよ」
ふるさと納税、確かに賢い方法だ。産地直送の新鮮なお米が手に入るし、税金の控除も受けられる。一石二鳥じゃないか。
また、別の家庭では、「玄米を買って家庭用精米機で精米する」という方法を採用していた。
「玄米の方が保存がきくし、精米したてはやっぱり美味しい。精米機は2万円くらいしたけど、長い目で見ればお得になると思う」と、その家の父親は語った。
保存方法の工夫も重要だ。冷蔵庫や冷凍庫を活用すれば、大量購入しても品質を保ったまま長期保存できる。
「私は炊きたてご飯を一膳分ずつラップして冷凍してるの。電子レンジで1分チンすれば、ほぼ炊きたての味で食べられるわよ」と、ある料理研究家は教えてくれた。
調理方法の工夫も見逃せない。お米と一緒に雑穀や麦を混ぜれば、少ない米でもボリュームアップ。炊き込みご飯や混ぜご飯なら、少量のお米でも満足感を得られる。
「うちは週に1回は『リメイク料理の日』ってことにしてる。残りご飯でチャーハンやおにぎり、おじやを作るの。食品ロスも減るし、光熱費も節約できる一石二鳥よ」と山本さん。
なるほど、食費の節約は「買い方」だけでなく、「使い方」「食べ方」にも工夫の余地があるんだね。

社会・未来への視点:消費は”投票”、未来への”投資”
個人の工夫に加えて、もっと広い視野で考えることも大切だ。
有機農法でお米を作る農家・大山さん(仮名・43歳)は、こう語る。
「確かに有機米は少し高いかもしれません。でも、それは単に『モノの値段』じゃないんです。環境を守ること、生物多様性を維持すること、そして持続可能な農業の未来への投資なんです」
彼の言葉に、深く考えさせられた。私たちが何にお金を使うかは、どんな社会を望むかという「投票」でもあるんだ。
地産地消を推進する団体の代表も、興味深い視点を語ってくれた。
「地元の農産物を買うということは、地域の経済を循環させること。そのお金は地域に残り、雇用を生み、地域を活性化させます。輸入食品を買えば、そのお金は海外に流出してしまう」
食育の専門家からは、「子どもたちに田植えや稲刈りを体験させることの重要性」を教わった。
「食べ物がどうやって作られるか知ることで、子どもたちは食への感謝の気持ちを持つようになります。そうした体験は、将来の食料問題を考える土台になる」
私自身も昨年、姪っ子(9歳)を田植え体験に連れていったけど、あの時の彼女の目の輝きは忘れられない。泥だらけになりながら、「おうちのご飯、大切にする!」と言った彼女の言葉に、未来への希望を感じた。
また、最近注目されているのが「フードバンク」や「こども食堂」への支援だ。食べ物を必要としている人々に届ける活動は、フードロス削減と社会貢献の両方につながる。
「私たちが買い支えることで守られる農業がある。それは未来の食料安全保障に直結する」と語るのは、食料安全保障の専門家。
「日本の食料自給率は、国民一人ひとりの選択の積み重ねで決まる。外国産の安い食品ばかり選べば、国内農業は衰退し、自給率はさらに下がる。それは国家の安全保障リスクを高めることを意味する」
その視点で考えると、国産米を選ぶという小さな行動も、実は大きな意味を持つのかもしれない。
「政策への関心も重要です」と、農業政策に詳しいある大学教授は語る。「選挙の際に、各党の農業政策や食料安全保障に関する政策を比較検討し、投票することも、間接的に日本の農業を守ることにつながります」
つまり、私たちの「選択」は単なる個人的なものではない。それは社会へのメッセージであり、未来への投票でもあるんだ。

【第5章】メタ認知で捉える本質:この危機から私たちは何を学ぶべきか?
最後に、この問題を少し高い視点から見つめ直してみたい。
“当たり前”の脆弱性への気づき
先日、スーパーで小学生の男の子が母親に「なんでお米高くなったの?」と聞いている場面に出くわした。母親は「色々事情があるのよ」と答えるだけで、詳しい説明はしていなかった。
でも、この「色々な事情」こそが、私たちが向き合うべき本質なんじゃないだろうか。
私たちは、水道の蛇口をひねれば水が出るように、スーパーに行けばいつでも食料が手に入ることを「当たり前」だと思ってきた。でも実際には、その「当たり前」を支えているのは、農家の労働であり、気候条件であり、国際的な資源や通貨の流れであり…つまり、非常に多くの要因が絡み合った「脆弱なシステム」なんだ。
新潟で出会った80代の農家のおじいさんは、こんなことを教えてくれた。
「昔は、こんな当たり前じゃなかったよ。戦後すぐは、食べるものがなくて本当に苦労した。もう二度とあんな思いはしたくない。だから米作りを続けてきたんだよ」
食料が安定的に供給されることを当たり前だと思わず、感謝の気持ちを持つこと。そして、その「当たり前」を守るために何ができるかを考えること。それが、今の私たちに求められている姿勢なのかもしれない。

「当たり前」が当たり前じゃないって、小学生の一言にハッとさせられた…。
グローバル経済とローカルな生活の”直結”
この米価問題がはっきりと示しているのは、グローバルとローカルが密接につながっているという現実だ。
「ウクライナで戦争が起きて、肥料の値段が上がる。円安が進んで、輸入資材が高騰する。異常気象で生産量が減る。そうやって、遠く離れた出来事が、私たちの食卓に直接影響するんだよね」と、経済アナリストの友人は言う。
私たちはもはや、自分の住む地域だけを見ていては生きていけない時代に生きている。世界の出来事が、私たちの日常に直結するという認識を持つことが重要なんだ。
最近、「グローカル」という言葉をよく耳にする。これは「グローバルに考え、ローカルに行動する」という意味らしい。確かに、世界の状況を理解しつつ、足元の地域で具体的な行動を起こすという姿勢は、今の時代にぴったりかもしれない。
“効率”だけでは測れない価値への回帰
経済学者の中には「非効率な日本の農業は、市場原理に任せて淘汰されるべき」という意見もある。確かに、大規模化・機械化できる平地と比べて、中山間地域の小規模農業は「効率が悪い」かもしれない。
でも、第2章で見たように、田んぼには食料生産以外にも多くの役割がある。洪水を防ぎ、生態系を支え、美しい景観を作り、地域の文化や伝統を守る…これらの「多面的機能」は、お金に換算できるものではない。
「効率や生産性だけで物事を判断する時代は終わりつつあるんじゃないでしょうか」と語るのは、環境経済学の研究者だ。「SDGsの時代、持続可能性という新しい価値基準が求められています」
この言葉に、私は深く頷かずにはいられなかった。短期的な経済合理性だけでなく、長期的な持続可能性や、数字では測れない価値も大切にする社会。それが、私たちが目指すべき方向なのかもしれない。

田んぼって「お米を作る場所」以上の価値があるんだよね。
効率だけじゃ測れない、大切なもの。
持続可能な社会への”転換点”
気候変動、資源枯渇、人口動態の変化…私たちは今、様々な課題が山積する時代の転換点に立っている。
「今の米価問題は、日本社会の様々な構造的課題が凝縮された形で現れている」と指摘するのは、社会学者の木村先生(仮名)だ。「高齢化、過疎化、グローバル化への対応、環境問題…これらが複雑に絡み合った結果がこの危機なんです」
確かに、この問題は単なる「値上げ」の問題ではなく、日本社会の多くの課題を象徴しているように思える。だからこそ、解決策も一筋縄ではいかないのかもしれない。
でも、危機は変革のチャンスでもある。「環境にやさしい農法への転換」「若者の農業参入の促進」「フードロスの削減」「地域内循環の経済システム構築」…こうした新しい取り組みが、この危機を契機に加速する可能性もある。
私自身、取材の過程で多くの若手農家や、新しい農業の形を模索する人々に出会った。彼らは従来の常識にとらわれず、創意工夫で道を切り開こうとしている。そうした姿に、未来への希望を感じずにはいられなかった。
この米価問題を通じて、私たちは自分たちの社会や生活のあり方そのものを見つめ直す機会を得ているのかもしれない。それは苦しいプロセスかもしれないけれど、より良い未来につながる大切な転換点になるはずだ。
まとめ:未来の食卓を守るために、”今”、私たちがすべきこと
取材を始めた当初、私は単に「米が高くなった」という経済ニュースを追いかけるつもりだった。でも深く掘り下げていくうちに、それが日本の農業、環境、地域社会、食文化、さらには国家の安全保障にまで関わる重大問題だということに気づいた。
JA全中の山野会長が危惧する「消費離れ」は、確かに深刻な問題だ。でも、それは決して避けられない運命ではない。私たち一人ひとりが意識を変え、行動を変えることで、未来は変えられる。
最後に、この取材を通じて私が学んだことをまとめておきたい。
- 米価高騰の背景には、異常気象、生産コスト上昇、円安、そして複雑な需給バランスの変化がある。
- 消費離れは、農家の離農、耕作放棄地の増加、食料自給率低下、食文化の変容、地域経済の衰退という”ドミノ倒し”を引き起こす可能性がある。
- 私たちの家計、食卓の豊かさ、そして健康にも深刻な影響を及ぼす可能性がある。
- 賢い消費者になるための「情報武装」「購入・保存方法の工夫」「調理・食べ方の工夫」など、個人レベルでできることはたくさんある。
- 私たちの消費行動は社会へのメッセージであり、未来への投票でもある。
- この危機は、「当たり前の脆弱性」「グローカルな視点の重要性」「効率だけでは測れない価値」「持続可能な社会への転換点」という、より大きな気づきをもたらしてくれる。
私の大好きな祖母は、いつも「もったいない」という言葉をよく使っていた。子どもの頃は古臭いと思っていたけど、今ならその言葉の深い意味がわかる気がする。それは単に「節約しなさい」という意味ではなく、「物事の本質的な価値を大切にしなさい」という教えだったのだろう。
お米一粒一粒には、農家の方々の汗と努力が詰まっている。私たちの国土を守り、環境を維持し、文化を伝える力がある。そして何より、私たちの命をつなぐ大切な食料なんだ。
未来の世代に、豊かな食卓と安心して暮らせる社会を残すために、私たちは今、何をすべきか?
答えは一つじゃない。でも、まずできることは、この問題に関心を持ち続けること、そして、日々の食に対する意識を変え、小さなことからでも行動を起こしてみることだろう。
この記事が、あなたにとって、日本の食と農の未来について考え、行動するきっかけとなることを願っている。
最後まで読んでくれて、本当にありがとう!また、次の取材でお会いしましょう。
(かずみ)
※※関連記事※※
米価高騰 #消費離れ #日本農業 #食料自給率 #地域経済 #食卓危機 #食文化の未来 #JA全中 #和食の力 #グローカル







コメント