「大学って、みんなの未来のためじゃないの?なのに…」21歳女性ルポライター・みくが鋭く斬る!
皆さん、こんにちは。社会派ルポライターの山田みくです。
今日は電車でスマホを見ていた時、思わず「えっ!?」と声を出してしまうニュースに遭遇しました。京都ノートルダム女子大学が2026年度から学生募集を停止するというんです。
「学生の街」として知られる京都で、しかも60年以上の歴史ある女子大がこんな決断を…。一体何が起きているのか?このニュースの背景には何があるのか?私なりに徹底的に掘り下げてみました。
京都ノートルダム女子大って、どんな大学?
まず基本情報から整理しましょう。個人的に北山エリアは取材で何度か訪れたことがあるのですが、静かで緑豊かな環境にキャンパスがあります。大学の前を通った時、綺麗な校舎と落ち着いた雰囲気が印象的でした。
【表1:京都ノートルダム女子大学 概要】
京都ノートルダム女子大学 概要
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 名称 | 京都ノートルダム女子大学 (Kyoto Notre Dame University) | |
| 所在地 | 京都市左京区下鴨南野々神町 | 北山エリア |
| 設立 | 1961年(昭和36年) | 60年以上の歴史 |
| 設置者 | 学校法人ノートルダム女学院 | カトリック系ミッションスクール |
| 学部(2024年度) | 国際言語文化学部、現代人間学部 | リベラル・アーツ教育を重視 |
| 学生数(目安) | 約1,000人~1,500人程度 | 比較的小規模で、少人数教育が特徴 |
| 特色 | 語学教育、国際交流、キャリア支援、地域連携などに注力 | グローバルな視点と実践力を育成 |
| 今回の発表 | 2026年度以降の学部・大学院の学生募集停止 | 2025年度入学生が最終学年となる見込み |
今回の発表で大切なのは、現在在学中の学生や2025年度に入学する予定の学生には、ちゃんと卒業まで教育の質を落とさずサポートを続けると約束していることです。それでも、60年以上続いてきた大学がこうした決断をするということは、相当な覚悟があったのだと思います。
大学のホームページで学長のメッセージを読みましたが、言葉の端々に苦渋の決断だったことが伝わってきて、胸が痛みました。
なぜこのニュースが衝撃的なのか?その理由を考えてみた
理由① 京都って「学生の街」なんです
私が京都を訪れるたび感じるのは、街全体が若いエネルギーで溢れていること。河原町を歩いても、祇園で友達と飲んでいても(笑)、学生らしき若者たちをよく見かけます。実際、京都は人口に対する学生の割合が日本一高いと言われています。
【表2:京都市内の大学・短期大学数】
| 種類 | 大学・短大の数(概数) | 主な大学例 |
|---|---|---|
| 国立大学 | 複数 | 京都大学、京都工芸繊維大学 |
| 公立大学 | 複数 | 京都市立芸術大学、京都府立大学、京都府立医科大学 |
| 私立大学・短大 | 約40~50校程度? | 同志社、立命館、京都産業、龍谷、佛教、京都女子 など |
| 合計(推定) | 50校以上? | (※大学・短大のキャンパス所在地ベース) |
去年、京都で飲食店の方に取材した時、「学生がいなくなったら、この街は灯が消えたようになる」と言われたことがあります。それほど京都は学生の存在に支えられている街なんです。
だからこそ、「学生の街」の中心地で大学が募集停止するというニュースは、「え、この京都で?何が起きてるの?」という衝撃を与えるわけです。これまで「地方の小さな大学が厳しい」という話はよく聞いていましたが、ついに「聖域」と思われていた京都にまでその波が来たということなんですね。

京都=学生の街ってイメージ、ほんと強いもんね…。そんな京都で大学が募集停止って、まさに“聖域崩壊”って感じで、衝撃デカすぎる…。
理由② ノートルダム女子大学の存在意義
私が特に考えさせられたのは、ノートルダム女子大学という大学が持っていた価値です。単なる無名の大学ではなく、京都で長年女子教育を担ってきた実績がある大学です。
少人数教育の良さについて考えると、私自身、大学時代に300人くらいの大教室で授業を受けることがありましたが、先生の顔も名前も分からないまま単位をもらったこともありました(苦笑)。これに対して少人数教育なら、先生との距離が近く、一人ひとりに目が届きやすい。そういう環境で学びたい学生にとっては、本当に貴重な場所だったと思います。
また、「女子大」という選択肢の意味も大きいと思います。共学が主流の今でも、「女性だけの環境でリーダーシップを学びたい」「女性の視点を活かした学問を深めたい」というニーズはあるはずです。そんな選択肢が一つ失われることは、多様な学びの機会が減るということでもあるんです。
なぜこうなった?3つの深刻な要因
要因1:容赦ない「少子化」の現実
もう耳にタコができるほど聞いている話かもしれませんが、日本の少子化問題は本当に深刻です。特に大学進学の中心となる18歳人口の減少ぶりを見てください。
【表3:日本の18歳人口の推移】
| 年代 | 18歳人口(概数) | 状況・トレンド |
|---|---|---|
| 1992年頃 | 約205万人 | ピーク(第二次ベビーブーム世代) |
| 2000年 | 約151万人 | 減少傾向が顕著に |
| 2010年 | 約122万人 | さらに減少 |
| 2020年 | 約115万人 | 減少ペースはやや緩やかに見えるが、依然として低い |
| 2024年 | 約106万人 | 過去最低レベルを更新中 |
| 2030年予測 | 約100万人割れ? | さらに減少が進む見込み |
| 2040年予測 | 約80万人台? | 本当に危機的なレベル… |
私たちの親世代と比べて、もう半分近くまで減ってしまっているんです。大学の経営は基本的に学生からの学費で成り立っています。特に私立大学はその傾向が強い。学生という「お客さん」がこれだけ減ってしまうと、経営が厳しくなるのは当然なんですよね。
これまでは「定員割れは地方の小規模大学の話でしょ?」と思われていたかもしれません。でも、もうそんな話じゃないんです。少子化の波は都市部も関係なく、日本の全ての大学を飲み込もうとしています。京都でさえ例外ではなくなった…それがノートルダム女子大の募集停止という形で現れたのだと思います。
要因2:「女子大」という選択肢の難しさ
次に考えなければならないのは、「女子大学」というカテゴリー自体の立ち位置です。
私自身、共学の高校・大学に通っていましたが、今の若い世代は「わざわざ女子大を選ぶ理由って何?」と考える人も多いと思います。女性の進路も多様化して、理系、工学系、医学系…どんな分野でも女子学生が当たり前にいる時代です。
「女子大」という括りが、逆に選択肢を狭めているように感じる受験生もいるかもしれません。実際、全国の女子大学数も減少傾向にあります。
【表4:全国の女子大学数の推移】
| 年代 | 女子大学数(概数) | 状況・トレンド |
|---|---|---|
| 1990年代 | 約90~100校? | ピーク期?多くの女子大が存在 |
| 2000年代 | 減少傾向 | 共学化する女子大も出始める |
| 2010年代 | 約80校前後? | 減少傾向続く。学生募集に苦戦する大学も |
| 現在 | 約70~80校? | 緩やかな減少傾向?共学化や募集停止の動きも散見される |
もちろん、今でも独自の教育理念や手厚いサポート、女子リーダー育成など、女子大ならではの強みを持つ大学はたくさんあります。ノートルダム女子大もそうした価値を提供しようと努力してきたはずです。
でも、社会全体の流れとして、女子大が学生を集めるのが以前より難しくなっているのは事実です。少子化でパイが減っているうえに、「女子大」というだけでは選んでもらえない時代になってきているんですね。
要因3:京都の激しすぎる大学間競争

そして三つ目の要因。これは京都ならではのシビアな大学間競争です。
先ほども述べたように、京都には本当にたくさんの大学があります。有名国立大、大規模私立大、特色ある中堅大学、芸術系、宗教系…ありとあらゆるタイプの大学が、狭いエリアで学生を取り合っている状態です。
受験生からすれば「選び放題で良いな」と思うかもしれませんが、大学側からすると地獄です。常に周りの大学を意識して、「うちはここが違う!」「うちに来たらこんなメリットがある!」とアピールし続けなければなりません。
ノートルダム女子大も独自の強みを打ち出してきたでしょうが、大規模な総合大学や、もっと専門分野に特化した大学との競争の中で、埋もれてしまった部分もあったのかもしれません。
少子化で全体のパイが減っている中で、この激しい競争に勝ち残り、安定して学生を確保し続けるのは、本当に難しいことなんです。特に私立大学は、基本的には自力で経営していかなければなりません。学費収入が減れば、教育の質を維持するのも難しくなるし、新しい設備投資もできない。そうなると、さらに魅力が下がって学生が集まらなくなる…という負のスパイラルに陥るリスクもあります。
今回のノートルダム女子大の決断は、「少子化」「女子大を取り巻く環境変化」「京都の激しい大学間競争」という3つの要因が重なって、もう未来に向けて学生を募集し続けるのは難しいと判断せざるを得なかった結果なんだと思います。
このニュースの本質と、私たちが考えるべきこと
これは氷山の一角?大学”大淘汰時代”の始まり
私が一番言いたいのは、今回のノートルダム女子大の件は、決して他人事ではないということです。
「学生の街」京都の、歴史ある女子大でさえこういう決断を迫られるなら、もっと学生集めに苦労している地方の小規模大学はどうなるでしょうか?水面下では、すでに同じような危機に直面している大学が、全国にたくさんあるはずです。
これから数年、数十年で、もっと多くの大学が募集停止、学部再編、統合、閉学に追い込まれる可能性は十分にあります。これは単に大学が減るというだけではなく、日本の「知のインフラ」が縮小していくことでもあるんです。本当に危機的な事態だと思います。
日本の女子大学と女子学生数の推移(2020-2024年)
女子大学数の推移
※2023年以降は募集停止や共学化が進み減少傾向
女子大学生数の推移(万人)
※全体の女子大学生数は増加傾向
私立女子大学の定員割れ率(%)
※2023年度は私立女子大学の77.1%が定員割れ
データについての注意点:
- 検索結果から得られた情報を基に作成しています
- 2024年度は恵泉女学園大学と神戸海星女子学院大学が募集停止
- 2025年度からは複数の女子大学が共学化予定
- 女子大学の数は減少傾向にある一方、全体の女子大学生数は増加傾向
地域社会への影響は?
大学が一つなくなるというのは、その大学の関係者だけの問題ではありません。地域社会への影響も深刻です。
北山エリアでノートルダム女子大の近くを歩いた時、学生向けのカフェや本屋さんを見かけました。そういう店舗は直接的に打撃を受けるでしょう。若者が減れば、地域の消費も冷え込むし、文化的な刺激も少なくなります。
特に地方都市にとって、大学は数少ない「若者が集まる場所」であり、「地域ブランドの核」でもあります。そういう大学がなくなったら、その地域の衰退はさらに加速する可能性が高いんです。
私たちはどう考えるべき?
この厳しい現実を前にして、私たちが考えなければならないことは何でしょうか?私は3つあると思います。
- 高等教育の「質」と「量」のバランス: これだけ18歳人口が減る中で、本当に今と同じ数の大学が必要なのでしょうか?もしかしたら、大学の数を絞って、その分、残った大学の教育の質をもっと上げるべきなのかもしれません。でも、それだと地方の学生の学ぶ機会が奪われるかもしれない…。難しい問題ですが、日本の大学の「適正規模」について、社会全体で真剣に議論する時期に来ていると思います。
- 税金の使い道としての大学: 国公立大学はもちろん、私立大学にも多額の税金(私学助成金など)が投入されています。その税金が、本当に効果的に使われているのか?経営が厳しい大学を延命させるためだけに使われていないか?限られた税金を、未来のためにどう投資していくべきか。これも考えなければなりません。
- 「大学で学ぶ意味」の再考: 良い会社に入るため?資格を取るため?もちろんそれも大事ですが、それだけじゃないはずです。幅広い教養を身につけること、専門分野を探求すること、多様な価値観を持つ仲間と議論すること…そういう「知的な営み」そのものに価値があるんじゃないでしょうか。大学が単なる「就職予備校」になってしまったら、ノートルダム女子大のようなリベラル・アーツを重視する大学の価値が見えにくくなってしまうのかもしれません。
結論:これは単なる一大学の問題じゃない。日本社会全体の警鐘
長くなりましたが、最後にまとめたいと思います。
京都ノートルダム女子大学の学生募集停止。これは単に一つの大学の話ではありません。
「学生の街」京都での募集停止は、少子化、社会の変化、大学間競争という日本の構造的な問題が、ついに「聖域」にまで及んだ証拠です。
これは氷山の一角で、日本の大学はこれから本格的な「大淘汰時代」に突入する可能性が高いと思います。
大学がなくなるということは、地域社会の活力を奪い、日本の「知のインフラ」を弱めることにつながります。本当に深刻な問題です。
私たちは、大学の「数」や「経営」だけでなく、「質」や「学ぶ意味」そのものについて、社会全体で考え直す時期に来ているのだと思います。
今回のニュースは、私たち全員に対する未来への警鐘なのです。この警鐘を、ただのニュースとして流し見るのではなく、自分たちの問題として、しっかり受け止めて考えていく必要があると思います。
最後まで読んでくださってありがとうございました。次回のルポでも、教育問題について取り上げていきたいと思います。
みく(21歳)
## 関連記事 【公式発表】京都ノートルダム女子大学 学生募集停止のお知らせ – 2026年度以降の学生募集停止を決定した経緯と今後の対応について 77%が入学定員割れの女子大学! 人気下落の理由とそれでも女子大学を選ぶメリット – 女子大学が直面する厳しい現実と共学化・募集停止の動向を詳しく解説 大学数・学生数は50年間で倍増、女子占有率も上昇 – 18歳人口減少の中で進む大学の生き残り競争と女子学生比率の変化
広告
|
|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4432d8e8.c1a71384.4432d8e9.fed3928d/?me_id=1213310&item_id=20569612&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4548%2F9784791774548_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


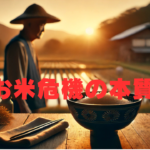
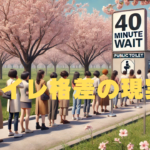



コメント