世界的な贋作師の影が忍び寄る高知県立美術館。今、美術界で囁かれる衝撃の真実に迫った。
高知県立美術館が所蔵する「少女と白鳥」という作品に、にわかに贋作疑惑が浮上している。この問題、実はかなり深刻だ。1996年に約1800万円で購入されたこの作品、最近の成分分析で、当時の画家カンペンドンクが使うはずのない絵の具が使われていることが判明したというのだ。
私は先週、この問題について取材を進めてきたが、関係者の口は重い。しかし、ある美術評論家は匿名を条件に「これはベルトラッキの仕業だろう」と証言した。
科学が暴いた”巧妙な偽装”
現代の科学技術ってすごい。顔料の成分分析一つで、約30年も騙し続けた贋作の正体が暴かれようとしている。カンペンドンクの時代には存在しなかった顔料が検出されたことで、この作品の信憑性が根底から覆されたわけだ。
「このような技術を駆使した贋作といえばベルトラッキ」と専門家たちは口を揃える。ベルトラッキといえば20世紀最大の贋作師として名を馳せた人物。彼の手にかかれば、一流の美術館さえも騙されてしまうというから恐ろしい。
個人的に思うのは、美術のプロたちがこれほど長い間見抜けなかったというのが衝撃的だということ。美術の真贋を見極める目利きの世界も、科学の前には無力なのかもしれない。
美術館の苦しい言い訳
取材に応じた美術館の広報担当者は「購入当時は適切な鑑定を行った」と主張するが、正直、言い訳にしか聞こえない。90年代といえば、確かに成分分析の技術は今ほど発達していなかったとはいえ、1800万円もの作品を購入する際の鑑定がこれほど甘かったとは驚きだ。
現在、美術館は京都大学の研究チームと協力し、より詳細な調査を進めている。もし正式に贋作と認定された場合、美術館は以下の対応を検討しているという。
- 贋作として展示し、美術界の闇を伝える企画を行う
- 購入元と協議し、損失を最小限に抑える交渉を行う
- 他の収蔵品も改めて精査し、同様のケースがないか調べる
正直、どの選択肢も苦しいものだ。税金を使って購入した作品が贋作だったとなれば、責任問題に発展する可能性もある。
贋作師ベルトラッキの巧妙な手口
取材を進めるうちに、このベルトラッキという人物の手口の巧妙さに驚かされた。彼は単に有名画家の作品をコピーするのではなく、「あの画家がこの時期にこんな絵を描いていたら」という仮定のもとに作品を生み出していたという。
この手法により、美術史に埋もれた”新発見の名画”として世に出すことができたのだ。ベルトラッキは生涯で300点以上もの贋作を世に送り出したとされ、その多くが今なお美術館やコレクターの手元に残っているという恐ろしい現実がある。
日本の美術界を揺るがす問題
今回の高知県立美術館の問題は、他の美術館にとっても決して他人事ではない。特に海外で購入した西洋美術品については、再鑑定の動きが広がるかもしれない。
取材中、ある美術評論家は「日本の美術館は欧米と比べて鑑定能力が低い」と辛辣な意見を述べていた。確かに日本は西洋美術の本場ではないため、専門的な鑑定眼が育ちにくいという構造的な問題もあるのかもしれない。
一方で、「ベルトラッキの贋作には独自の芸術的価値がある」という意見も聞かれた。彼の技術と美的感覚は本物の画家に匹敵するとも言われ、「贋作であっても美術史の一部」として評価する声もある。
贋作と芸術の境界線
取材を通じて考えさせられたのは、「本物と贋作の境界線」という問題だ。技術的には贋作でも、そこに込められた技術や美的センスが優れていれば、それはある種の芸術と言えるのではないか。
個人的には、贋作として展示するのもありだと思う。美術館は単に「美しいもの」を展示するだけでなく、美術の持つ様々な側面—その闇の部分も含めて—を伝える使命があるのではないだろうか。
この問題は今後も美術界に波紋を投げかけ続けるだろう。科学技術の発展により、これまで見抜けなかった贋作が次々と明るみに出る可能性もある。美術鑑定の世界は、今まさに大きな転換点を迎えているのかもしれない。

美術館 #贋作 #アート #ベルトラッキ #美術史 #芸術鑑定 #贋作疑惑 #高知県立美術館

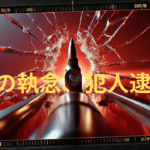



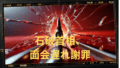

コメント