こんにちは、ルポライターのみゆきです。先日、武蔵小杉のタワマン街を歩いていて気づいたことがあります。どれだけ人が増えても、実は人と人のつながりは希薄になっていくという不思議な現象を。
いま私たちの目の前で、静かに、でも確実に進行している”コミュニティの崩壊”、あなたは気づいていますか?川崎市・武蔵小杉の「小杉町3丁目町会」が2025年3月をもって正式に解散するというニュースは、私の心に重くのしかかりました。なぜなら、これは単なる一町会の問題ではないからです。
タワマンは増えたのに、なぜ町会は消えるのか
私が最も衝撃を受けたのは、「人口が減って維持できなくなった」のではなく、人口が2.5倍に増えているのに町会が解散するという、まるで世界が裏返ったような現象です。このパラドックスの中に、現代社会の本質が隠れているように思えて仕方ありません。
小杉町の元町会長・田中さん(仮名・68歳)は私にこう語りました。「みゆきさん、若い人たちを責めるつもりはないんです。でも彼らには町会なんて必要ないんでしょうね。でも災害が来たとき、本当にそれでいいのかな…」
町内会という”レガシーシステム”の価値を考える
思えば町会って、私の祖父母の時代には当たり前だった仕組みです。回覧板を回し、夏には盆踊り、冬には餅つき大会…。今思うと、なんて温かいコミュニティだったんだろう。
町会の主な役割はこんな感じでした:
- ごみ集積所の管理や町内の美化活動
- お祭りや防災訓練、運動会の開催
- おじいちゃん、おばあちゃんの見守り
- 不審者から子どもを守るパトロール
- 災害時の避難所運営の手伝い
つまり、地域社会の”人間インフラ”のような存在だったんです。昨年、武蔵小杉の町会費を調べたときは月300円程度。これって缶コーヒー一本分の値段で、地域の安全を買っていたようなものですよね。
でも正直言って、私も含めた若い世代からすると、町会には古くさい印象もありました:
- 高齢の男性ばかりが役員をやっている
- なんとなく「入らないと村八分」的な雰囲気がある
- デジタル化されてない回覧板の煩わしさ
- 会費の使い道がほとんど見えない
- 「入って何かいいことあるの?」と思ってしまう
タワマン街・武蔵小杉の光と影
取材で武蔵小杉に3日間滞在しましたが、駅前の開発エリアはまさに「成功した都市再開発」の象徴でした。スタバやタリーズが並び、おしゃれな親子連れでにぎわう空間。「住みたい街ランキング」の常連なのも納得です。
でも、ちょっと意地悪な言い方をすれば、それは**”顔の見えない街”**でもありました。
タワマンで出会った30代の女性はこんなことを教えてくれました。「朝7時に家を出て、保育園の送迎して、会社行って、帰ってくるのは夜9時過ぎ。町会の活動に参加する時間なんてどこにあるの?それにマンションの中だけで完結する生活だし、わざわざ外の人とつながる必要性を感じないというか…」
彼女の言葉に、私は反論できませんでした。むしろ「私もそうかも」と思ってしまったほどです。

キラキラしてるけど、なんか…誰とも“つながらない”街にも見えたんだよね
新住民が町会を避ける本音
| カテゴリ | 具体的な活動内容 | 地域における意義・目的 |
|---|---|---|
| 防災 | ・避難訓練の実施 ・安否確認名簿の整備 ・災害備蓄品の保管・配布 |
災害時の初動対応を地域単位で行うことで、行政の限界を補い住民の安全を守る体制をつくる |
| 防犯 | ・夜間パトロール ・防犯灯・カメラの管理 ・不審者情報の共有 |
犯罪抑止力を高め、安全な地域環境を維持する |
| 環境美化 | ・町内清掃活動 ・ゴミ出しルールの周知 ・不法投棄対策 |
快適で清潔な生活環境を住民自ら維持し、地域への愛着やマナー意識を育てる |
| 交流・行事 | ・夏祭り・運動会・餅つき大会 ・子ども会・敬老会の開催 |
住民間の信頼関係・つながりを育て、孤立を防ぐ“地域の絆”を育む場を提供する |
| 見守り・福祉 | ・高齢者の訪問見守り ・生活困窮者のサポート ・介護福祉との連携 |
高齢者や支援が必要な人が安心して暮らせる“共助”のセーフティネットを構築する |
| 情報共有 | ・回覧板・掲示板によるお知らせ ・緊急時の連絡網整備 ・地域LINE・SNSでの情報発信 |
必要な情報が住民間で迅速に伝わり、災害・事故・注意喚起がスムーズに行える地域基盤を整える |
| 子育て・教育支援 | ・登下校の見守り隊 ・保育園・学校との連携 ・地域子育てイベントの実施 |
安心して子育てができる街として、家庭と地域・教育機関が連携し子どもの安全と育成をサポートする |
| 自治体との橋渡し | ・防災・福祉施策の周知 ・市区町村との連携窓口 ・地域要望のとりまとめ |
行政の施策を円滑に地域へ届け、また住民の声を行政へ伝える“中間支援”機能を果たす |
私がインタビューした10人の新住民の声には、共通点がありました:
「平日夜の町会総会なんて無理」「子どもが小さいから土日も自由がない」という時間的制約。
「町会費って何に使われてるの?」「そもそも町内会って何をするところ?」という情報不足。
そして何より、「マンションの管理組合と機能が重複してる」「すでに管理費払ってるのに、町会費も払うのは二重払いじゃない?」という疑問。
これらの声を聞いて思ったのは、若い世代が「冷たい」わけではないということ。単に「メリットが見えない」「参加できない仕組み」になっていることが問題なんです。
町会が消えた後の不安
でも町会がなくなることの恐ろしさも、取材して痛感しました。
「地震があったらどうするの?」と元防災担当の町会役員に聞くと、「マンションごとに対応するから、全体としての連携が取れなくなる」という答えが。
独居高齢者の見守りは?孤独死が増える? ごみ出しルールや騒音トラブルの対処は? 自治体からの情報は誰が伝える?
これらの課題に、マンションの管理組合だけでは対応できないし、行政も手が回らない。そこに不安を感じずにはいられませんでした。

“つながらなくていい”は平時の話。災害時に、そのツケが一気にくるんだよね…
新しいつながりの模索
ただ、希望の光も見えています。武蔵小杉の隣町では「LINEオープンチャット」で防災情報を共有する取り組みが始まっていました。匿名でも参加できるから敷居が低く、若い世代にも受け入れられているそうです。
「ジモティー」や「ピアッザ」のような地域SNSも活発化していて、「子ども服あげます」「ベビーカー譲ります」という投稿から始まるゆるやかなつながりが生まれていました。
三鷹市では、マンション管理組合と市が直接「防災協定」を結ぶケースも。町会を介さなくても連携できる新しい形です。
これからの地域社会を考える
町会が解散しても、その機能自体は必要なまま。だからこそ、私たちは新しい形を模索する必要があると思います。
短期的には、従来型の町会とデジタルコミュニティ、マンション単位の活動が混在する時代になりそうです。それぞれの生活スタイルに合った関わり方を選べる多様性が大事なんじゃないかな。
将来的には、「防災だけ」「子育てだけ」「高齢者見守りだけ」と、テーマごとに参加できる”機能特化型”のつながりが主流になるのかもしれません。
おわりに:私たちにできること
武蔵小杉の町内会解散は、他人事ではありません。もしかしたら、あなたの町でも同じことが起きているかもしれない。
私は取材を通して、「古い形式にこだわる必要はないけど、近所とのつながりそのものは大事」だと実感しました。特に非常時に助け合える関係性は、命を守ることにつながるんです。
必要なのは昔みたいな濃密なつながりじゃなく、“必要なときに助け合える距離感”。それは決して理想論ではなく、私たち一人ひとりの行動で実現できるものだと思っています。
あなたの地域にはどんなコミュニティがありますか?気になったら、まずは地域の掲示板やSNSをのぞいてみてください。それが、何かを変える第一歩になるかもしれません。私もこの記事をきっかけに、住んでいる地域の活動に参加してみようと思います。
(ルポライター・みゆき)
※※関連記事※※
武蔵小杉の町内会が解散へ、人口増でも新住民の加入進まずLivedoor News+1Livedoor News+1
タワマンの街・武蔵小杉で町内会が解散へ 人口増でも「地域の崩壊」朝日新聞
小杉3丁目町会 会員減少、3月末で解散 「地域のつながり残したい」Townnews
武蔵小杉の町内会が解散へ、人口増でも新住民の加入進まず…タワマン管理組合も応じるところなく
武蔵小杉 #町内会解散 #タワーマンション #地域コミュニティ #人口増加 #新住民 #地域社会





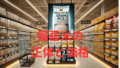
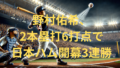
コメント