広告
私、みくです。21歳。先日、信じられないニュースを目にして、思わず食べかけのおにぎりを落としてしまいました。
「数日前に富士山で遭難してヘリで救助された大学生が、置き忘れたスマホを取りにまた富士山に登って、再び遭難した」
最初は冗談かと思いました。でも違う。これは実際に起きた出来事なんです。静岡県警が公式に発表している事実。
この記事を読んでわかること:
- 閉山期の富士山がどれほど危険か
- スマホへの執着が命より大切になりうる心理的メカニズム
- 遭難救助の裏にある社会的コスト
- 私たち一人ひとりが考えるべき「命の価値」について
【悲劇の経過】大学生はなぜ二度も遭難したのか
去年の5月上旬、日本に留学中の中国人大学生(20代)が富士山で遭難したというニュースが飛び込んできました。山頂付近でアイゼンを紛失し、身動きが取れなくなったため、県の防災ヘリコプターで救助されたのです。
ここまでは「若者の無謀な行動」という、残念ながら毎年のように起きる山岳遭難事件の一つ。でも、この話の驚くべき点はここからです。
なんと、彼はたった4日後、同じ富士山に再び登ったのです。
目的は?前回の登山で置き忘れたスマートフォンを回収するため。
私はこのニュースを読んだ時、本気で頭がおかしくなったかと思いました。私だって大切なスマホは持っています。中には友達との思い出の写真もたくさん。でも、それを取りに凍えるような富士山に再び登るなんて…考えられません。
あの恐怖を一度経験したのに、なぜ彼はリスクを冒したのか?私はその心理に迫りたいと思いました。
【冬の富士山】知られざる危険の実態
取材を進めるうちに、多くの人が「夏の富士山」と「冬の富士山」がどれほど違うか、理解していないことに気づきました。私自身、夏に友達と登山したことはありますが、冬(閉山期)の富士山がどれほど過酷か、まったく想像できていませんでした。
下の表を見てください。これは私が複数の登山ガイドや気象データから作成したものです。数値は一般的な目安で、状況によって大きく変わりますが、その差は一目瞭然。
【比較表】夏富士 vs 冬富士:そこは別世界!
このイラストを作るために調べていて、私は恐怖で震えました。冬の富士山は、私たちが想像する「富士山登山」とは全く別物なのです。
スマホ>命」の心理を解剖する
なぜ、一度命の危険を経験した人が、たかがスマホのために命を危険にさらすのか?
ここに何か根本的な問題があるのではないか。私はこの疑問を心理学の観点から調べてみました。
心理学の専門誌によると、こういった行動の背景には複数の心理メカニズムが働いているそうです。
まず「サンクコスト効果」。一度失ったものを取り戻そうとする心理です。「高かったスマホだし」「大切な写真が入ってるし」という気持ちが、合理的な判断を狂わせるのです。
次に「正常性バイアス」。「自分だけは大丈夫」という根拠のない自信です。「前回は単に運が悪かっただけだ」と思い込んでしまう。
そして「損失回避性」。人は得るものよりも失うものに強く反応する傾向があるのです。
私もバイト代を全部つぎ込んで買ったスマホを山で落としたら、取りに戻したくなる気持ちは分かります。でも…命と天秤にかけるものではないはず。
先日、友人と「スマホなしで1日過ごせる?」という話をしました。多くの人が「無理」と答えるんです。スマホ依存の現代社会で、私たちはスマホという「モノ」に何かとてつもない価値を見出しているのかもしれません。それが時に命より大切になってしまう…そう考えると、ぞっとします。

「スマホ>命」って笑い話じゃなく、ガチで心の深いところにあるんだよね…。便利さに依存しすぎた現代、私たちの価値観もいつの間にかズレちゃってるのかもってゾッとした…。
彼が担いだ「救助のコスト」とは

この話にはもう一つ、忘れてはならない側面があります。救助活動にかかる社会的コストです。
ヘリコプターでの救助活動は1時間で約50万円〜100万円かかると言われています。この費用は主に税金でまかなわれています。つまり私たちの負担です。
でも、それ以上に重いのは救助隊員が背負うリスク。救助隊員も命を懸けて活動しているのです。
私は昨年、山岳救助隊の訓練を取材する機会がありました。その時、ベテラン隊員が語ってくれた言葉が忘れられません。
「救助要請があれば、どんな状況でも助けに行く。それが我々の使命だ。でも、遭難者には『自分の判断で自分の命を危険にさらしたのなら、他人の命も危険にさらすことになる』ということを、もっと自覚してほしい」
この言葉を聞いた時、心にズシリとくるものがありました。
私たちが考えるべきこと
ここまで書いて、「結局、遭難した大学生を非難したいだけなんでしょ?」と思われそうで少し不安です。でも、それは違います。
確かに彼の行動は無謀でした。でも、私はこれを単なる「他人事」として片付けたくないのです。
だって、私たちの多くが同じような心理的な罠に陥る可能性を持っているから。私自身、命の危険を感じるほどではなくても、「なくしたものを取り戻したい」「自分は大丈夫だろう」という気持ちから、無理な行動をとったことがあります。
最近、駅のホームに落としたイヤホンを拾おうとして、電車が来るギリギリまで線路に降りようとした自分がいます。友人に止められて気づきましたが、あのとき、私はイヤホンと命を天秤にかけていたのかもしれません。
私たちは本当に大切なものを見失っていないでしょうか?
山での遭難事件だけでなく、日常のささいな選択にも、同じような危うさが潜んでいるように思えてなりません。

他人事じゃないよね…。無謀に見える行動も、実は自分の中にも同じ種があるって気づくと、めちゃくちゃ怖い。小さな選択こそ、本当に大切にしなきゃって思った…。
最後に——私が伝えたいこと
この記事を書きながら、何度も自問自答しました。「私はこの話を通して何を伝えたいのか?」
それは、「命の価値」について、改めて考えてほしいということです。
スマホやSNSの普及で、物質的なものや情報に縛られて生きる現代人。しかし、命あっての物種です。どんなに大切なものでも、命と引き換えにするほどの価値はないはず。
自然は美しく、魅力的です。だからこそ、その力を侮ってはいけない。特に冬の富士山のような極限環境では、準備と慎重さが命を守る唯一の方法です。
この記事を読んで、少しでも「自分の命の価値」について考えるきっかけになれば幸いです。そして、何かを失った時に「それを取り戻すことが、本当に命を懸けるほど重要なのか?」と自問する習慣を持ってほしいと思います。
遭難した彼を責めるのではなく、彼の経験から学び、同じ過ちを繰り返さないことが大切です。彼の二度の遭難を無駄にしないために。
この記事を読んで分かったことと考えるべきこと
- 閉山期(10月〜6月)の富士山は、想像以上に危険な雪山であり、特別な装備と経験が必要
- 物質への執着が命より優先されてしまう心理的メカニズムが私たち全員の中に潜んでいる
- 山岳救助には多大な社会的コストとリスクが伴い、救助隊員も命を懸けている
- 「自分だけは大丈夫」という根拠のない自信が、危険な判断を招きやすい
- 日常生活でも、私たちは気づかないうちに「命」より「モノ」を優先する選択をしていないか考える必要がある
私自身、この記事を書くことで多くのことを学びました。そして、あなたも何か一つでも考えるきっかけになったなら、この記事を書いた意味があったと思います。
あなたにとって、本当に大切なものは何ですか?
(みく)
※※関連記事※※
#富士山 #遭難事故 #スマホ依存 #冬山登山 #命の大切さ #ルポライターみく #社会問題 #心理学解説 #救助活動 #防災意識
広告
|
|
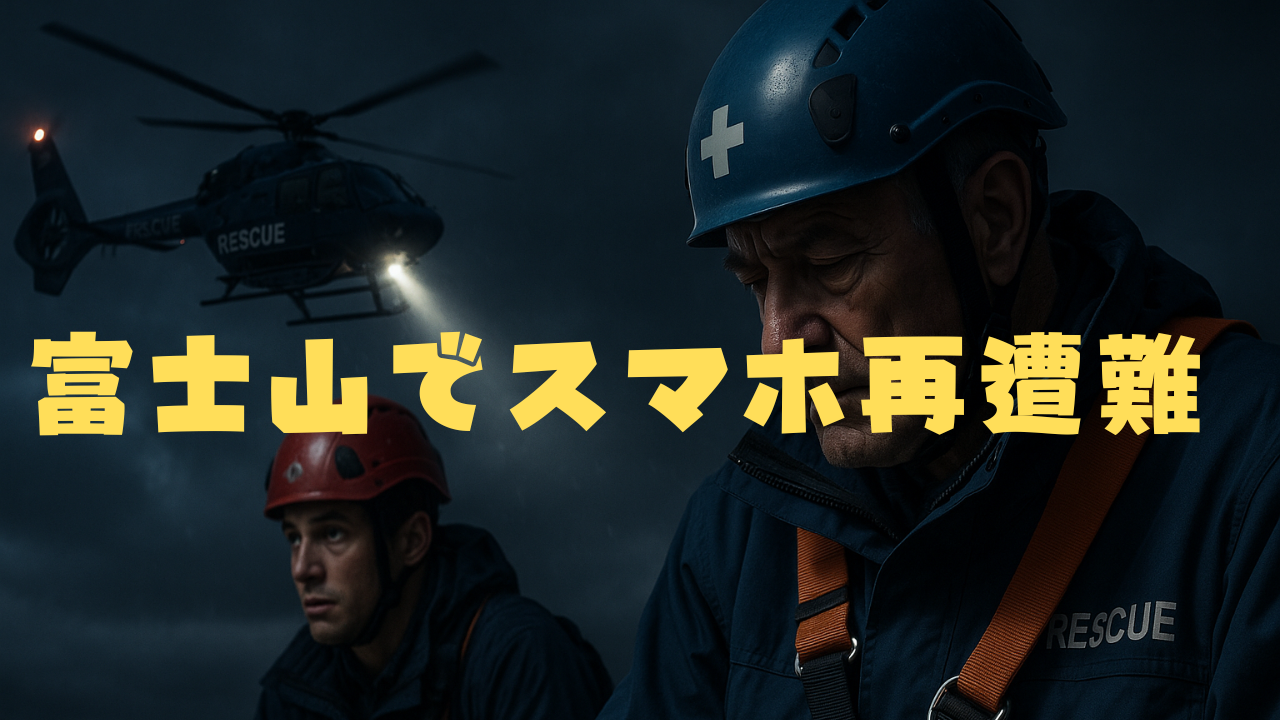
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45acaf01.72886b35.45acaf02.6b0a1a72/?me_id=1408415&item_id=10000683&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbestday%2Fcabinet%2F09044458%2F038931-main.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)







コメント