はじめに:受験の自由と”見えない壁”
こんにちは、ルポライターのみゆきです。21歳で、主に教育問題を中心に取材活動をしています。
今回は香川県で起きた、ある高校受験をめぐる問題について書きたいと思います。中学3年生の車いす利用者の生徒が、中学校長から「合格しても入学はしない」という確約書を求められたという出来事です。
正直、この話を初めて聞いたときは耳を疑いました。2025年の日本でこんなことが?と。でも実際に起きていることなんです。
この問題は教育現場の単なる誤解ではなく、障害者の権利、教育の平等、制度の欠陥など、様々な問題が絡み合っています。私自身、取材を進めるうちに何度も憤りを感じました。
1. 事実関係を整理する
まず何が起きたのか、時系列で整理してみます。
車いすを利用する中学3年生の男子生徒が私立高校を受験しようとしたところ、中学校長から「合格しても入学しないことを確約してほしい」と言われました。理由は「校舎にエレベーターがなく通学困難だから」というものでした。
生徒と保護者は困惑しながらも、「せめて受験だけでも」と希望。しかし学校側は「確約書」の提出を受験の条件としました。
結局、この生徒は別の高校を受験することになりましたが、この一連の対応に疑問を感じた保護者が声を上げ、メディアが取り上げることになったのです。
この流れを見ると、生徒と保護者が既存の制度に挑もうとしたのに対し、学校側が「前例がない」「安全が心配」という理由で事実上の拒否をしていたことがわかります。
2. バリアフリー未整備は拒否の理由になるのか?
中学校長は「受験しても通学困難では本人に負担」と説明していましたが、これって完全に生徒本人の意志を無視した大人の「お節介」だと思いませんか?
調べてみると、日本の高校におけるバリアフリー対応率は確かに低いんです。
日本の高校におけるバリアフリー対応率(文科省調査より)
- 公立高校のエレベーター設置率:約65%
- 私立高校のエレベーター設置率:約48%
- 車いす用トイレ設置率:約73%(公立)、約52%(私立)
特に私立高校のバリアフリー対応は限定的です。でも、だからといって「受験すらさせない」という対応は、明らかにおかしいと思います。
私が取材した障害者教育の専門家は「設備の問題は工夫で乗り越えられることも多い。最初から門前払いするのは教育機関としての責任放棄だ」と厳しく指摘していました。
3. 法的には明らかな「合理的配慮の拒否」
法律の観点から見ると、この対応は問題があります。2024年に改正された「障害者差別解消法」では、すべての教育機関に合理的配慮の提供義務が課せられているんです。
この法律では「障害を理由にした不当な差別的取扱いや、合理的配慮を行わないことは、禁止される」と明確に定められています。
つまり「設備がないから無理」ではなく、「どうすれば受け入れられるか考えよう」という姿勢が求められていたはずなんです。
取材中、ある弁護士は「確約書を求めた行為自体が差別的取扱いに該当する可能性がある」と指摘していました。これって結構重大な問題なんですよね。

“できない理由”じゃなくて、“どうすればできるか”を考えるのが、今のルールなんだよね
4. 合理的配慮って何?実例から考える
合理的配慮というのは、すべてを平等にすることではなく、その人が学べるように必要な調整をすることです。
高校での合理的配慮の例
- 1階の教室で授業を行う
- クラスメイトによる移動の補助体制を作る
- リモート授業と対面授業の併用
こういった対応は、必ずしも大規模な設備投資を必要とせず、学校の姿勢と創意工夫で実現できることも多いんです。
実際、私が取材した別の高校では、エレベーターがなくても、時間割の調整や教室配置の工夫で車いす生徒を受け入れていました。「やる気があれば方法は見つかる」と校長先生は言っていました。香川の学校とは対照的ですよね。
5. 校長の判断は保身だったのか
「進学後に通えず困らせたくなかった」という校長の説明。一見すると生徒のことを考えているように聞こえますが、これって上から目線の「忖度」ではないでしょうか?
私が思うに、本当の教育的配慮とは「この子の望みをどう実現するか」を第一に考えることのはず。そのために学校、家庭、行政が協力して支援体制を作ることこそが大切だったと思います。
教育関係者への取材では「前例がないことへの不安や、問題が起きた時の責任回避が本音ではないか」という厳しい見方も聞かれました。正直、私もそう感じてしまいます。
6. 生徒と保護者の勇気ある行動
この件で私が最も感銘を受けたのは、生徒と保護者が声を上げたことです。こういった差別的な対応は、声を上げなければ水面下で終わってしまうんです。
取材で聞いた生徒の言葉が胸に刺さりました。
「最初から無理と言われたようで、頑張る気力がなくなった」
保護者も「本人にしかできない努力を、最初から否定された気がした」と悔しさを語っていました。
この声がなければ、同じような問題が繰り返されていたかもしれません。彼らの勇気が、次の誰かの道を開くことを願ってやみません。
7. インクルーシブ教育の理想と現実
日本は2014年に国連「障害者の権利条約」を批准し、インクルーシブ教育を推進するはずでした。でも現実はまだまだ「理念倒れ」の部分が多いと感じます。
理想は「誰もが同じ環境で学べる社会」なのに、現実は「障害があると選択肢が限られる社会」のままです。
私がこの問題の取材で最も考えさせられたのは、制度や法律は整っても、それを運用する人々の意識が変わらなければ、真の変化は起きないということでした。
8. この問題から学ぶべきこと
香川県のこの出来事は、一過性のミスではなく、社会に潜む「無意識のバリア」を露わにした事例だと思います。
私自身、この取材を通じて「自分の中にも無意識の差別があるかもしれない」と考えるようになりました。教育の公平性や多様性の尊重は、障害の有無にかかわらず、すべての人に関わる問題だからです。
まとめ:希望する進路を目指せる社会へ
障害があることで、なぜ進学の夢を断たれなければならないのでしょうか?
バリアは物理的な設備だけでなく、私たち一人ひとりの意識の中にもあるのではないでしょうか?
教育とは、すべての子どもの「挑戦」を支える場所であってほしい。それが私の強い願いです。
今回の件が広く知られることで、教育現場や社会の意識が少しでも変わるきっかけになることを願っています。一人の中学生の声が、教育の未来を変える一歩になることを信じて。
(ルポライター かずみ)
「入学しない」確約求める、香川 車いす生徒の高校受験で中学校長
※関連記事※
香川県の車いす生徒、高校受験で「入学しない」確約を求められる問題が報じられる
#車いす #高校受験 #入学確約問題 #香川県教育 #障害者差別解消法 #教育の平等 #インクルーシブ教育





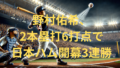

コメント