2025年3月。新潟で起きたこの出来事を、私は“ひとりの知事のスキャンダル”なんて軽く片付けることができなかった。
なぜか。
この問題の裏にあるのは、ひとつの組織の中で、権力がどのようにふるわれていたのか、そしてそれを誰も止められなかった構造的な怖さだと思うからだ。ニュースで取り上げられるのは「辞めるのか、辞めないのか」というところばかり。でも、もっと大事なのは、信頼ってどう壊れて、どう取り戻すべきなのか、って話じゃないだろうか。
パワハラはあったのか?その調査のリアル
今回のパワハラ認定は、外部の法律家や臨床心理士が入った第三者委員会が行ったもの。職員21人からの聞き取りに加え、メールのやりとりなど文書資料も精査された。僕も報告書を読み込んだけれど、主観じゃなくて客観的な証拠が重視されていて、正直、これは相当しっかりした調査だと感じた。
「感じたかどうか」ではなく、「実際に起きていたか」。その線引きが明確だった。
支配の構図、その中身とは
| パワハラ要素 | 内容と影響 |
|---|---|
| 威圧的な言葉 | 長期間にわたり繰り返され、職員が萎縮。発言の自由を奪う |
| 組織的黙認 | 幹部クラスの沈黙により、内部通報の道が閉ざされる |
| 精神的追い込み | 対象職員のメンタル不調、休職者も発生 |
正直に言うと、こうした話は他の自治体や企業でも聞いたことがある。でも今回のケースが重たいのは、“誰も止められなかった”という点。つまり、パワハラが個人の問題ではなく、組織ぐるみで放置されていたことが見えてくる。
これは、ひとつのリーダーの問題で終わらせてはいけないと思う。
辞めないという決断の意味
記者会見で斎藤知事は、「逃げない」と言った。私もその映像を何度か見返したけど、あの表情には確かに覚悟があった。でも、その“覚悟”が果たして誰のためなのか?そこには大きな疑問が残る。
表向きには「今、知事が辞めたら県政が混乱する」という論理。確かに、人口減少や地域医療、気候政策など、新潟が抱える課題は山積みだ。知事の不在でそれが滞るのは、県民にとってもリスクかもしれない。
でも、裏を返せば「時間を稼いで嵐が過ぎるのを待っている」ようにも見える。これまでの政治でもよく見てきた光景だ。説明責任を果たすと言いつつ、具体的な行動は後回し。記者の質問には答えるけれど、核心には触れない。そんな印象も否めなかった。
県庁の“対応”に潜むリスク
第三者委員会が特に強調していたのが、「知事だけの問題じゃない」という点。組織全体が、内部通報を握り潰し、適切な対応を取らなかった。そのことが、むしろ深刻だ。
| 違法性 | 内容 | リスク |
|---|---|---|
| 通報無視 | 正式ルートでの通報が複数件、対応されず | 労働安全衛生法違反の可能性 |
| 内部調査の不備 | 組織内調査が非公開、文書記録が不完全 | 公文書管理法違反の疑い |
| 被害者の権利無視 | 精神的ケアなし。配置転換も実施されず | 労働契約法違反・訴訟リスク |
もし自分が県職員だったら、この状況に信頼なんて持てないだろうなと正直思った。通報しても無視され、精神的に追い詰められても何のフォローもない。そんな組織に希望なんて持てるだろうか。
世論と議会の“温度差”
SNSを見ていると、若い人たちの声が圧倒的に厳しい。「辞めろ」「信用できない」──そんな声が多く飛び交っている。かたや、議会では慎重論が目立つ。自民系の議員は「もう少し様子を見るべき」というスタンスで、すぐに辞任を求める空気はそこまで強くない。
| 反応 | 内容 |
|---|---|
| SNS世論 | 「辞職すべき」「責任をとれ」など厳しい意見多数 |
| 与党議員 | 慎重姿勢。次の定例会まで判断を保留する声も |
| 野党系 | 問責決議の検討。ただし、過半数に届くかは微妙 |
こういうズレ、よくあるけど、今回は特に大きく感じた。議会の判断が世論の感覚とズレていると、政治不信が加速する。その先に待っているのは、投票率の低下や無関心だ。
そしてそれこそが、一番避けるべき事態なんじゃないかと思う。
これからどうなるのか
知事は「議会が閉会したあとに改めて説明する」と言っているけど、それが“説明”で終わるのか、“決断”を伴うのかで、未来は変わってくる。
| シナリオ | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自主辞任 | 自ら職を辞す | 信頼回復、県政再出発の象徴に | 施策中断、混乱 |
| 続投し改革宣言 | 改革を主導し自ら改善策を実施 | 政策の継続、責任遂行 | 信頼回復には時間が必要 |
| 議会による不信任 | 議会が辞職を強制 | 公的判断として明確 | 政治的対立激化、県民分断 |
個人的には、ただ辞めるよりも、「なぜこうなったのか」を洗いざらい語って、その上で再発防止策を実行する。そんな“泥臭いリーダーシップ”を見せてほしい気もする。
でも、それをやるには相当な覚悟がいる。うわべだけの反省では、もう誰も信じないから。
最後に──信頼を取り戻すには
この問題は、結局のところ「信頼」の話だ。辞職するかどうか、よりも、「自分たちの声が届く行政なのか」「また同じことが起きないのか」──その不安にどう答えるか。
必要なのは、被害者への謝罪や補償だけじゃない。再発防止のために、どんな人が、どう監視していくのか。そして、それを県民が見てわかる形にすること。
信頼って、言葉じゃ取り戻せない。行動しかない。
そして僕たちも、ただ「辞めろ」と叫ぶだけじゃなく、「何をすれば二度と同じことが起きないか」を一緒に考えていく必要がある。政治と距離を置きすぎると、結局、誰かがまた泣くことになるから。
──信頼を失った組織が、それを取り戻すまでには、長い時間がかかる。でも、そのスタートラインに立つことだけは、今すぐにでもできるはずだ。
【速報】斎藤知事「今読み続けています。議会閉会後にコメントしたい」現時点で辞職否定「県政前に進めるのが責任」第三者委パワハラ認定 県対応を「違法」と指摘
※※関連記事※※
【斎藤知事、26日の県議会閉会以降に見解示す意向 告発文書問題 第三者委の報告書提出受け
立花孝志氏へ「黒幕」文書、受け渡し場所に維新の岸口実・兵庫県議…「渡したと言われても抗弁しようがない」
斎藤知事 #パワハラ問題 #新潟県政 #地方政治 #第三者委員会 #辞職問題 #コンプライアンス


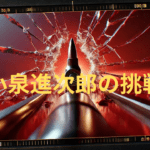




コメント