仕組み・背景・影響・課題を徹底解説【完全保存版】
報告:ルポライター みゆき
はじめに:ガソリンが家計を直撃する時代へ

先日、実家に帰省するために車を借りたのですが、給油するときに思わずため息が出ました。リッター182円。この価格を見たとき、「車を持つなんて絶対無理だな」と思ったのは私だけじゃないはずです。
ここ数年、ガソリン価格の異常な高騰は私たちの生活を直撃しています。全国平均でリッター180円台は当たり前になり、地方に取材に行くと190円を超える看板を目にすることも。
「車を使わなきゃ生活できない」
「遠出をあきらめる週末が増えた」
「物流コストが跳ね上がり、商品価格も高騰している」
こんな声を取材中に何度も聞いてきました。そんな中、ついに政府が動きだしたんです。定額で10円を補助する新制度の導入を検討し始めたのです。でも、これって本当に私たちの助けになるのでしょうか?
1. ガソリン高騰の構造とは? なぜこれほど値上がりしたのか
先日、石油元売り会社のある社員に話を聞く機会がありました。「みゆきさん、ガソリン価格ってね、実はかなり複雑な仕組みで決まっているんですよ」と教えてくれました。
ガソリン価格は、こんな多段構造で成り立っているそうです。
■ ガソリン価格の内訳(2025年現在)
構成要素 価格の目安(円/L)
原油輸入コスト 約77〜80円
精製・流通・販売コスト 約30〜35円
ガソリン税・石油税等 約56.6円
消費税(10%) 約16〜18円
合計 約180〜190円
「この表を見てピンときませんか?」とその社員。「税金だけで約72円も取られているんです。二重課税とも言えますよね」。なるほど、税金がこんなに大きな割合を占めていたとは…。
主な上昇要因は、ウクライナ侵攻による原油供給不安、OPECの減産方針、円安ドル高の影響、それに日本特有の”二重課税”構造(ガソリン税+消費税)があるようです。私たちの生活を直撃するこの価格高騰、いつまで続くのでしょうか。

「180円のうち72円が税金って…そりゃ高いはずだよね。二重課税、ほんと勘弁してほしい」
2. 「燃料価格激変緩和措置」から「定額補助」へ
これまで政府は「燃料価格激変緩和措置」という、なんとも覚えづらい名前の制度を実施していました。170円を超える部分について補助金を支給する方式です。でも正直、その効果を実感できた人はどれだけいるでしょうか?
私も地方取材で何度かガソリンスタンドの店主に質問しましたが、「いや〜、あの制度は複雑すぎて、お客さんにも説明しづらかったですよ」という答えが返ってきました。
■ 現行制度の課題
- 補助が複雑で分かりづらい(私も理解できませんでした…)
- 価格が下がると補助が止まり、また急騰するリスクあり
- 店頭価格に反映されにくく、消費者の実感が薄い
そこで新たに浮上してきたのが「定額補助」という仕組みです。
■ 新制度の特徴(予定)
特徴 内容
補助額 一律10円/L(価格に関係なく)
対象 ガソリン・軽油・灯油など
適用タイミング 2025年度早期導入予定(調整中)
目的 家計支援・燃料価格の平準化・物価対策
財源 一般会計、燃料税の再分配などが候補
「とにかく分かりやすく!」というのがポイントのようです。でも、この10円、実際のところどれだけ効果があるのでしょうか?
3. 影響:家庭・業界・地域社会にどんな変化が?
先日、地方取材で知り合った4人家族のお母さんはこう言っていました。「週に満タン1回は入れるから、月に4,000円くらい助かるかな。でも正直、子どもの習い事一つ分にもならないのよね…」
確かに計算してみると、週50L給油で月2,000円、年間24,000円の節約になります。大きいような、小さいような…。でも、地方の高頻度通勤層や子育て世帯にとっては、少しでも助かる金額かもしれません。
特に印象的だったのは、東北地方のタクシー運転手さんの言葉です。「燃料代が下がれば、その分を車両整備に回せる。安全面でもプラスなんだよ」と。確かに、単なる「お得感」だけではない効果もありそうです。
地域による差も気になります。取材で回った限りでも、山形県では185円を超えるガソリンスタンドを見かけましたが、千葉や埼玉では平均170円台前半。同じ10円補助でも、地域によって感じる恩恵は違いそうです。
私自身は東京住まいで車を持っていませんが、地方の友人から「みゆき、都会の人には分からないだろうけど、こっちは本当に車がないと生きていけないんだよ」と言われたことがあります。確かに、その通りかもしれません。
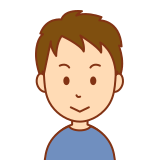
「月2,000円の差でも、“その2,000円”に生活かかってる人がいるって…東京にいると気づきにくいよね」
4. 課題1:年2,400億円超の財政負担は可能か?
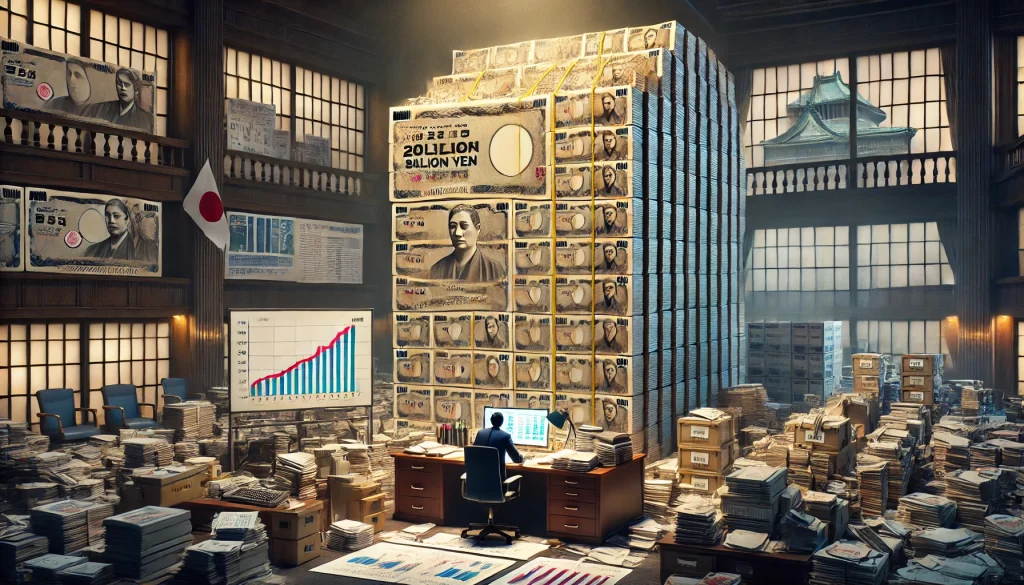
さて、ここで疑問が湧きます。この補助金、一体いくらかかるのでしょうか?経済担当記者の先輩に聞いたところ、「政府試算によると、10円補助を全国で1年間継続すると年間約2,400億円の財政支出が必要になる」とのこと。
「えっ、2,400億円!?」思わず声が出てしまいました。この巨額の費用は一体どこから出すのでしょうか。
想定される財源案としては、燃料税の一部を再分配する案や、予備費・赤字国債の活用、さらには炭素税・カーボンプライシングとの組み合わせなどが挙げられています。
財務省関係者に取材したときには、「正直言って、永続的に続けられる制度ではないですね」と耳打ちされました。結局、一時的な対策にしかならないのではないか、という懸念が残ります。
5. 課題2:環境政策との整合性は?

個人的に最も気になるのは、この政策と環境問題の関係です。環境NPOでボランティアをしている友人は怒り心頭でした。「みゆき、ガソリンを安くするって、脱炭素社会の目標と真逆じゃない?政府の左手と右手が別のことをしてるよ」と。
確かに、
- EV(電気自動車)やPHVの導入促進に水を差す可能性
- 二酸化炭素排出量増加リスク
- カーボンニュートラルへの逆行と国際的批判の恐れ
など、多くの問題が考えられます。特に、2035年以降のガソリン車販売禁止を目指すという政策と、ガソリン補助は明らかに矛盾している気がします。
先日、環境省の若手官僚に匿名で話を聞く機会がありましたが、「省内でも賛否両論です。でも経済優先の流れには逆らえないのが現状ですね…」と複雑な表情を浮かべていました。
6. 海外事例と比較:日本だけが「定額補助」?
私は昨年、欧州の燃料政策について取材する機会がありました。各国の対応はさまざまです。
国名 補助の方式 特徴
フランス 燃料費の現金給付 低所得層向けのターゲット型
ドイツ 一時的に燃料税を引き下げ 一律だが時限的
アメリカ 各州ごとにガソリン税調整 民主・共和で対応に差あり
日本 一律10円の定額補助 ガソリン価格に関係なく一定額を支給
フランスのカフェで出会った現地ジャーナリストはこう言っていました。「日本の制度は珍しいですね。価格に関係なく一定額を補助するというのは、予算管理はしやすいかもしれませんが、本当に必要な人に届いているかどうかは疑問です」
確かに、日本の制度は「価格連動ではない定額方式」という点で独特です。これが良い方向に働くといいのですが…。
7. 中長期的に求められる視点とは?
正直に言って、このガソリン10円補助は、あくまで短期的な”応急処置”に過ぎないと思います。本質的な解決のためには、もっと踏み込んだ施策が必要なのではないでしょうか。
先日、エネルギー政策の専門家に話を聞きましたが、「みゆきさん、この問題の本質は、ガソリン依存型の社会構造そのものなんですよ」と指摘されました。
求められる政策転換として、
- 公共交通機関の利便性向上(地方の鉄道・バス整備)
- EVや再エネ車への買い替え支援策の強化
- 燃料税制の抜本的な見直し(環境税化など)
- “脱ガソリン”を前提としたエネルギー政策の再設計
などが考えられます。
個人的に地方取材で痛感するのは、「車がないと生活できない地域」と「環境配慮」のバランスの難しさです。田舎の親戚は「電気自動車なんて、充電どこでするの?」と首をかしげていました。都市部と地方の温度差も大きいのが現実です。
結論:助かるけど、続けるには工夫が必要
取材を進めるうちに、この定額補助に対する複雑な思いが膨らんできました。確かに、多くの国民にとって「ありがたい」と思える制度です。でも、それだけに終わらせてしまっては、日本のエネルギー政策は前に進みません。
北海道の小さな町で出会ったガソリンスタンド経営者の言葉が忘れられません。「10円安くなるのは嬉しいよ。でも、これからの時代、ガソリンだけに頼る商売じゃダメだって分かってるんだ。うちも充電スタンドの導入を検討してるよ」
結局のところ、私たち一人ひとりにとっての問いかけでもあるのかもしれません。
- この機会に「ガソリンを使いすぎない生活」へ移行できるか?
- 地方交通をどう守りながら、脱炭素へ進むか?
- 税のあり方を見直し、真に持続可能な制度に変えられるか?
10円の補助は確かに助かります。でも、それが日本のエネルギーと経済と環境の”未来”をどう描くのかを問う分岐点になることを、私たちは忘れてはいけないと思います。
(取材・文 みゆき)
トレンドを狙え今、話題の“泉”から情報が湧き出す!ニュース&トレンド特急便
ガソリン補助 #ガソリン価格 #定額補助制度 #生活支援策 #政府施策 #物価対策 #燃料高騰 #エネルギー政策







コメント