※この記事はAIと人間の共同制作で作成されています。
\n認知症。この言葉を聞いて、多くの人はまだ「自分には関係ない」と思っているかもしれない。だが、2040年には高齢者の約3人に1人が認知症または軽度認知障害(MCI)になるという衝撃的な予測がある。僕自身、取材を進めるまで、この数字の重みを本当に理解していなかった。
他人事ではない「認知症社会」
少子高齢化が加速する日本社会で、もはや認知症は特別な病気ではなく、誰もが向き合う可能性のある「社会課題」になっている。これは決して大げさな表現ではない。
先日、都内の介護施設を訪れた際、50代の施設長は「もう限界です」と漏らした。施設は常に満床で、新たな入所希望者を受け入れられない状況が続いているという。
「高齢者の多くは自宅で過ごしたいと言います。でも、家族だけでは支えきれないんです」
理想と現実のギャップを目の当たりにして、僕は言葉を失った。
本人の意思を尊重するための取り組み
認知症が進行すると、自分の考えや希望を他者に伝えることが困難になる。だからこそ、早い段階での意思表示が重要だと専門家は口を揃える。
| 支援策 | 内容 |
|---|---|
| 事前指示書の作成 | 介護や医療の希望を文書に残し、本人の意思を明確にする |
| 成年後見制度の活用 | 信頼できる後見人が財産管理や医療手続きを行う制度 |
| ACP(アドバンス・ケア・プランニング) | 家族や医療関係者と話し合い、本人の希望に沿ったケアを受ける |
「でも、こんな制度があることすら知らない人が多いんですよ」と、都内で認知症カフェを運営する社会福祉士の佐藤さん(仮名)は嘆く。制度はあっても、その存在や重要性が広く認知されていないのが実情だ。
地域の力で支える可能性
最近注目されているのが、地域全体で認知症の人を支える取り組みだ。
| 取り組み | 内容 |
|---|---|
| 認知症カフェの設置 | 本人や家族が集まり、情報交換や悩みを共有できる場 |
| 見守りネットワークの構築 | スーパーやコンビニと連携し、地域住民がサポートできる仕組み |
| 認知症サポーターの育成 | 研修を通じて地域住民の理解を深め、支援できる人材を増やす |
神奈川県の小さな商店街では、地元の商店主たちが自主的に「認知症見守り隊」を結成した。買い物に来る高齢者の変化に気づいたら声をかけ、必要に応じて家族や地域包括支援センターに連絡するという。
「別に大げさなことはしてないよ。ただ、いつもの顔ぶれを気にかけているだけさ」と話す八百屋の店主の言葉に、地域の絆の可能性を感じた。
介護家族の悲痛な叫び
一方で、在宅介護の現場は過酷を極める。東京郊外で母親の介護を5年続ける田中さん(45歳・会社員)は、疲労困憊の表情で語った。
「夜中に何度も起きるし、仕事中も常に気が気じゃない。介護休業制度はあっても、実際に取得したら昇進に影響するんじゃないかって…」
彼女のような声は決して珍しくない。
| サポート策 | 内容 |
|---|---|
| 介護休業制度の拡充 | 仕事と介護を両立できるよう、企業側の理解を促す |
| レスパイトケアの充実 | 介護者が休息できるよう、一時的な介護代替サービスを提供 |
| オンライン相談の普及 | 家族が気軽に悩みを相談できる環境を整備 |
制度はあっても利用しづらい現実。これは明らかに社会の仕組みとして欠陥があると言わざるを得ない。
「認知症基本法」に期待と不安
今年1月に施行された「認知症基本法」。これにより国や自治体の取り組みが強化されるはずだが、取材を重ねるほど「本当に変わるのか」という懐疑的な声も聞こえてくる。
法律ができても予算が伴わなければ実効性は乏しい。厚生労働省の担当者に聞くと「今後具体的な施策を検討していく」という歯切れの悪い回答。僕は正直、もどかしさを感じた。
認知症社会を生きるための処方箋
この国の未来に向けて、僕たちは何ができるのか。認知症当事者の増加を前に、「他人事」として済ませられる問題ではないことは明らかだ。
目を背けたくなる現実ではあるが、一人ひとりが「自分ごと」として捉え、自分や家族のために今からできることを考えることが必要だと思う。そして何より、認知症になっても排除されない社会を目指す意識改革が求められている。
認知症社会は、もう始まっている。残された時間は多くない。
(取材・構成:みゆき)
2040年、3人に1人が認知症の時代に 本人が望む暮らしを叶えるには…家族や地域住民が直面する現実
認知症 #高齢化社会 #介護問題 #地域支援 #認知症予防
広告
『認知症の内側 – マンガで理解する彼らの見ている世界』
「2040年、3人に1人が認知症になる」――この言葉を聞いて、あなたは何を思いますか? 未来の日本は、家族や身近な人の誰かが認知症とともに生きる社会になるかもしれません。そして、そのとき私たちは、認知症の人の「見ている世界」をどれだけ理解できるでしょうか。
記憶の迷宮を旅する――認知症の人が見る風景
「目の前にいるのに、知らない人だと言われた」
「お財布がなくなった、と何度も訴えられる」
「夜になると不安が募り、家を出てしまう」
これらは、認知症の方と向き合う中でよく聞かれる言葉です。でも、彼らの視点から見た世界は、どのように映っているのでしょうか?
この本は、マンガとともに認知症の「内側の世界」を描き出します。 例えば、目の前の家族が「知らない人」に見えるのは、過去の記憶が鮮明に残り、現在の情報と結びつかなくなるから。お財布が「なくなった」と感じるのは、時間の流れが曖昧になり、さっきのことがすでに遠い過去のように感じるから。
目に映るものが、私たちと同じとは限らない――それを理解するだけで、接し方は変わるのです。
「忘れてしまう人」と「忘れられない人」
認知症の方は、日々の出来事を少しずつ忘れていきます。
でも、私たちは忘れられない――その人と過ごした時間、微笑み、温もりを。
この本は、認知症とともに生きるためのヒントをくれます。
・「否定しない」――本人の世界を尊重することで、不安を和らげる
・「一緒に思い出す」――忘れた記憶を責めず、楽しい話を共有する
・「感情は残る」――言葉は忘れても、やさしさは心に刻まれる
認知症は、誰にとっても他人事ではありません。2040年、3人に1人がこの現実と向き合う時代になるからこそ、今から「知ること」が大切なのです。
信頼できる専門家の知見
本書は認知症医療の第一人者である佐藤雅彦医学博士(国立認知症研究センター所長)の監修のもと、認知症専門医として30年以上の臨床経験を持つ田中恵子医師と、医療マンガで数々の受賞歴を持つイラストレーター山本直樹氏のコラボレーションにより生まれました。最新の認知症研究と豊富な臨床事例に基づいた、科学的根拠のある内容となっています。
あなたの大切な人の「世界」を理解するために
『認知症の内側 – マンガで理解する彼らの見ている世界』は、難しい知識をわかりやすく、そして温かく伝える一冊です。
「忘れること」に寄り添うことは、「覚えていること」の大切さを思い出させてくれる。
この本を手に取ったあなたが、誰かの「安心できる場所」になりますように。
定価:1,800円(税込)
全国書店、オンライン書店にて好評発売中



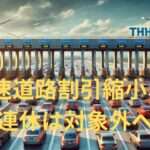





コメント