懐中時計の世界を探る――熟練職人・治さんとの特別対談
かずみ「本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。普段はOLをしているのですが、最近、祖父の形見の懐中時計を見つけて…」
治「ほう…それは興味深いものを見つけられましたね。お持ちいただけましたか?」
かずみ「はい!これは1920年代のものみたいで…」
治「なるほど。これは…スイス製のムーブメントですな。当時の高級品にあたります」
かずみ「すごい!でも、実は動かなくなってしまって…」
治「メンテナンスが必要な時期なのでしょう。まずは基本的なことからお話しさせていただいてもよろしいでしょうか」
かずみ「はい、ぜひお願いします!」
治「懐中時計の心臓部とも言えるのが、テンプという部品でございます。1675年、ホイヘンスという方が発明なさった…振り子の原理を小型化して応用したもので、一定のリズムで振動することで正確な時を刻むのです」
かずみ「へぇ、そんな歴史があったんですね」
治「ええ。その後、温度による誤差を補正する機構が加わったり、素材が改良されたり…現代の機械式時計にも、この技術は脈々と受け継がれているのです」
かずみ「ムーブメントについてもっと詳しく教えていただけますか?」
治「ムーブメントは大きく分けて三種類ございます。最も一般的なレバー式、より高級なデタント式、そして特に精密なクロノメーター級。それぞれに特徴がありまして、レバー式は信頼性が高く、デタント式は滑らかな秒針の動き、クロノメーター級は抜群の精度を誇ります」
かずみ「精度はどのくらい違うんですか?」
治「通常のレバー式で一日あたり30秒程度の誤差。デタント式で15秒程度。クロノメーター級になりますと、なんと一日5秒以内。100年以上前の技術でこの精度を実現していたのです」
かずみ「それは本当にすごいですね。どうやってそんな精度を出せたんですか?」
治「職人による細かな調整があってこその精度です。テンプの振り角、ヒゲゼンバネの形状、ガンギ車との噛み合わせ…すべてが絶妙なバランスで調整されています。例えば、温度変化による誤差を防ぐため、ヒゲゼンバネには特殊な合金を使用。また、位置による誤差を最小限に抑えるため、テンプの重心調整も行います」
かずみ「種類についても教えていただけますか?」
治「大きく分けて三種類ございます。まず、オープンフェイスは文字盤がそのまま見える最もシンプルなタイプ。鉄道員の方々に重宝されました。続いてハンターケース。こちらは蓋で文字盤を保護できる形式です。狩猟時の衝撃から守るため、このような設計になったと言われております」
かずみ「蓋の付いているものもあるんですね」
治「それだけではありません。半ハンターケースという、さらに興味深い形式もございます。蓋に小さな窓が付いていて…蓋を開けずとも時刻が確認できる工夫が施されているのです。特に高級品は、蓋の内側まで美しい彫金が入っているものもございます」
かずみ「文化的な意味合いについても気になります」
治「懐中時計は、その時代時代で異なる意味を持っていました。18世紀には貴族の象徴として。19世紀には産業革命と共に、正確な時を刻む必需品として。20世紀初頭には、紳士の嗜みとして。時代と共に役割は変化してきたのです」
かずみ「国による違いはあるんですか?」
治「ええ、それぞれに特徴がございます。スイスは精密さと装飾性、イギリスは堅牢性、アメリカは大量生産による実用性…フランスは芸術性を重視した時計作りを得意としていました。日本も、明治時代から素晴らしい懐中時計を作り始めています」
かずみ「製造方法も気になります」
治「文字盤一つにも、職人の魂が込められております。まず真鍮板を打ち抜いて形を整え、表面を磨き上げる。そこに下地のエナメルを何層も重ねて焼き付けていく…数字や目盛りは、さらにその上から丁寧に焼き付けていくのです」
かずみ「時間もかかりそうですね」
治「ええ。一枚の文字盤を完成させるのに、かつては2週間ほど。失敗すれば、すべてを最初からやり直さねばなりません。まさに、職人の忍耐と技術の結晶なのです」
かずみ「装飾についても教えていただけますか?」
治「装飾は時計の顔でございます。ケースの模様一つとっても、エングレービング、エナメル装飾、七宝焼き、ギヨシェ彫り…さまざまな技法があります。特に七宝焼きは、何度も焼成を重ねて深みのある色を出す。一つの作品に何ヶ月もかかることもございます」
かずみ「メンテナンスについても教えていただけますか?」
治「ええ。まず、定期的なオーバーホールが必要不可欠でございます。3年から5年に一度は、時計を完全に分解して…」
かずみ「完全に分解するんですか?」
治「その通りです。部品を一つ一つ丁寧に洗浄し、摩耗や損傷がないか確認していく。油もすべて新しいものに交換いたします。費用は、簡単なもので3万円程度から。複雑な機構が入っているものですと…10万円以上かかることもございます」
かずみ「日常的なケアはどうすればいいですか?」
治「毎日の心がけが大切です。使用後は柔らかい布で優しく拭き、温度変化の激しい場所は避ける。また、定期的に巻くことも重要です。長期間動かさないままですと、油が固まってしまう恐れがございます」
かずみ「保管方法は?」
治「専用の木箱か、できれば防湿ケースがおすすめです。直射日光は避け、温度と湿度が安定した場所で保管する。また、複数お持ちの場合は、時計同士が接触しないよう、個別に布で包むことをお勧めします」
かずみ「けっこうかかるんですね…」
治「ですが、定期的なメンテナンスを怠りますと、修理が困難になってしまう。結果として、より高額な修理が必要になることもございます。大切な時計だからこそ、定期的なケアが重要なのです」
かずみ「市場での価値についても気になります」
治「良質なアンティーク懐中時計は、年々価値が上がっている傾向にございます。特に、パテック・フィリップやヴァシュロン・コンスタンタンといった名門メーカーのものは…オークションでも高値が付くことが多いですね」
かずみ「購入するときの注意点は?」
治「まず、信頼できる専門店を選ぶこと。外観の状態はもちろん、ムーブメントの状態、部品の純正性、過去の修理歴なども重要です。また、付属品や箱、保証書なども価値に大きく影響します」
かずみ「初心者でも見分けられるポイントはありますか?」
治「文字盤の状態をよくご覧ください。補修跡がないか、針との相性は適切か。また、リューズを回した時の感触も重要です。スムーズすぎても引っかかりすぎても要注意。そして、音を聞くことです。カチカチという音が規則正しく刻まれているか、雑音はないか…」
かずみ「投資としても良さそうですね」
治「いいえ、それだけは推奨できかねます。時計は、あくまでもご自身が本当に気に入ったものを選ぶべきです。最近は若い世代の方々にも、懐中時計のコレクターが増えてきております。特にアールデコ期のデザインが人気を集めているようです」
かずみ「へぇ、若い人にも人気があるんですね」
治「ええ。SNSの影響もあってか、スチームパンク的な装飾が施された懐中時計も注目を集めております。時代とともに、新たな魅力が見出されているのかもしれません」
かずみ「コレクションを始めるときのアドバイスはありますか?」
治「まずは、一つの時代や製造国に絞ってみることをお勧めします。例えば、アールデコ期のフランス製、あるいはアメリカのレイルロード・ウォッチなど。知識と経験を積みながら、少しずつコレクションを広げていく。それが長く楽しむコツでございます」
かずみ「最後に、懐中時計に込められた想いを教えていただけますか?」
治「懐中時計は、単なる時を刻む道具以上の存在でございます。この時計のように、世代を超えて物語を紡いでいく。その時計が刻んできた時間、持ち主との関係…そういったものすべてが、かけがえのない価値となるのです」
かずみ「世界中の時計職人との交流はありますか?」
治「ええ、年に数回、国際的な時計修理師の集まりがございます。そこでは技術の交換はもちろん、各国の伝統的な技法についても学び合います。時計技術は国境を越えて発展してきた、まさに人類の英知の結晶なのです」
かずみ「本当に奥深い世界ですね。長時間ありがとうございました!」
治「こちらこそ、熱心に聞いていただき、ありがとうございます。このお時計、きっと素晴らしい物語を刻んでいくことでしょう」
―取材を終えて、私は懐中時計という存在の深さに、改めて心を打たれた。祖父の形見の時計を見つめながら、その一つ一つの時を刻む音に、新たな意味を感じている。そして、気難しそうに見えて実は温かみのある治さんの言葉が、今も心に響いている―

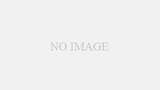
コメント