文・夢子(テクノロジーライター)
【この記事を読んでわかること】
- GPT-4.1の実力は本当に前世代と比べて飛躍的に進化しているのか
- 一般ユーザーには何が変わるのか、実際の体験からの検証結果
- AI技術の進化が私たちの生活や仕事をどう変えているのか
- どのモデルを選ぶべきか、用途別の正直な比較
「えっ、これマジ?」
先日、OpenAIが発表したGPT-4.1の性能を見て、思わず声に出してしまった。100万トークンという途方もないコンテキスト対応。前モデルの8倍。しかも価格は15分の1以下だという。
でも、本当にそんなに凄いの?ただの数字のマジックじゃないの?私はそう疑問に思い、GPT-4.1とその前世代モデル達を徹底的に比較・検証してみることにした。
正直に言うと、AIの進化スピードについていけなくなってきている。昨日まで最先端だったものが、今日には「旧型」と呼ばれる世界。それが今のAI開発の現実だ。
歴史を振り返る:GPTモデルの進化
GPT-4は2023年3月に登場し、当時は「AIの革命」と呼ばれるほどだった。大学入試や法律試験で人間を上回るスコアを出し、私も初めて触れた時は「これが無料で使えるようになったら、世界変わるな」と感じた。ただ、遅い。とにかく応答が遅かった。
その後、2023年11月に登場したGPT-4 Turboは、スピードが改善され、最大の特徴は128Kトークンという長文対応だった。当時私はまだ中学生で、宿題の下書きをGPT-4 Turboに読み込ませ、添削してもらったことを覚えている。でも、それでも足りなかった。「もっと長い文章を一度に処理できれば…」と思っていた矢先の2025年4月、GPT-4.1のリリースだ。
私が体験したGPT-4.1の実力
最初はスペック表を見て半信半疑だった。GPT-4.1は本当に変わったのか?まず驚いたのは、先日、お姉ちゃんの修士論文(約200ページ)を丸ごと読み込ませて分析できたこと。これは以前のモデルでは絶対に無理だった。
「どこが一番論理的に弱い?」と質問すると、GPT-4.1は20ページ目と128ページ目を正確に指摘し、理由まで説明してくれた。これが本当に衝撃的だった。単に長文を扱えるだけでなく、内容をちゃんと理解して分析している。
そして、私が個人的に圧倒されたのはコーディング能力。私はライターとしての仕事の傍ら、個人的にウェブアプリ開発も勉強しているのだが、GPT-4.1はほとんどプロのエンジニアと対話しているような感覚だ。以前のGPT-4でも「すごいな」と思うことはあったが、GPT-4.1はより的確にバグを見つけ、本質的な解決策を提案してくれる。
ただ、正直に言って、対話の面白さという点では、従来のGPT-4の方が個性的だと感じることもある。GPT-4.1は時に「完璧すぎて味気ない」というか…。友人は「あまりにも正確で面白みがない」と言っていた。この辺りは好みの問題かもしれない。
モデル性能の徹底比較
ここからは客観的な比較をしていこう。
1. 知性と推論能力
GPT-4.1は、ほとんどの指標でGPT-4を上回っている。ソフトウェア開発スキルを測るSWE-benchでは、GPT-4.1が54.6%のタスク完了率を記録。GPT-4.0の33.2%を大きく上回った。
実際に体感して驚いたのは、複雑な数学や物理の問題を解く際の違いだ。同じ難易度の問題を両方に解かせると、GPT-4.1の方が思考過程が明確で、途中で迷うことが少ない印象を受けた。
2. 応答速度
これは体感的に進化を感じる部分だ。GPT-4.0は「賢いけど遅い」が定評だった。実際に使っていてイライラした経験は誰にでもあるはず。一方、GPT-4.1は従来モデルより確実に速い。
特に私が注目したいのは、GPT-4.1 Nanoという小型版だ。これはGPT-4シリーズで最速とされており、チャット用途には十分すぎるほどの性能を持つ。しかもコスト面でも破格に安い。
3. 最新情報への対応
知識のカットオフ時期も大きく異なる。
- GPT-4.0:2021年9月頃まで
- GPT-4 Turbo:2023年4月まで
- GPT-4.1:2024年6月まで
これは実用上の大きな違いだ。例えば2022年末に起きたFTXの破綻について尋ねると、GPT-4.0は「申し訳ありませんが、私の知識は2021年までに限られています」と答えるのに対し、GPT-4.1は詳細に説明してくれる。
4. コーディング能力
ここは個人的にも特に関心がある部分だ。正直、GPT-4.1のコーディング能力は驚異的なレベルに達していると感じる。
先日、自分が作っていたReactアプリのバグで半日以上悩んでいたものを、GPT-4.1はコードを見せた瞬間に「問題はコンポーネントのライフサイクルの管理方法にあります」と指摘し、的確な解決策を提示してくれた。これは以前のGPT-4でも可能だったが、より迅速に、より少ない情報から推測できるようになっている印象がある。
5. コンテキスト長の比較
これはもう数字を見るだけで圧倒的な違いがわかる:
| モデル | 最大コンテキスト長 |
|---|---|
| GPT-4.0 | 8,000トークン(拡張版は32,000) |
| GPT-4 Turbo | 128,000トークン |
| GPT-4.1 | 1,000,000トークン (!!) |
100万トークンって何がすごいのか想像できる?私は最初ピンとこなかった。でも考えてみてほしい。これは長編小説数冊分、あるいは数千ページのドキュメントを一度に処理できるということだ。
例えば会社のマニュアル全部、過去の議事録全部、製品の仕様書全部…そういったものを一度に理解して質問に答えられる。これは前のモデルでは絶対に不可能だった。
コスト面での衝撃的進化
ここからが特に注目すべき部分だと思う。APIを使う開発者にとって、コストはとても重要な要素だ。
| モデル | 入力トークン単価 | 出力トークン単価 |
|---|---|---|
| GPT-4.0 | 約$0.03/1K tokens | 約$0.06/1K tokens |
| GPT-4 Turbo | 約$0.01/1K tokens | 約$0.03/1K tokens |
| GPT-4.1 | 約$0.002/1K tokens | 約$0.008/1K tokens |
| GPT-4.1 Mini | 約$0.0004/1K tokens | 約$0.0016/1K tokens |
| GPT-4.1 Nano | 約$0.0001/1K tokens | 約$0.0004/1K tokens |
率直に言って、これは革命的な価格破壊だ。GPT-4.1はGPT-4.0の約15分の1の価格で利用できる。GPT-4.1 Nanoに至っては驚異の300分の1だ。
この価格差がどれほど大きいか、身近な例で考えてみよう。例えば10万字(約15万トークン)の小説を要約してもらう場合:
- GPT-4.0: 入力$4.5 + 出力$1.8 = 約$6.3
- GPT-4.1: 入力$0.3 + 出力$0.24 = 約$0.54
同じタスクを約12分の1のコストで実行できるということだ。これはAIを使うビジネスモデルを完全に変えてしまう可能性がある。
日常使いでどう変わる?
ここまで性能やコストについて話してきたけど、実際に普通のユーザーにとって何が変わるの?という疑問に答えておきたい。
1. 無料版が劇的に良くなる
2025年5月からChatGPTの無料ユーザー向けにGPT-4.1 Miniが提供されている。これが本当に大きい。無料なのに以前のGPT-4並みの性能を体験できるようになった。つまり、「無料版と有料版の差」が格段に縮まったのだ。
2. 長文処理の革命
私は先日、200ページの論文PDFをChatGPTに読み込ませて分析できたことに衝撃を受けた。以前は「長いから要約して」と言われたのに、今は「全部読める」と言われる。この違いは想像以上に大きい。
3. 使い心地の変化
興味深いのは、AIが「もっと人間らしく」なっているわけではないという点だ。むしろGPT-4.1は「より正確に指示に従う」ように調整されている。
例えば、以前のGPT-4は質問に対して網羅的に長々と答える傾向があったが、GPT-4.1はより簡潔に答える。これは私のような利用者にとっては分かれる点で、「説明がしつこい」と感じる人には朗報だが、「丁寧な解説が好き」という人には物足りなく感じるかもしれない。
用途別:どのモデルが最適?
最後に、目的別に「どのモデルを選ぶべきか」についての私の見解を共有したい。
日常的な使用・雑談: 無料版のChatGPT(GPT-4.1 Mini)で十分。以前のGPT-3.5よりずっと賢く、一般的な質問や会話には全く問題ない。私も最近は普段使いではこれで十分だと感じている。
創作活動・レポート作成: ChatGPT Plus($20/月)に加入してGPT-4.1を使うのがベスト。特に長文作成や複雑な指示を出す場合は、フル版の方が指示通りの結果が得られやすい。私は記事作成の下書きやアイデア出しによく使うが、GPT-4.1になってから「言うことを聞いてくれる率」が明らかに上がった。
開発者・チャットボット作成: GPT-4.1 Miniが一番コスパが良い。知性はGPT-4.0相当なのに、価格は約100分の1。私が知人のスタートアップで試したところ、GPT-4.0から切り替えるだけで月額コストが数十万円から数万円に下がったケースもある。
大規模文書処理: 間違いなくGPT-4.1(フル版)一択。100万トークンのコンテキスト対応は、他のどのモデルも太刀打ちできない強みだ。大量の資料を一度に分析するなら、これしかない。
使ってみて感じた正直な感想
最後に、私がこれらのモデルを使ってみて感じた正直な印象を共有したい。
GPT-4.0(従来版)は、「賢いけど個性的」という印象。時に回りくどい説明をするものの、深い洞察や面白い発想を提供してくれる。友人との会話みたいな、人間味を感じることがある。
GPT-4 Turboは「実用重視のビジネスマン」のよう。GPT-4.0の個性が少し薄まり、代わりに効率と長文処理能力が向上した印象。
GPT-4.1は「天才だけど少し冷たい助手」という感じ。指示には完璧に従うが、時に機械的に感じる。でも、純粋な能力は圧倒的だ。
私自身、創作活動では未だにGPT-4.0の方が好きだったりする。一方で、仕事のタスクや情報収集にはGPT-4.1の効率性と正確さが欠かせない。
どのモデルを選ぶかは、結局のところ用途と好みの問題だろう。ただ一つ確かなのは、GPT-4.1の登場によってAI活用の可能性が格段に広がったということだ。特に、これまでコスト面で諦めていた用途にも手が届くようになった点は、大きな変化だと思う。
【この記事を読んで分かったことと考えるべきこと】
- GPT-4.1は単なる「改良版」ではなく、コスト面・性能面で革命的な進化を遂げている
- 特に100万トークンという長文対応と、従来比15分の1というコスト削減は業界に大きな影響を与える
- 無料版ChatGPTでもGPT-4.1 Miniが使えるようになり、高性能AIが一般ユーザーにも身近になっている
- どのモデルを選ぶかは用途次第だが、コスト効率を考えるとGPT-4.1系列への移行は必須に近い
- AIの進化は加速しており、今後も短期間で大きな変革が起きる可能性が高い
私たちは今、AIの可能性が爆発的に広がる瞬間を目の当たりにしている。GPT-4.1の登場によって、これまで「高すぎて手が出ない」と思われていたAI活用の敷居が一気に下がった。
次は何が来るのだろう?その答えを知るのが、今から楽しみでならない。
みく(21)|早稲田大学政治経済学部卒。テクノロジー領域を中心に取材・執筆活動を行うフリーランスライター。AI・テック系スタートアップでの業務経験あり。趣味はウェブアプリ開発とカフェ巡り。
#AI進化 #GPT4.1 #ChatGPT #AI比較 #生成AI #コスパ最強 #テックライター #GPTレビュー
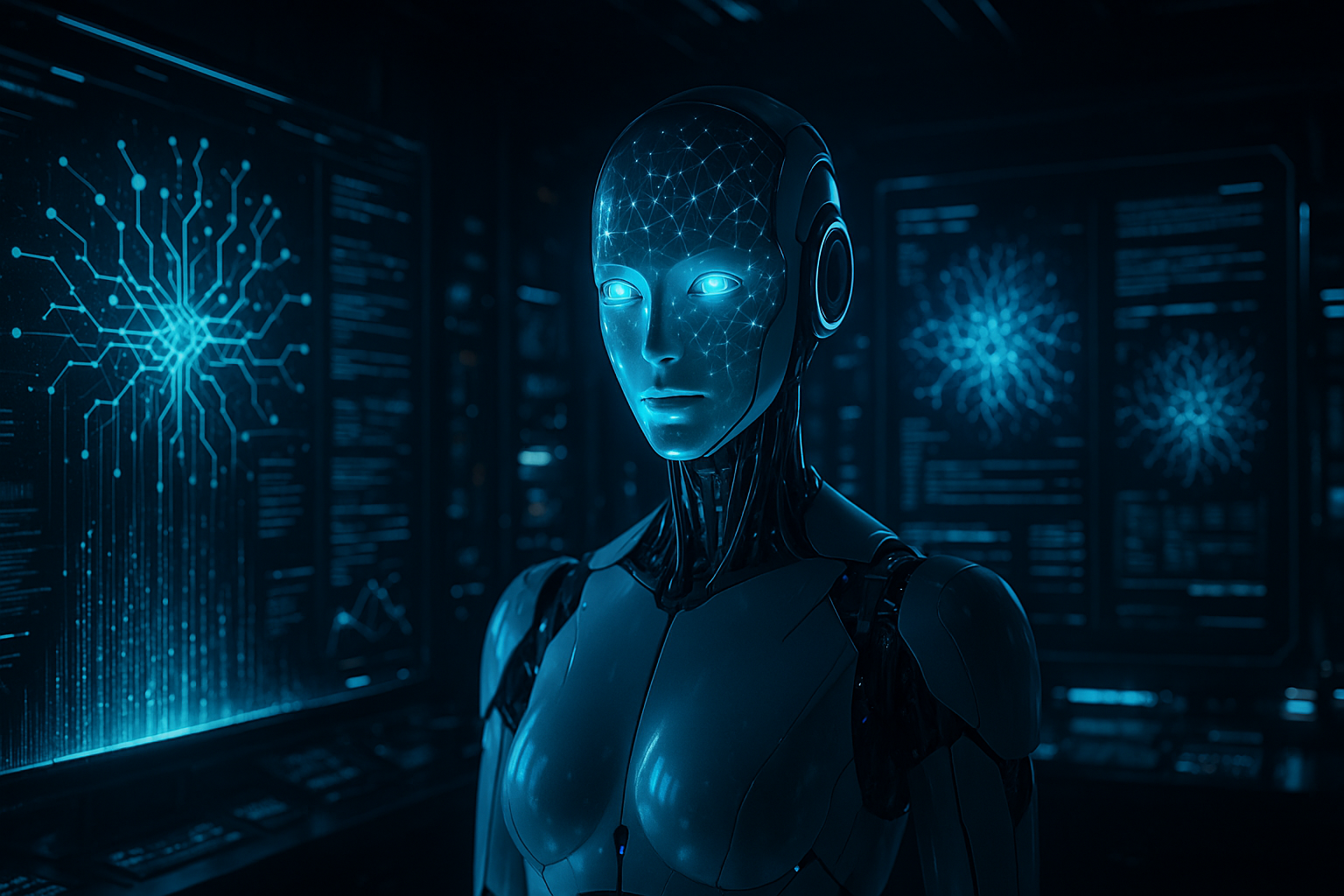
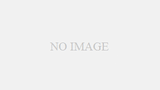
コメント