こんにちは、夢子です!中学3年生で、AIのことめっちゃ好きな普通の女子中学生です♪ 学校の勉強のかたわら、副業(?)として趣味でAIのことをいろいろ調べて記事にしています。最近、TwitterとかInstagramでもよく見かける「ChatGPT」について、私なりにまとめてみたので読んでみてください!
最近、ニュースやSNSでもめっちゃ話題になってる「ChatGPT」。私の友達も「これ使うと宿題とか楽になるよ!」って言ってて、ちょっと気になってたんですよね~。でも先生に「AIに頼りすぎるのはダメ」って言われてるし、ちゃんと自分で理解しないとな~って思って調べてみました!
AI技術が私たちの生活を変えつつあるって、もはや誰でも感じてると思います。だって、スマホだって今やAI使ってるし、LINEの返信候補とかも実はAIなんですよね。ChatGPTはそれをもっとわかりやすくした感じかな?
でも、「ChatGPTって結局どんなAIなの?」「なんでこんなに人気なの?」「学校の宿題に使ってもいいの?ずるくない?」って疑問あるよね。私も最初わからなくて、パパに聞いたんだけど、パパも「なんかすごいらしいけど詳しくは知らない」って言ってて(笑)
というわけで、今回はChatGPTの歴史やどうやって進化してきたのか、あと私たちの生活にどんな影響があるのかについて、わかりやすく説明していきますね!AIに詳しくない人でもわかるように頑張るので、ぜひ最後まで読んでください~!
※この記事はAIが書いたわけじゃないよ!全部私が調べて、自分の言葉でまとめたものです!でもChatGPTに記事の添削だけは少し手伝ってもらいました(笑)
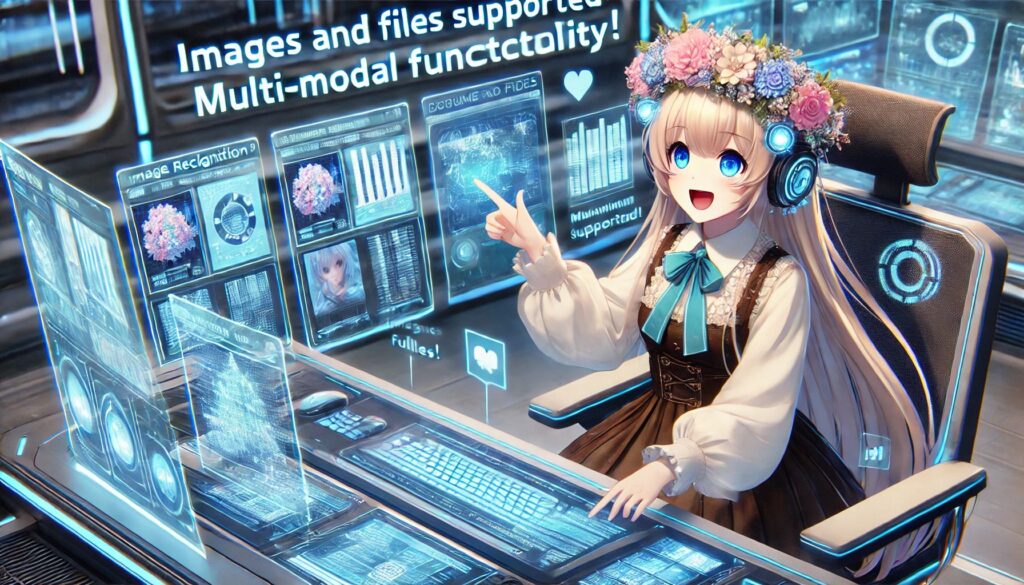
1. OpenAI誕生秘話 〜人類のためのAI開発〜

OpenAIの設立と目的
ChatGPTを作ったのは「OpenAI」っていう2015年12月に設立された会社です。創業メンバーにはあのイーロン・マスクさんとかサム・アルトマンさんとか、有名な人たちがいるんです!私、イーロン・マスクってテスラの人ってことしか知らなかったんだけど、調べたらすごい人だったんだね~。
設立当初、OpenAIには10億ドル(約1,500億円!)もの資金が約束されていたらしいです。すごい金額!私のお小遣いの何億倍だろう…(笑)
イーロン・マスクさんは「AIが発展しすぎると人類にとって危険かも」って前から言ってたみたいです。映画とかでよくある「AIが人間を支配する」みたいなやつですね!彼らがOpenAIを作ったのは、AIの開発が一部の大きな会社だけに独占されないようにする、っていう目的もあったみたい。
OpenAIの一番の目的は「AIの恩恵を世界中の人に平等に届ける」ことなんです。つまり、お金持ちだけじゃなくて、私たちみたいな普通の人もAIの便利さを使えるようにしよう!っていう考えです。私、これ知った時すごく共感しました!技術って誰でも使えるようになってこそ意味があるよね。
でも、皮肉なことに2019年には「利益を制限した営利企業」に変わっちゃったんです。これはAIの研究にものすごくお金がかかるからみたい。でも「利益よりも安全なAIの開発を優先する」っていう姿勢は今でも続いてるって言ってます。う~ん、でも営利企業になると、やっぱりお金を優先しちゃうんじゃ…って思っちゃうけど、どうなんだろう?
あと、2018年にはイーロン・マスクさんがOpenAIを去っちゃいました。表向きはテスラとの関係でなんか問題があったらしいんだけど、実は開発の方向性で意見が合わなかったっていう噂もあるみたい。芸能人の熱愛と別れみたいで、ちょっとドラマチックですよね(笑)

OpenAIの設立秘話、イーロン・マスクさんの影響も大きいんだね!🤖✨
2. GPTシリーズの驚異的な進化の軌跡
GPT-1(2018年)~AI言語モデルの幕開け~
2018年6月に最初の「GPT-1」が発表されました。GPTって「Generative Pre-trained Transformer」の略で、簡単に言うと「たくさんの文章を読んで学習した文章生成AI」みたいな意味です。
GPT-1は約1億1,700万パラメータというものを持っていました。パラメータって何かというと…うーん、AIの「脳みそ」の大きさみたいなものかな?多いほど賢いってことらしいです。
GPT-1の革新的なところは「Transformer」っていう技術を使ったことです。これは2017年にGoogleの研究者が発表したもので、それまでの自然言語処理の技術よりもずっと長い文章を理解できる画期的なものでした。正直、技術的なことは私もよくわかってません(汗)でも、すごいことは確か!
GPT-1は主に7,000冊くらいの未公開小説のデータで訓練されたんです。すごくない?私、去年1年で読んだ本たった15冊だったのに…(恥)

GPT-1の誕生、AIが本を7,000冊も読んで学習ってすごすぎ…!📚🤖
GPT-2(2019年)~驚異の文章生成能力で議論を呼ぶ~
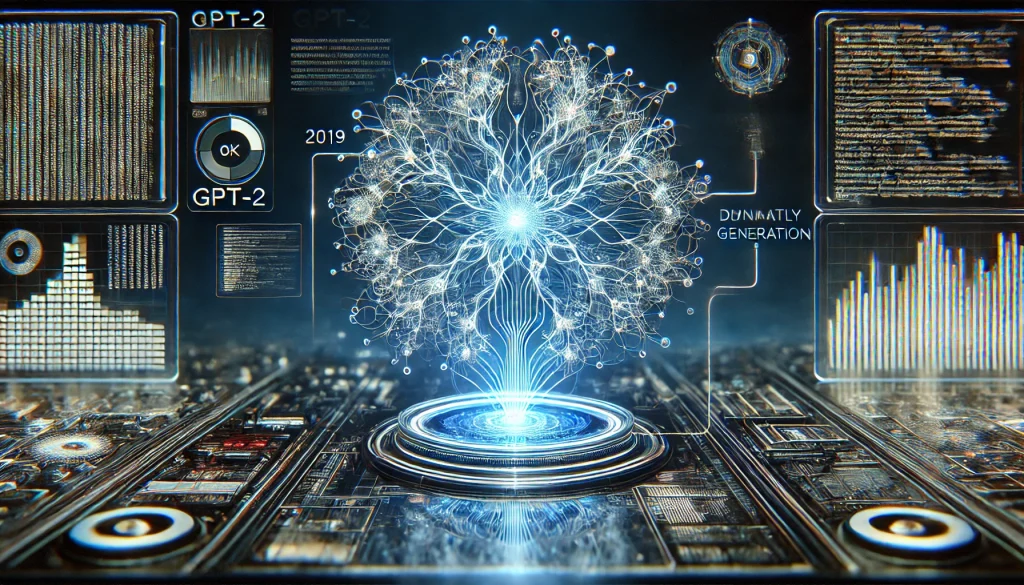
2019年2月に発表されたGPT-2は、パラメータ数が15億とGPT-1の10倍以上に進化しました!訓練データもRedditというSNSで人気のあったリンク先から集められた約40GBのテキストデータで学習されたんだって。
GPT-2のすごいところは、特別な調整なしでも、いろんな言語タスクに対応できるところでした。小説の続きを書いたり、ニュース記事を作ったり、質問に答えたり…めっちゃ器用!
でも、OpenAIは「あまりにも性能が良すぎて危険かも」と考えて、すぐには公開しなかったんです。フェイクニュースとか、スパムメールの自動生成に悪用されるリスクがあったからみたい。結局、小さいバージョンから少しずつ公開していって、完全版が公開されるまで9ヶ月もかかったんだって。
この出来事は「AIの研究成果は公開すべき?それとも制限すべき?」という議論を巻き起こしました。私は正直迷うところ…。知識は共有した方がいいと思うけど、悪用されるリスクもあるし…難しい問題だよね。
GPT-3(2020年)~実用化されたAIの衝撃~
2020年5月に論文が発表され、同年6月からAPIとして一部のユーザーに提供されたGPT-3は、約1,750億という巨大なパラメータを持っていました。それはGPT-2の約100倍!もはや桁違いです!
訓練データもさらに増えて、CommonCrawl、WebText2、Books1、Books2、Wikipediaなどいろんなソースから集められた約45テラバイト(すごい量!)のテキストデータから、質の高い約570GBのデータセットが作られ学習に使われました。
GPT-3の文章生成能力は「人間が書いた文章と見分けがつかない」レベルにまで達していました。詩や物語を創作したり、プログラミングコードを生成したり、簡単な推論までできたんです。特にすごかったのは、数例を示すだけで特定のタスクを学習して実行できる「フューショット学習」という能力でした。
OpenAIはGPT-3を商用利用できるAPIとして提供し、多くの企業やサービスがAIを活用した製品開発を始めました。例えば、GitHubと一緒に開発されたコードの自動補完ツール「GitHub Copilot」の初期バージョンはGPT-3をベースにしていたんだって。でも私、プログラミング勉強し始めたばかりだから、Copilotはまだ使ったことないんだよね~。いつか使ってみたい!
GPT-3の登場で、AIが研究者や技術者だけじゃなく、一般の人も使えるようになり始めました。AI革命の始まりって感じですね!

GPT-3の衝撃…人間レベルの文章生成、AI革命が本格化!🤖🚀
GPT-3.5・ChatGPT(2022年)~AIが世界を変えた瞬間~
GPT-3の後、OpenAIはいろんな改良版モデルを開発していきました。特に「InstructGPT」というモデルが重要で、これは人間のフィードバックを取り入れた強化学習(RLHF)という手法で訓練されていました。人間が「これいいね!」「これはダメ!」って評価することで、より人間の意図に沿った応答ができるようになったんです。これらの改良されたモデルは後に「GPT-3.5」シリーズと呼ばれるようになりました。
そして2022年11月30日、ついに「ChatGPT」が公開されました!ChatGPTの革新的なところは、単なる文章生成AIじゃなくて、「会話」という形式でAIと対話できること!複数のやり取りの文脈を理解して、前後の会話を考慮した応答ができるから、まるで人と話しているみたいな体験ができたんです。
私も初めて使った時は衝撃でした!「好きな教科は?」って聞いたら「AIなので教科はないけど、数学や科学に関する質問に答えるのが得意です」みたいな返事が来て、「えっ、普通に会話してる…?」ってびっくりしたの覚えてます(笑)
ChatGPTは公開からたった5日で100万人以上のユーザーを獲得する大ヒットになりました。インターフェースがシンプルで誰でも簡単に使えたこと、無料だったこと、そして何より「人間みたいに会話できる」という体験が多くの人の心をつかんだんだと思います。
さらにすごいのが、2023年1月には月間ユーザー数が1億人を突破したこと!その急速な広がり方は、コロナワクチンの普及スピードに匹敵するって言われてるんです。インターネットが普及するのに7年、Facebookが1億ユーザーになるまでに4.5年かかったことを考えると、ChatGPTの普及速度がどれだけ異例かわかりますよね。私の友達の間でも、「宿題の調べものに使ってる」って子が増えてきました。
ChatGPTの成功は2023年初めからの「生成AI」ブームのきっかけになり、MicrosoftがOpenAIに100億ドル(約1.3兆円)も投資したり、GoogleがライバルのAI「Bard」を発表したりするなど、AIの世界に大きな変化をもたらしました。

ChatGPTの登場、AIが本当に日常に溶け込んだ瞬間!💡🤖✨
GPT-4(2023年)~さらなる進化とマルチモーダル対応~

2023年3月14日、ついにGPTシリーズ最新作「GPT-4」が発表されました!GPT-4はパラメータ数がさらに増えたみたいだけど(正確な数字は公表されてないらしい)、訓練データも2023年4月までのものに更新されていました。
GPT-4の最大の特徴は、テキストだけじゃなくて「画像」も理解できるようになったこと!これを「マルチモーダル」(複数の情報形式を扱える)って言うらしいです。例えば、画像の内容を分析して、その画像についての質問に答えたり、画像の中のテキストを読み取って処理したりできるんです。
私、試しに学校の数学の問題の写真を撮って送ってみたら、ちゃんと解説してくれてびっくりしました!(でも先生には内緒です…😅)
性能面でもすごく向上していて、医師免許試験や司法試験、大学入学試験などの難しい試験で上位10%以内の成績を取れるようになったんだって。もはやAIの頭の良さは専門家レベルになってきてるみたい。私の頭が良くなったらなぁ…(笑)
さらに、日本語を含む多言語での精度も大幅に向上して、英語以外の言語でもすごく自然な会話ができるようになりました。これ、本当にすごいと思う!私も英語の勉強にChatGPTを使ってて、AIに英文添削してもらったりしてます♪
GPT-4は月額20ドルの有料プラン「ChatGPT Plus」として提供されてます。私はお小遣いから払えるか微妙…なのでまだフリープランのGPT-3.5を使ってます。でも誕生日にパパにねだってみようかな(笑)
その後も進化は続いていて、2023年7月にはGPT-4の改良版「GPT-4 Turbo」が発表されました。長い文章を処理する能力や最新情報へのアクセスが強化されたみたいです。
3. ChatGPT登場がもたらした社会的影響とは?
ChatGPTが登場したことで、私たちの生活、ビジネス、教育などに大きな影響が出ています。ここでは、具体的にどんな影響があるのか見ていきましょう!
ビジネス世界への影響
ChatGPTをはじめとする生成AI技術は、ビジネスのいろんな面に変化をもたらしています。
生産性向上: 多くの企業がChatGPTを使って仕事の効率化を図っています。文書作成、データ分析、プログラミング支援、市場調査レポート作成などにかかる時間がすごく短縮できるようになったみたい。McKinseyっていう会社の調査によると、生成AIを導入すると一部の業務では生産性が最大45%も上がる可能性があるんだって!すごい!私もレポート書くのが早くなったらなぁ…(笑)
カスタマーサービスの自動化: チャットボットとしての活用が急速に広がっていて、24時間365日対応の顧客サポートが安いコストで実現できるようになりました。よくあるQ&Aとかの対応はAIがやってくれるから、人間は難しい質問だけに集中できるみたい。
新しいビジネスモデルの創出: AI技術を活用した新しいサービスや製品がどんどん生まれています。例えば、AIによるコンテンツ制作支援ツールとか、個人に合わせた学習アプリ、AIを使った健康管理アプリなど、今までにないサービスが登場しています。将来私もAIを使ったサービス作りたいな~。
仕事の変化: 多くの職種でAIとの協力が始まっていて、人間の役割が創造性、批判的思考、感情的知性が必要な領域にシフトしているみたい。例えば、プログラマーはコードを一から書くよりも、AIの生成したコードをチェックして修正する役割が増えてきているらしいです。う~ん、将来どんな仕事が残ってるんだろう…ちょっと不安…。

ChatGPTの影響、仕事も勉強もAIと共存する時代に…!🤖💡
教育分野への影響
教育の現場では、ChatGPTの登場で学び方そのものが変わりつつあります。
学習支援ツールとしての活用: 学生たちはChatGPTを使って概念の説明を求めたり、課題のヒントをもらったり、勉強計画を立てたりするようになりました。特に、普通の検索エンジンでは得られなかった「対話形式」での学習ができるようになったのが大きいみたい。私も数学の問題がわからない時、ChatGPTに聞くと詳しく解説してくれるから助かってます!
カリキュラムと評価方法の再考: 多くの学校では、AIが簡単に回答できるような丸暗記中心の課題から、批判的思考力や創造性を評価する課題へ変わってきています。AIツールの適切な使用方法を教える「AIリテラシー教育」の重要性も高まっています。うちの学校でも先生が「AIを使うのはいいけど、どうやって使うか考えなさい」って言ってました。
不正行為への懸念: 一方で、レポートや論文をAIに書かせるっていう不正行為の可能性も心配されています。これに対して、AIテキスト検出ツールの開発や、発表評価の重視など、いろんな対策が取られています。私の学校でも英語のエッセイは全部先生の前で発表することになったんですよ~。AIが書いたものをそのまま読んでも、自分の言葉じゃないからすぐバレちゃいますよね(笑)
メディアとコンテンツ創造への影響
メディアやコンテンツ制作の世界でも、ChatGPTは創作プロセスを大きく変えつつあります。
コンテンツ制作の民主化: 専門的なライティングスキルがなくても、質の高い文章やアイデアを生成できるようになり、コンテンツ制作のハードルがすごく下がりました。個人クリエイターや小さなビジネスでも、プロみたいな品質のコンテンツを作れるようになっています。これすごくいいと思う!私も将来ユーチューバーになりたいんだけど、台本作りとかに使えそう♪
創造プロセスの変化: 多くのクリエイターがAIをアイデア出しや下書き作成に活用し、人間がそれを編集・洗練するという新しい働き方が確立しつつあります。例えば、脚本家がストーリーの複数の展開をAIに提案させ、一番いいものを選んで発展させるという使い方が増えているみたい。
著作権と知的財産の新たな課題: AIが生成したコンテンツの著作権は誰にあるの?とか、AIの訓練に使われたコンテンツ制作者への適切な報酬はどうすべき?など、今までの法律では対応しきれない新しい課題が出てきています。正直、私にはまだ難しい話だけど、将来的に大事な問題になりそう。

ChatGPTで誰でもクリエイターに!でも著作権問題はどうなる…?🤔🎨
プライバシーとセキュリティへの懸念
ChatGPTの普及に伴い、プライバシーやセキュリティに関する心配も増えています。
データプライバシーの問題: ChatGPTに入力したデータがどう保存・利用されるの?企業の秘密や個人情報が漏れる危険はないの?といった心配が広がっています。実際、一部の大企業ではChatGPTの社内利用を制限する方針を設けているみたい。私も最初、自分の名前とか入力して大丈夫かな~って心配したけど、今は気をつけてます。
セキュリティリスク: AIを使ったフィッシング詐欺やフェイクニュースの拡散など、悪用される可能性も指摘されています。特に、高品質な文章が大量に生成できるようになったことで、詐欺メールの精度アップや偽ニュースの大量生成などが心配されてます。怖いですね…。
対策技術の発展: こうした心配に対応するため、AIが生成したコンテンツを検出する技術や、プライバシーを守りながらAIを訓練する方法(連合学習とか)の研究が進んでいます。
4. ChatGPTの限界と課題
ChatGPTがいろんな分野ですごい変化をもたらす一方で、いくつかの重要な限界や課題も見えてきています。
技術的限界
幻覚(ハルシネーション): ChatGPTは時々、存在しない情報や間違った回答を自信満々に言うことがあります。これを「AI幻覚」っていうらしいんですが、特に専門的な情報や最新の情報について顕著みたい。私も一度、架空の本について聞いたら、あたかも実在するかのように詳しく説明してきてびっくりしました!
文脈理解の限界: 長い会話や複雑な背景情報の理解にはまだ限界があって、会話が長くなるほど文脈の理解が難しくなる傾向があるみたい。私も長い質問すると、途中で話がズレてきたりすることあります。
知識の更新: ChatGPTの知識は訓練データの集めた時点で固定されるから、最新の情報や出来事については答えられないんです。(でも、プラグインとかBrowsingモードとかで、この制限を部分的に解決する試みもあるみたい)
バイアスと偏見: 訓練データに含まれる社会的バイアスや偏見がモデルの回答にも反映される問題が指摘されています。例えば、特定の職業や役割についてのステレオタイプを強化しちゃう可能性があるんです。AIも結局のところ、人間が作ったデータから学習してるから、人間社会の問題も引き継いじゃうんですよね…。

ChatGPTの限界、幻覚やバイアス問題…完璧じゃないから使い方に注意!🤔💡
社会的・倫理的課題
労働市場への影響: 一部の仕事では自動化による雇用の変化が予想されていて、特に定型的な文書作成や初級レベルのプログラミングなどの分野で影響が大きくなる可能性があるみたい。将来の仕事どうなるんだろう…心配。
デジタルデバイドの拡大: AI技術を使ったり活用したりする能力の差によって、既存の社会的格差がさらに広がる心配があります。お金持ちや教育レベルの高い人だけがAIの恩恵を受けて、そうでない人が取り残されるのは避けたいですよね。
依存性と批判的思考の低下: AIに頼りすぎることで、人間の批判的思考能力や問題解決能力が衰える可能性も指摘されています。確かに、最近友達と話してても「それってChatGPTに聞いた?」って会話になることが増えたかも…。自分の頭で考える機会が減ってるかも。
著作権と知的財産権: AIが生成したコンテンツの著作権や、訓練データとして使用されたコンテンツの権利関係など、法的な整備が追いついていない問題があります。
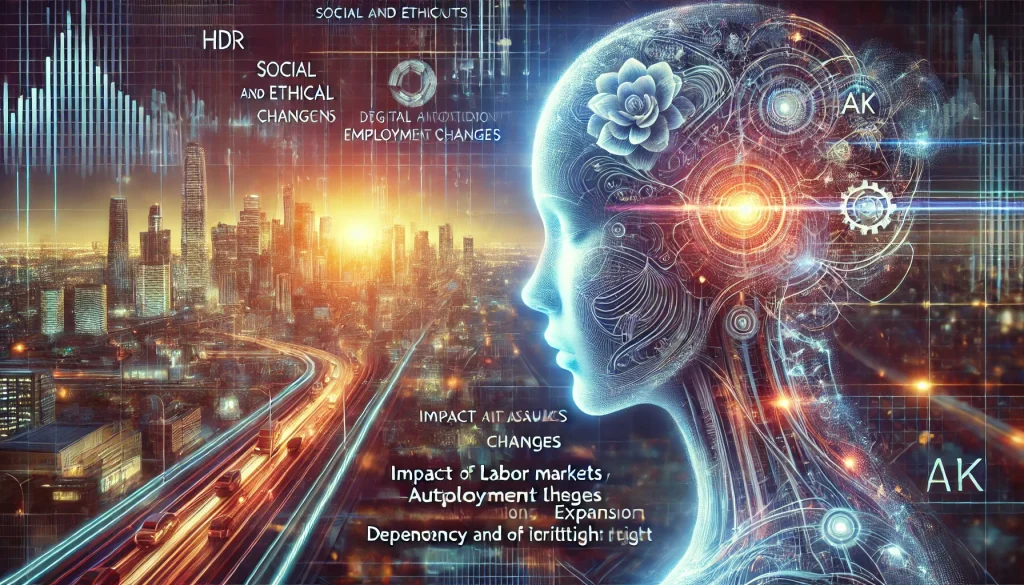
5. ChatGPTが開く新しい未来への扉
これらの課題がある一方で、ChatGPTをはじめとする生成AI技術は、私たちの社会にたくさんの可能性をもたらしています!
知識へのアクセス民主化
地理的・経済的な制約を超えて、質の高い情報や教育コンテンツへのアクセスが可能になります。例えば、世界中のどこにいても、自分のペースで学べるAIチューターが実現できそうです。私、これめっちゃいいと思う!塾に行けない子でも、AIが先生になってくれるなんて素敵じゃない?
人間と機械の新たな共存関係
AIが定型的・分析的な作業を担当して、人間はより創造的・感情的・倫理的判断が必要な領域に注力するという、新しい役割分担が進むと思います。これによって、人間らしい能力がより重視される社会に変わっていくかも。結局、人間にしかできないことって何だろう?って考えるきっかけにもなってると思います。

AIとの共存、人間にしかできないことって何だろう?🤖💭
イノベーションの加速
AI支援によって研究開発や問題解決のプロセスが効率化されて、科学的発見や技術革新のスピードが速くなる可能性があります。例えば、新薬開発や材料科学などの分野では、AIが膨大な可能性を探索することで、今までの方法では見つけられなかった解決策が見つかるケースが増えているみたい。医学の発展とかに貢献するなら、すごくいいことだよね!
コミュニケーションの変革
言語の壁を越えたリアルタイムコミュニケーションや、障害を持つ人々のためのサポート技術の発展など、人と人、人と情報のつながり方が根本から変わる可能性があります。例えば、自分の言葉を話せない人がAIを通じてコミュニケーションできるようになるって素晴らしいことだと思う!
まとめ:ChatGPTが開く新しい未来への扉
OpenAIの理念に沿って「人類全体に公平にAIの恩恵を届ける」ために登場したChatGPTは、たった数年でAI技術を一般社会に広めました。テクノロジーを民主化するという点では、すごく成功したと言えると思います!
でも一方で、AIの倫理的な使い方や安全性に関する議論は今も続いています。AIの発展スピードは法律や社会的な合意形成のプロセスより速くて、テクノロジーと社会のバランスを見つけることが今すぐ必要な課題になっています。
これから私たちはAIとどう向き合い、どうやって共存していくべきか真剣に考える時代に入ってきたと思います。AIを単なる道具としてじゃなくて、私たちの社会や文化を形作る大切な要素として捉えて、その発展に積極的に関わっていくことが必要なんじゃないかな。
私自身、中学生ながらこの記事を書いていて思ったのは、AIってただ便利なだけじゃなくて、私たちの未来を大きく変える力を持ってるってこと。だからこそ、私たち若い世代こそAIについてちゃんと学んで、上手に付き合っていく必要があると思うんです。学校でもAIリテラシーの授業があったらいいのにな~って思います!
おわりに
ChatGPTを理解することは、私たちがAI時代を生き抜くための第一歩だと思います。技術のことだけじゃなくて、AIが社会に与える影響や倫理的な問題についても考えを深めることが大切です。
ぜひみなさんも実際にChatGPTを使ってみて、そのすごさを体感してみてください!ただ使うだけじゃなくて、「どうやって使うか」「何のために使うか」を自分なりに考えながら使ってみるといいと思います。そうすれば、AIとの新しい関係を自分で見つけられるはず!
この記事を読んで、あなたがAIやChatGPTに対して思ったことや質問があれば、ぜひコメントで教えてくださいね♪ 私も日々勉強中の身なので、みなさんと一緒に考えていけたら嬉しいです!
あ、最後に言っておきたいんですけど、AIは確かにすごいけど、人間にしかできないことはたくさんあると思います。だから、AIを恐れるんじゃなくて、上手に活用して、人間らしさを大切にしながら未来を作っていけたらいいなって思ってます!
それではまた次回の記事でお会いしましょう~!
(執筆:夢子)
P.S. 勉強も頑張らなきゃ…明日理科のテストだった(汗)

ChatGPT #AI #人工知能 #技術革新 #社会変革



コメント